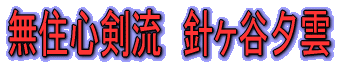
![]()
五
次の日の朝、朝稽古を終えて、岩屋の前で朝飯を食べている時、お鶴はやって来た。 昨日とは違って、やけに派手な着物を着ていた。昨日は喪服のせいか、寂しそうな感じだったが、今日は華やいでいる。昨日よりも若々しく見え、派手な着物がよく似合っていた。着物いっぱいに梅の花が咲き乱れ、うぐいすが飛び回っている。 下界はもう春じゃな‥‥と着物を眺めながら五郎右衛門は思った。 「おはようさん」とお鶴は笑いながら言った。さわやかな笑顔だった。 「おはよう」と飯を食べながら返事をした。 「お寒いですね」とお鶴は焚き火にあたった。「でも、今日もいいお天気になりそう。五右衛門さん、もし、雪が降ったらどうするんですの」 「わしは五郎右衛門じゃ。雪が降っても変わらん」 「雪が吹雪いていても、木剣を振るんですか」 五郎右衛門はうなづいた。 「風邪ひきますよ」とお鶴は岩屋の方を見た。 岩屋の入口の上に太くて長い 「そんな事はない」と五郎右衛門も氷柱を眺めながら言った。 「そう、強いのね」 お鶴は五郎右衛門の隣にしゃがむと、 「毎日、自分でご飯、作ってらっしゃるの」 お鶴は鍋の中をかき回した。 「当然じゃ」 五郎右衛門はお鶴から 「悪いな。そなたも食うか」 お鶴は首を振った。 「ねえ、あたしが作ってあげましょうか」 お鶴は五郎右衛門に笑顔を見せた。 いい女じゃ‥‥‥と五郎右衛門は思ったが、心とは裏腹に態度はそっけなかった。 「いらん。そなたは毎日、何してるんじゃ」 「あたし? あたしは毎日、何やってんだろ」 突然、ドサッという音がして松の木から雪が落ちて来た。 お鶴は驚いて振り返った。五郎右衛門は平気な顔で飯を食っていた。 「あまり、そういう事、気にしないのよ。要するに暇なのかしら」 五郎右衛門は お鶴は焚き火に手をかざし、笑みをたたえたまま五郎右衛門を見ていた。 「寺では何かをしてるんじゃろ」 「そうね。和尚さんのご飯を作ったり、洗濯をするくらいよ。夜になれば和尚さんとお酒を飲んでるわ」 「亡くなった御亭主の供養もしてるんじゃろ」 「そうね、それもしてるわ。急に死んじゃったんですものね」 五郎右衛門は雑炊をかっ込んだ。お鶴に見つめられて、何となく食べずらかった。 「仇を討つのか」 「討つわ。あなた、助けてくれるんでしょ」 「縁があったらじゃ。相手はどんな男じゃ」 お鶴は脇に積んである枯れ枝を一本引き抜くと焚き火にくべた。 「人から聞いた話だとね、髭面の大男だったって言ってたわ。それと確かな事は夫よりも強い男よ」 「それだけか」 「うん‥‥‥」 お鶴は目を丸くして五郎右衛門を眺めながら、「まるで、あなたみたいじゃない」と言った。 「わしかもしれんな」と五郎右衛門は無精髭を撫でた。 「あなたであるわけないでしょ」 お鶴は立ち上がると岩屋の側まで行き、中を覗いた。 「御亭主の名は?」 「川上新八郎」 「知らんな」 五郎右衛門はまた、お代わりをした。 お鶴は岩屋の入口の所にある岩の上に腰を下ろすと、上から落ちて来る滴を見つめた。 「ねえ、五右衛門さん。あなた、何人ぐらい人を殺したの」 「わしは五郎右衛門じゃ」 「あら、御免なさい。でも、どっちでもいいじゃない」 「五右衛門というのは 「あっ、そうか。なんか聞いた事あると思ってたのよ。石川五右衛門でしょ。 「わしは五郎右衛門じゃ」 「わかったわ、五郎右衛門さん。で、何人殺したの」 「数えた事はないが相当な数じゃろうな」 「ふうん‥‥‥」 お鶴は落ちて来る水滴を手を伸ばして、手のひらで受けていた。 「女は?」 「女など殺さん」 「ふうん。でも、泣かせた女はいるんでしょ」 「そんなもんは知らん」 「お尻が冷たいわ」と言うとお鶴は腰を上げて、焚き火の方に尻を向けて暖まった。 五郎右衛門はお鶴の尻を眺めながら雑炊を食べていた。 「ねえ、ほんとはかなりいるんでしょ」 「何が」 「泣かせた女よ」 「ああ、百人じゃ」 「ほんと?」とお鶴は振り返って目を丸くした。 「ああ。そなたを入れりゃあ百一人になる」 お鶴は笑った。お鶴の尻が揺れていた。 「面白い人。あたしを泣かす気?」 「ああ、そのケツをひっぱたいてな」 「フフフ、そのうちね」 お鶴はまた岩屋の入口まで行くと、中を覗き込んだ。 「ねえ、この お鶴の声が岩屋の中に響いた。 「ああ。中はあったかいぞ」 「ほんと? 入ってもいい?」 「どうぞ」 お鶴は振り返り、五郎右衛門を睨んだ。 「あたしに、一人でここに入れっていうの」 「入りたいんじゃろ」 「普通、案内してくれるじゃない」 「わしは案内人じゃない」 「いじわるね」 五郎右衛門は焚き火の中から火の付いた手頃な棒切れを取り出すとお鶴に渡した。 「これで行けっていうの」 五郎右衛門はうなづいた。 「ねえ、ローソクはないの」 「そんな贅沢なもんはない」 「そうなの。今度、持って来てあげるわ。あれがあれば便利よ」 お鶴は棒切れの火で岩屋の中を照らしたが、奥が深くて何も見えなかった。 「ねえ、お願い、案内して」とお鶴は五郎右衛門の着物を引っ張った。 五郎右衛門はしょうがないと腰を上げ、火の付いた棒切れを持つと岩屋の中に入って行った。お鶴は恐る恐る五郎右衛門の後ろに付いて行った。 「何だか怖いわ。熊なんていないでしょうね」 「熊はいないが、鬼が出る」 「やだ、脅かさないでよ」とお鶴は五郎右衛門の帯をつかんだ。 「ここから狭くなるぞ」と五郎右衛門はお鶴の手を取った。 入口の辺りは一 お鶴は両方を照らしてみた。どちらも先まで見えなかった。 「こっちに行きましょ」と左側を示した。 五郎右衛門はお鶴の手を引いて左に曲がった。三間程、進むと行き止まりとなり、そこは一間四方の空間となっていた。 「ここは食料置き場じゃ」と五郎右衛門は米やら野菜やらを照らして見せた。 「へえ‥‥‥随分と溜め込んだじゃない」 二人は元の道に戻り、奥へと進んだ。また二手に分かれ、真っすぐに進むとまた、行き止まりとなった。行き止まりの岩壁に観音像らしき物が彫ってあった。 「凄いわね。これ、誰が彫ったの」 お鶴は観音像を照らしながら眺めていた。 「よくは知らんが何百年も前のものじゃないのか。多分、この岩屋を掘った連中の守り本尊だったんじゃろう」 「へえ‥‥‥」 五郎右衛門は引き返した。お鶴は慌てて、後を追った。左側に曲がってしばらく進むと広い場所に出た。三間四方程の広さのある、そこは五郎右衛門が寝起きしている場所だった。片隅に 「いい所じゃない」とお鶴は部屋の中を見て回った。 隅の方に縄が張られ、稽古着やふんどしが干してあった。お鶴は干し物を照らしながら、「どうして、こんな所に干すの」と聞いてきた。 「外に干しといたら凍っちまったんでな」 五郎右衛門は焚き火に火を点けていた。 「凍る前に取り入れればいいでしょ」 「そう思ってたんじゃがな、つい、忘れたんじゃ。そなたのように暇人じゃないんでのう」 焚き火が燃え、部屋の中は明るくなった。 「やっぱり、ローソクは必要よ」とお鶴は言った。 お鶴は岩棚の上に並んでいる二つの木像を見つけ、側に行って眺めた。 「これ、可愛いわ」 「それは、わしが彫った」と五郎右衛門も岩棚の方に行った。 「へえ、ほんと? あなた、凄いのね。この二人はあなたの昔の女なの」 「馬鹿言うな。観音様と弁天様じゃ」 「えっ、これが? あっ、そうか。こっちが弁天様で、こっちが観音様ね。でも、この観音様、おかしいわ。観音様って、こんな厚ぼったい着物なんて着てないわよ」 「そうなっちまったんじゃ」 「それに比べ、こっちの弁天様は寒そうだわ。何も着てないの」 「いいんじゃ」 「変なの」 お鶴は岩棚の下にあった彫り掛けの木を手に取って眺めた。 「これは何を彫ってるの」 「 「摩利支天様て剣術の神様でしょ。亡くなった夫もよく摩利支天様を拝んでいたわ」 彫り掛けの摩利支天を置くと、もっと小さな木を取った。 「これは?」 「そいつはお椀じゃ」 「へえ。お椀も作るの」 「何でも作る。箸も杓子も木剣もな」 「器用なのね」 お鶴は藁の上に腰を下ろした。 「結構、住み易そうじゃない」 「ああ、最高の穴蔵じゃ」 五郎右衛門は焚き火越しに、お鶴を見ていた。お鶴という女と一緒に、ここにいるという事が不思議に思えた。もしかしたら、また、変な夢でも見ているのでは、と疑った。 岩屋の中にいると昼も夜もわからず、時間の感覚がなくなってしまう。そのうちに、夢なのか お鶴は藁の上から立ち上がると、さらに奥の方を覗いていた。 「ねえ、まだ、先があるんでしょ」と言うお鶴の声で、五郎右衛門は目を開け、「ああ」と返事をした。 「出口に向かうだけじゃがな」 五郎右衛門は夢なら夢でも構わんと、火の付いた棒切れを持つと、お鶴の手を取って奥へと進んだ。だんだんと穴は狭くなり、曲がりくねった所を腰を曲げながら進んで行くと、ようやく、外の光が見えて来た。 氷柱におおわれた穴から顔を出すと、そこは崖になっていて、下まで二 「何で、こんな所に出口があるの」 お鶴は崖下を覗いた。 「掘り方を間違えたんじゃないのか」 「ここから下に降りられるの」 五郎右衛門は岩壁にかけてある綱を示した。「非常の時はこれを使って逃げる。そんな事はないと思うがの」 二人は来た道を引き返して入口に戻った。お鶴はキャーキャー言いながら先に立って歩き、時々、驚いては五郎右衛門にしがみついていた。 「ああ、面白かった」とお鶴は焚き火にあたりながら言った。 「今度、お寺からローソクをいっぱい持って来るわね。ずっと、住みよくなるわ」 「悪いな。ところで、その寺の和尚っていうのはどんな男なんじゃ」 「 「へえ、偉い坊主なのか」 「さあ、ちっとも偉くなんか見えないわ。大した坊主じゃないんでしょ。面白い人だけどね。でも、京都のお寺で修行したとか言ってたから、ほんとは偉い和尚さんかもね」 「何宗なんじゃ」 「 「臨済禅か‥‥」 五郎右衛門は修行の中に座禅を取り入れていたが、正式に禅僧のもとで修行したわけではなかった。最初の師匠である大森勘十郎が座禅をしていたのを真似したのが始まりだった。臨済宗だの 「ねえ、あなた。また木剣を振るの」とお鶴が聞いた。 「ああ」と五郎右衛門はさっき食べ残していた雑炊を食べながら、うなづいた。 「どうして、かなり強いんでしょ」 「わしの剣はまだまだじゃ」 「よく昔の人が山奥で修行して、悟りを開いたとか聞くけど、あれね? 悟りを開くまでここにいるの」 「まあ、そういう事じゃな」 「頑張ってね。あたしも応援するわ」 五郎右衛門はお椀と箸を空になった鍋の中に放り投げると、木剣を持って立ち上がった。 「今晩、お酒、持って来るわね。それと、ご飯も作ってあげる」 五郎右衛門はいつもの立ち木の前まで行くと新陰流の形の稽古を始めた。 お鶴は焚き火にあたりながら、五郎右衛門の稽古を眺め、ニコッと笑った。
|