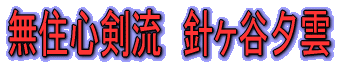
![]()
七
次の日の朝、五郎右衛門はお鶴に起こされるまで、ぐっすりと眠っていた。 お鶴は五郎右衛門の体の上にまたがり、筋肉の盛り上がった胸を撫でていた。 「朝か」と五郎右衛門は目を開けると聞いた。 「わかんない」とお鶴は首を振って、五郎右衛門の体の上に上体を倒した。 五郎右衛門は優しく、お鶴を抱きしめた。お鶴を抱きながら首を傾けて、焚き火の方を見た。焚き火は燃え、所々にローソクが灯っていた。 「お前が火を点けたのか」 お鶴は五郎右衛門の胸の上でうなづいた。 五郎右衛門はお鶴の長い髪を撫でた。 「ねえ、滝に打たれるの」 「ああ」 「寒くないの」 「寒いさ‥‥‥寒いが、そのうちに体が熱くなって来る」 「風邪ひかないでね」 「ああ‥‥‥ 「覚えてたの」とお鶴は顔を上げた。 「忘れてくれればよかったのに‥‥‥」 「わしはできるが、そなたは忘れられまい」 「そうね‥‥‥仇を討たなくちゃね」 「戦闘開始じゃな」 「‥‥‥でも、まだ、夜かもしれないわ」 お鶴は五郎右衛門の胸を撫でていた。五郎右衛門はお鶴を抱き締めた。 どうして、お鶴の仇がわしなんじゃ‥‥‥五郎右衛門は運命を恨んだ。ずっと、このまま、お鶴を抱いていたかった。お鶴の言う通り、まだ、夜なのだという事にしておきたかった。岩屋から出ない限り、いつまで経っても明日は来ないと思いたかった。しかし、五郎右衛門は意を決して、お鶴を下ろした。 お鶴の顔を見ないようにして立ち上がると、ふんどしを締めた。 「それ、洗った方がいいわ」とお鶴が後ろで言った。 「滝で洗う」と五郎右衛門は振り返った。 裸のお鶴が座っていた。ぼんやりした顔をして五郎右衛門を見上げていた。 五郎右衛門の心がまた傾きかけた。お鶴から目をそらし、慌てて着物を着ると刀をつかみ、お鶴から逃げるように外へと飛び出した。 外は雪が降っていた。何もかもが真っ白だった。 『こんな日は修行なんかやめて、お鶴と一緒に楽しく過ごそう』と誰かが言った。 『馬鹿言うな、 五郎右衛門は岩屋の入り口で寒そうに足踏みしながら迷っていた。 『お鶴が待っている。一日くらい休んだって大丈夫さ』 「ウォー」と五郎右衛門は大声で叫びながら、甘い言葉を振り切るようにして雪の中に飛び出して行った。 冷たい滝に打たれた後の五郎右衛門は、昨夜の事はすっかり忘れたかのように、決められた日課をこなして行った。 いつもと変わらぬ一日だった。しかし、お鶴が側にいた。 お鶴は一旦、寺に帰って着替えて来た。なんと今度は男の格好をして 男装姿のお鶴は食事の支度をしてくれた。そして、どこからともなく飛び出して来ては、五郎右衛門に斬り付けて来た。 飯を食っている時、木剣を振っている時、突然、どこからか現れ、五郎右衛門にかかって来た。五郎右衛門はお鶴の刀を軽くかわし、お鶴の事など完全に無視しているがごとく、飯を食い続け、木剣を振り続けていた。 座禅をしている時は、後ろから忍び寄って斬ろうとするのだが、どういうわけか、お鶴は投げ飛ばされ、五郎右衛門は座禅をしたままだった。何度やっても同じだった。五郎右衛門を斬るどころか、触れる事さえできなかった。それなのに、お鶴の体は傷だらけになっていった。 お鶴は五郎右衛門の敵ではなかったが、まったくの素人でもなかった。五郎右衛門は初め、お鶴が刀を振り回して、怪我をしなければいいがと心配した。ところが、お鶴の剣の腕は女とは思えない程、筋がよかった。武家の娘として、幼い頃から剣術の稽古を積んで来たに違いないと思った。五郎右衛門は簡単にお鶴の刀をよけているように見えるが、実は真剣だった。少しでも気を緩めたら、お鶴に斬られてしまうと常に気を張っていた。 「おい、その顔、どうしたんじゃ」と五郎右衛門は夕飯の時、とぼけて聞いた。 「なによ、あなたがやったんでしょ」 お鶴は 「綺麗な顔が台なしじゃのう」 「顔だけじゃないわ。体中、傷だらけよ。ほら見て」 お鶴は 「ねえ、どうしてくれるのよ」 「もう、諦める事じゃな」 「あたしだって、やめたいわよ」 「やめればいいじゃろ。こいつはうまいのう」 五郎右衛門はお鶴の作った 「おいしいでしょ。これでも、あたし、お料理、得意なんだから」 「仇討ちはやめた方がいいが、飯作りは続けてくれ」 「勝手な事言わないでよ。あたしはね、あなたを憎んでるのよ」 お鶴は雑炊を食べながら五郎右衛門を睨んだ。 「どうして」 「まったく、あなたは鈍感なの。あたしの夫を殺したのはあなたなのよ。あたしは夫を愛してたのよ。とても、とても愛してたのよ。あなたを憎むのは当然でしょ」 お鶴は箸を振り回しながら、しゃべった。 「そりゃそうじゃ」 「でもね、あたし、うまく、あなたを憎めないのよね。どうしてかしら」 「わしがいい男だからじゃろう」 「あなた、冗談を言ってる場合じゃないのよ」 お鶴は箸とお椀を置くと立ち上がり、五郎右衛門に詰め寄った。 「あたしたち仇同士なのよ。ねえ、わかってるの。こうやって一緒にご飯を食べてる事だって、ちょっと、おかしいんじゃない」 「そうでもないぞ。わしは楽しい。今晩も一緒に酒を飲もう」 「あなたは全然、わかってないわ」 お鶴は五郎右衛門に背を向けると雪景色を眺めた。 雪はもう、やんでいた。 お鶴は小川の方を眺めてから、焚き火の側にしゃがんで、のんきに雑炊を食べている五郎右衛門を見つめた。 「ねえ、あなた、こんな所、人様に見られたらどうすんの。あたしの立場がないじゃない。人はみんな、噂をするわ。亭主が死んで、まだ一年も経ってないのに、他に男を作って一緒にお酒を飲んで遊んでるって。みんな、あたしに後ろ指さすのよ。もっと 「どこに世間体ってものがあるんじゃ」 五郎右衛門は辺りを見回した。 「確かに、ここにはないけど。いいでしょ。あたしはあたしに言い聞かせてるのよ。あたしだって、ほんとは今晩もあなたと一緒にいたいの。ずっと、あなたと一緒にいたいの。でも、それはいけない事なのよ。絶対にいけない事なの。だから、あたしはもう帰るのよ。止めたって、あたしは帰るわ。絶対に帰るんだから」 お鶴は焚き火を見つめながら手のひらを火にかざしていた。焚き火の中の燃えさしを手に取ると灰の上に何かを書いていた。 「帰る、帰るって言ってるが、まったく、帰る気配なんて見えんのう」 「うるさいわね。あたしは自分に言い聞かせてるって言ったでしょ。そんなにあたしに帰ってもらいたいの。いいわよ。もう、あんたなんか勝手にするといいわ」 お鶴は立ち上がり、五郎右衛門の木剣をつかむと、それを杖代わりにしてヨタヨタと帰って行った。 「おい、お鶴さん」と五郎右衛門はお鶴の後ろ姿に声を掛けた。 「おぬし、面白い 「ふん。もう、体中、痛くてしょうがないよ。明日はきっと起きられないわ」 お鶴の後ろ姿を見送りながら五郎右衛門は可愛い女じゃと思っていた。
いい天気だった。 昨日、積もった雪が光って眩しかった。 下界ではもうすぐ、桜の咲く時期なのだが、山の中はまだまだ寒かった。 五郎右衛門は今日も飽きずに木剣を振っていた。新陰流、 昨日は相当まいったとみえて、今朝、お鶴は来なかった。五郎右衛門は木剣を振りながらも、お鶴の事が気になっていた。 楽しそうなお鶴の笑顔‥‥‥傷だらけになって、ふくれているお鶴の顔が思い出され、五郎右衛門はつい吹き出してしまう。 これではいかん、と、お鶴の事を断ち切るように木剣を振っても、お鶴の事が頭から離れなかった。夢のようなあの夜の出来事が鮮明に思い出され、五郎右衛門の手は止まり、呆然と立ち尽くした。 小川を誰かが歩いて来る音がした。お鶴が来た、と思って五郎右衛門は振り返った。 お鶴ではなかった。分厚い綿入れを着込んだ坊主頭だった。坊さんが裾まくりして、 和尚はニコニコしながら側まで来ると、じっと五郎右衛門の顔を見つめた。太く垂れ下がった眉毛の下の目はとぼけていたが、その顔には厳しい修行の跡が刻まれていた。 「ホッホッホウ」と言いながら和尚は杖を突き、五郎右衛門の回りを一回りして、五郎右衛門を上から下まで、じっと眺めた。 お鶴の言った通り、ちょっと変わった和尚のようだった。 「成程、うむ、成程のう‥‥‥お鶴が惚れるのも無理ないわい」と和尚は満足気に何度もうなづいた。 五郎右衛門は木剣を下ろすと、「お鶴さんは大丈夫ですか」と聞いた。 「なに、あの女子はそんなやわじゃない。今は痛い痛いと騒いどるが、明日になれば、ケロッと元気になるじゃろう」 五郎右衛門もそう思っていた。明日になれば、また、斬り掛かって来るに違いない。 「ちょっと、お鶴に頼まれてのう。おぬしを斬って来いって言われたんじゃ」 和尚は杖に両手を乗せて、五郎右衛門を見上げ、笑っていた。 五郎右衛門は和尚の杖に注目した。刀が仕込んであるのかとよく見たが、ただの黒光りした年期の入った杖だった。 「わしを斬る?」 「なに、坊主は 「わしは殺し屋ではない」 五郎右衛門は右手を振った。 「似たようなもんじゃ。人斬り包丁など振り回しておるのは人を殺すためじゃろ」 和尚は杖で五郎右衛門の腰の脇差を示した。 「違う」 「悟るなどと無駄な事はやめて、さっさと山を下りた方がおぬしのためじゃ」 「わしが何をしようとわしの勝手じゃ」 五郎右衛門は和尚を無視して、立ち木に向かって木剣を構えた。 「そりゃそうじゃがの。無駄じゃと思うがの」 「無駄ではない」と五郎右衛門は立ち木を打った。 木の上から雪が落ちて来て、二人の回りに舞った。 「今のおぬしの剣は完全に死んどるのう」と和尚は笑った。 五郎右衛門は木剣を構えたまま和尚を睨んだ。 「今のおぬしの剣では、わしのような坊主でさえ斬れんじゃろう」 和尚は五郎右衛門に近づくと顔を近づけて木剣を眺めた。 「わしの剣は、そんなへなへな剣ではない」 五郎右衛門は木剣を引いた。 「試してみるかな」 和尚は五郎右衛門を馬鹿にしたような笑みを浮かべた。 「わしは坊主を斬る剣など持ってはおらん」 五郎右衛門は和尚を無視した。 「 五郎右衛門はその杖を木剣で受け止めた。 「どうじゃな。わしを打ってみる気になったかな。立ち木よりは、わしの方が手ごわいぞ」 「よかろう。それ程、叩かれたいと申すなら、叩いてくれるわ」 五郎右衛門と和尚は二間程離れて立った。五郎右衛門は木剣を 「構えろ!」 「わしは坊主じゃ。剣の構えなど知らん。遠慮せずにかかって来い」 生意気な、くそ坊主め! 軽く、小手でも打ってやるかと思った。が、なぜか、打ち込む事ができなかった。和尚を見ても隙だらけだ。しかし、打ち込む事ができない。こんな事は初めてだった。目の前の和尚が、やたらと大きく見えてきた。 五郎右衛門は木剣を中段の清眼から上段に振りかぶった。それでも、どうする事もできない。まるで、金縛りにあったかのように、足を動かす事さえできなかった。 しばらく、二人は石のように動かず、向かい合っていた。 「どうじゃな」と和尚が声を掛けた。 「くそっ、負けた‥‥‥」と五郎右衛門は木剣を下ろした。 「わからん‥‥‥なぜじゃ。なぜ、わしは打ち込めなかったんじゃ」 五郎右衛門は足元の泥を見つめた。 和尚は五郎右衛門に近づきながら、「おぬしの心は何かに 五郎右衛門は顔を上げて和尚を見た。 「何かに囚われている?」 和尚はうなづいた。 「だから、わしを打つ事もできん。多分、今のおぬしは自分の剣に疑問を持っているんじゃろう。剣術というのは人を殺すための技術じゃ。ところが、おぬしは、その人を殺すという事に疑問を持った。そうじゃないかな」 「確かに、そうかもしれん」と五郎右衛門はまた、うなだれた。 「難しいのう」と和尚は言った。 五郎右衛門は顔を上げると和尚を見つめた。 和尚は杖の上に両手を乗せ、静かな顔付きで遠くを眺めていた。半ば白くなった 「和尚は一体、何者なんです」 「わしはただの禅坊主じゃ」 和尚はそう言ったが、偉い和尚に違いないと五郎右衛門は思い始めていた。 「少々、 「和尚、わしは一体、どうしたらいいんじゃ」 五郎右衛門は和尚に救いを求めた。この和尚なら問題を解決する糸口を見つけてくれるに違いないと信じ切っていた。 「そうじゃのう」と和尚は首の後ろを掻いた。「まず、お前の体に染み付いている新陰流をすっかり忘れる事じゃな」 「新陰流を忘れる?」 和尚の言った言葉があまりにも以外だったので、五郎右衛門は戸惑った。 「そうじゃ。木剣振るべからず、座禅すべし。飯食うべからず、座禅すべし。眠るべからず、座禅すべし」 そう言うと和尚は背中を丸めて、スタコラと帰って行った。 『新陰流を忘れろ』とは、どういう意味なのか五郎右衛門にはわからなかった。
|