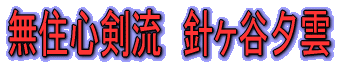
![]()
八
和尚の言われるままに、五郎右衛門はさっそく座禅を始めた。 岩屋の入口、いつも、飯を食べる場所に、でんと腰を落ち着け、目を閉じ、足を組み、座禅を始めた。 新陰流を忘れろ‥‥‥ 新陰流を忘れろという事は、剣術を忘れろという事か。剣術を忘れろという事は、刀を捨てろという事か。刀を捨てろという事は、お鶴に斬られろという事か。お鶴に斬られるという事は、死ねという事か。お鶴に斬られて、わしはこの雪山で死ぬのか‥‥‥いや、斬られるわけにはいかん。お鶴には悪いが、 新陰流を忘れろ‥‥‥ お鶴は今、何してるんじゃろ。痛い、痛いと泣いているのか。いや、あの女が泣くわけがない。傷口をなめながら、じっと痛みに耐えているに違いない。 可哀想に‥‥‥どうして、あんな 川上新八郎‥‥‥お鶴はわしが斬ったと言うが、どう考えても思い出せん。お鶴の亭主がどんな男だったか、まったく思い出せん。去年の夏の始めだとお鶴は言った。確かに、その頃、わしは試合をして人を斬っている。しかし、その男の名が川上新八郎だったのか、どうしても思い出せん。 お鶴は仇の名は針ケ谷だと言った。針ケ谷を名乗る武芸者はほとんどいない。やはり、わしがお鶴の仇なのか‥‥‥ いかん、お鶴の事は関係ない。 新陰流を忘れろ‥‥‥ 新陰流は、 苦しい修行に耐えて、ようやく勝ち取った新陰流の極意を忘れろというのか。わしから新陰流を取ったら何も残らん。新陰流を忘れたら何もなくなってしまう。しかし、今のわしはあの和尚を打つ事もできん。わしは一体、何のために剣術をやって来たんじゃ。 剣によって両親は殺された。無残に殺された‥‥‥わしは絶対に仇を討つと誓った。両親の仇を討つために剣術を習った。多分、あの時のくだらん足軽は戦で死んだ事じゃろう。いや、戦場から逃げ出したに違いない。今、生きているとすれば、五十歳前後か。どうせ、まともに五十まで生きられるはずはない。きっと、もう、死んでいるはずじゃ。 関ヶ原の原因を作った徳川家康も死んだ。結局、仇は討てなかった‥‥‥仇を討つどころか、わしは剣で人を殺して来た。何の恨みもない者を何人も殺して来た。自分が強くなるために、わしは人を殺して来た。 お鶴の亭主も殺した。お鶴のように なぜ、こうなるんじゃ。 剣というのは所詮、人殺しの道具に過ぎんのか。わしの親が剣によって殺される。そして、今度はわしが誰かの親を剣によって殺す。そして、次は、わしが誰かに剣によって殺される。この繰り返しじゃ。ぐるぐる同じ事が繰り返される。剣を捨てたからといって解決するもんじゃない。今、わしが剣を捨てたら、お鶴が喜んで、わしを斬るじゃろう。 お鶴‥‥‥男装姿のお鶴もなかなか色っぽかった。いかん、また、お鶴じゃ。お鶴は関係ない。 新陰流を忘れろ‥‥‥ あの和尚め、わからん事を言いやがって。 そういえば、観音様がわしの剣術は 畜生兵法‥‥‥弱い者には勝ち、強い者には負け、互角の者とやれば相打ち‥‥‥当たり前じゃろ、そんな事。 畜生、わからん‥‥‥ 木剣振るべからず、座禅すべし。 飯食うべからず、座禅すべし。 眠るべからず、座禅すべし‥‥‥ あのくそ坊主め、何もしないで座っていたからといってわかるわけねえじゃろう。しかし、なぜ、わしはあの坊主を打つ事ができなかったんじゃ。 わからん‥‥‥ 不思議じゃ‥‥‥ もしかしたら、あの坊主、天狗か何かか。昔、 新陰流を忘れろ‥‥‥ 新陰流を忘れろ‥‥‥ 師匠は今頃、どうしてなさるか。もう年じゃからな‥‥‥兄弟子の神谷(後の伝心斎)さんはどうしてるじゃろ。神谷さんちの腕白坊主も、もう大きくなってるじゃろうな‥‥‥松田、野口、中川、岡田、竹内、柏木、みんな、元気でやってるかのう‥‥‥お雪はもう嫁に行ってしまったじゃろうな。可愛い娘じゃった‥‥‥あの時、お雪は泣いていた。わしは、そんなお雪を置いて旅に出てしまった。 江戸か‥‥‥久し振りに帰りたくなったのう。こんな事をやめて帰るか。いや、駄目じゃ。帰ったからといって、何も解決せん。 新陰流とは? 新陰流を忘れるとは? 「五右衛門さ〜ん、元気?」とお鶴の声がした。 五郎右衛門は目を開けた。 もう、日が暮れかかっていた。焚き火の火も消えかかっている。 お鶴が男装姿のまま五郎右衛門の木剣を杖代わりに突きながら、一升どっくりを抱いて、片足を引きずるようにして、こちらに向かって来た。 五郎右衛門の顔を見るとニコッと笑って、「また、来ちゃった」と言った。 「どうしたんじゃ、その足」 「何でもないのよ。ちょっと凝ってるだけ。昨日、ちょっと、はしゃぎ過ぎた罰よ」 「なにも、そんな足で無理して来なくてもいいじゃろ」 五郎右衛門はお鶴の顔を見て嬉しかったが、言葉は素直には出て来なかった。 「なによ、和尚さんに聞いたわよ。あたしが来ないので、あなたがしょんぼりしてるって」 「あの坊主、そんな事、言ったのか」と五郎右衛門は髭を撫でた。 「そうよ。だから、わざわざ来てあげたんじゃない。それにさ、あたしもにっくきあなたの顔を見ないと落ち着かないしね。あっ、これ、御免なさい」 お鶴は木剣を返した。 「お稽古できなかったでしょ」 「いや。木剣は一つだけじゃないからの。お前、まだ、それが必要なんじゃないのか」 「優しいのね。じゃあ、もう少し借りとくわ」 お鶴はとっくりを置くと焚き火に枯れ木をくべた。 「何してたの。火が消えちゃうじゃない」 「見ての通りじゃ」 「何もそんな所に座らなくても、穴の中のがあったかいでしょうに」 「わしの勝手じゃ。それより、まだ、わしを斬るつもりなのか」 「そうよ。隙を見つけたら斬るわよ。覚悟してらっしゃい」 お鶴は木剣を杖代わりにして腰の刀を抜いて見せたが、「いてて」と顔をしかめた。 「無理するな。わしはまだ当分、ここにいる。傷が治ってからかかって来い」 「そうね。今日はやめとこう」 お鶴は刀を 「さてと、憎き仇のためにご飯でも作ってやるか」 お鶴は汚れたままの鍋を持って小川に行こうとしたが五郎右衛門は、「今日はいい」と断った。 「えっ?」とお鶴は振り向き、腰をかがめると五郎右衛門の顔を覗いた。 「あたしの作ったご飯は食べられないっていうの」と額を突っついた。 「そうじゃない。あのくそ坊主に言われたんじゃ。剣も振るな、飯も食うな、夜も眠るな。そして、座禅をしろってな」 「へえ、あんな和尚の言いなりになるの」とお鶴はゆっくりとしゃがむと、五郎右衛門の顔のすぐ前で言った。 お鶴の目が五郎右衛門の目をじっと見つめていた。五郎右衛門は目をそらした。 「別に言いなりになるわけじゃないがな、毎日、剣を振っていても何も解決しなかったんでのう。ちょっと、やり方を変えてみようと思ったんじゃ」 「それじゃあ、当分、ご飯、食べないの」 「ああ‥‥‥その手にはのらん」 お鶴は五郎右衛門の脇差を抜き取ろうとしていた。五郎右衛門は脇差の 「ばれたか」とお鶴は笑ってごまかし脇差から手を放した。 「ねえ、夜も寝ないで座ってるの」 「ああ」 「体を壊したらどうするの」 「そしたら、お前がわしが斬ってくれ」 「そうか、それはいい考えよ。早く倒れてね」 「残念じゃが、そう簡単には倒れん」 「まあ、頑張ってね」とお鶴は木剣にすがって立ち上がった。 「あたし、お酒、持って来たんだけど、これも飲めないのね」 「ああ。持って帰ってくれ」と言って、五郎右衛門は目をつぶった。 「そうはいかないわ。せっかく苦労して持って来たんだもん。あたし、一人でも飲むわ」 「勝手にしろ」 「ええ。あなたはずっと座ってればいいのよ。あたしはご飯を食べて、お酒を飲んで、ゆっくりと寝るわ」
五郎右衛門は座っていた。 お鶴は五郎右衛門の目の前で飯を作って、わざと音を立てながら一人で食べた。 「ああ、おいしかった。食べ過ぎたわ。ほんとに食べないの。あなたの分もあるのよ」 五郎右衛門は目をつぶって黙っていたが、腹の虫はゴロゴロ騒いでいた。 「さてと、お酒でも飲もうかな」とお鶴はとっくりを揺すって酒の音を聞かせた。 五郎右衛門は唾を飲み込んだ。 「飯を食おうと酒を飲もうと構わんがのう、少し、静かにしてくれんか」 「あら、気が散るの? 修行がなってないわ。あたし、あなたの修行のお手伝いしてやってるのよ、わかる? 静かな所で座ってたって、何の修行にもならないわ。こんな山の中にいれば自然と心は落ち着いて来るものよ。でも、山から下りて町の中に戻ったら、また、心は乱れて元に戻っちゃうのよ。お寺の中にいるお坊さんが悟ったような顔をしていても、お寺から一歩出たら普通の人に戻っちゃうのと同じよ。そんなの悟りでも何でもないじゃない。本物の悟りっていうのは『真珠』みたいなものでしょ。本物の『真珠』っていうのは、どんなに汚れたドブ川に落ちたって、決して、汚れに染まったりしないで綺麗なままなのよ。あなたもそういう境地まで行かなきゃ駄目。わかる? あたしが側で騒いでいても全然、気にしない。うまそうな匂いがしても全然、気にしない。側で、あたしがうまそうにお酒を飲んでいても全然、気にしない。しかもよ、あなたのすぐ目の前に凄くいい女がいても全然、気にしない。その位にならなきゃ駄目よ」 「うるさい!」 五郎右衛門は怒鳴ると、お鶴に背を向けて座り直した。 「駄目ね。あなたは凄くいい環境の中で修行できるんだから、あたしに感謝しなけりゃ駄目なのよ。ねえ、一緒にお酒飲みましょ。おいしいわよ」 お鶴は五郎右衛門の正面に回って、音をさせながら酒をすすった。 「ねえったら」 五郎右衛門はまた、お鶴に背を向けた。 「 お鶴は酒の所に戻り、あぐらをかくと一人でグイグイやり出した。 「本物の『真珠』ってのはね、汚れる事なんて恐れないのよ。平気で汚れの中に入って行くの。それでも、ちっとも汚れない。汚れを避けてちゃ駄目だわ。汚い物に 五郎右衛門は目を開けた。 「飲む気になったのね」とお鶴は手をたたいて喜んだ。 「小便じゃ」と五郎右衛門は小川の方に向かった。 「あら、おしっこもしないんじゃなかったの」 「馬鹿者、垂れ流しなんかできるか」 「そんな中途半端な修行なんか、やめちゃいなさいよ」 「うるさい!」 五郎右衛門は帰って来ると焚き火の燃えさしを持って岩屋の中に入って行った。 「もう、やめるのね」とお鶴は嬉しそうに酒をぶら下げて五郎右衛門を追った。 お鶴が岩屋の中の広い部屋に行くと、五郎右衛門は焚き火も焚かず、一本のローソクだけを灯して、その前で座り込んでいた。 「まだ、やめないの。よく飽きないわね」と言いながら、お鶴は焚き火に火を点けた。 「一体、目なんかつぶって、なに考えてるの。あたしの事なんでしょ。ね、違う? ああ、つまんないの」 焚き火が燃えると、お鶴は五郎右衛門を見つめたまま、しばらく、音も立てずに黙っていた。五郎右衛門はお鶴の気配が消えたので、気になって目を少し開けてみた。 「やった。やった」とお鶴は喜んだ。 「やっぱり、あたしの事が気になるんでしょ。あたし、賭けてたのよ、あなたが目を開けるかって。もし、目を開けなかったら、あたし、泣いちゃったわよ。あたしって、そんなに魅力がないのかしらって。でも、よかった。やっぱり、あなた、あたしの事、好きなんだわ」 「うるさい!」と言うと五郎右衛門は目を閉じた。 「頑固ね、まったく‥‥‥」 お鶴は酒をあおった。 「もう、あんたなんかいいわ。あたし、一人でのんびりとやるわ。袴を脱いで、楽な格好になろう」 お鶴は腰の刀を抜くと、わざと音を立てて、袴を脱いだ。五郎右衛門がまた目を開けるだろうと期待していたが、五郎右衛門の反応はなかった。 「次いでだから、パァッと裸になっちゃおうかな。ここはあったかいし、裸になってお酒を飲もう」 お鶴は帯を解き、わざと衣ずれの音をさせて、「ほら、全部、脱いじゃった」と言ったが、五郎右衛門は歯を食いしばって、じっと耐えていた。 「五右衛門さん、やっぱり寒いわ」と言っても、しかめっ面をして座っているだけだった。 「ああ、つまんない。こうなったら、お酒をみんな飲んでやる」 お鶴は酒をすすった。帯を解いた時、小袖の 「そうだわ、ねえ、あなた、こういうの知ってる?」 お鶴は紙切れを拾うと広げた。 「今日ね、あたし、剣術の事、調べたのよ。お寺にね、剣術の本があったの。和尚さんに読んでもらってね。あたし、ちょっと写して来たのよ。いい、読むわね。初めは我が心にて迷うものなり。われと我が心の月をくもらせて、よその光を求めぬるかな。人の心を知る分別、第一なり。善も友、悪も友の鏡なる、見るに心の月をみがけば。やめる、捨てる、分けるも一つにも心次第なり。 「待て」 五郎右衛門は目を閉じたまま、左手をお鶴の方に出した。 「もう一度、心のっていう所から言ってくれ」 「いいわ。心の止まり居着く所あるうちは進む志しはなし。よしあしと思う心を打ち捨てて、何事もなき身となりてみよ」 「いいぞ、続けてくれ」 「 「ああ‥‥‥もしかしたら、そいつは新陰流じゃないのか」 「うん、そうみたい。上泉伊勢守の歌だって、和尚さんが言ってたわ」 「なに、伊勢守殿の歌か‥‥‥」と五郎右衛門は目を開いた。 「やはり、この山に伊勢守殿の歌が残っていたんじゃな」 「昔、ここで伊勢守っていう人が修行してたんですって」 「やはり、ここじゃったか‥‥‥そうか、伊勢守殿がここでのう‥‥‥」 五郎右衛門は一人で興奮していた。 「そうか、やはり、ここじゃったか」と岩屋の中を眺めながら何度も言っていた。 五郎右衛門は興奮が治まるとお鶴を見た。 「おい、どこが、すっ裸なんじゃ」 五郎右衛門の期待に反し、お鶴は袴を脱いだだけで、小袖を着たままだった。 「やっぱり、見たかったくせに。我慢するのは体によくないわよ」 お鶴はニコッと笑って酒を飲んだ。 「ふん」と五郎右衛門はまた目を閉じた。 「ねえ、五右衛門さん、あたしもね、これ読んで考えたのよ。この間の晩の事よ。あなたはいつでも回りに気を張って警戒してるわね。あたしを抱いてる時もあなたはそうだったわ。あたしはあたしで、あなたを刺してやろうと思いながら、あなたに抱かれてた。よくわからないけど、あなたがあの時、あたしの事を警戒してたから、逆にあたしはあなたを刺そうと思ったのかもしれない。結局は失敗しちゃったけどさ。もし、あの時、あなたがあたしの事を警戒しないで、あたしに夢中になっていてくれたら、あたしもあなたに夢中になっちゃって、あなたを刺す事なんて忘れちゃったかもしれないわ‥‥‥あたしにはよくわからないけど、『よしあしと思う心を打ち捨てて、何事もなき身となりてみよ』って、そういう事じゃないの。ねえ、違うかしら」 五郎右衛門は返事もしなかった。
五郎右衛門は一睡もせずに座り続けた。 お鶴は五郎右衛門の前で、持って来た酒を一人で全部、飲み干すと、時々、訳のわからない寝言を言いながら、気持ちよさそうに朝までぐっすりと眠った。 目を覚ますと焚き火を燃やし、座り込んでいる五郎右衛門に向かって、「お馬鹿さん、おはよう」と言い、五郎右衛門が返事もしないでいると、「なんだ、修行だなんて言って、座ったまま寝てるんじゃない」と五郎右衛門の鼻先を突っついた。 「うるさい!」と五郎右衛門は怒鳴った。 「あら、起きてたの? 御苦労様。それで、何か悟れた」 五郎右衛門は返事をしない。 「さてと、お寺に帰って朝風呂でも浴びよう。あなたもお風呂に入らない。気持ちいいわよ」とお鶴は出て行った。 五郎右衛門は疲れていた。 昨夜、お鶴が騒いでいた時は何も考える事ができなかったが、お鶴が寝てから、ずっと、考え続けていた。 新陰流を忘れ去るとは‥‥‥ 心の止まり居着く所あるうちは進む志しはなし‥‥‥ 心の止まり居着く所とは、新陰流の事か。 よしあしと思う心を打ち捨てて、何事もなき身となりてみよ‥‥‥ よしあしと思う心とは、新陰流の事か。 何事もなき身となりてみよ‥‥‥ しかし、今は考える事に、そして、座っている事に疲れ果て、頭の中は空っぽになっていた。 ただ、『わからん』という言葉だけが頭の中をグルグル回っていた。 五郎右衛門は目を開けた。 焚き火は勢いよく燃え、部屋中のローソクに火が点いていた。お鶴が酒を飲んでいたお椀は転がっていたが、とっくりは見当たらなかった。 五郎右衛門は立ち上がると体を伸ばし、お鶴が寝ていた藁布団を見た。お鶴は新しい藁束を全部ほぐして、藁をたっぷりと敷いて寝ていた。 「あのアマ、好き勝手な真似をしやがって」と五郎右衛門は舌を鳴らした。 お鶴が杖代わりにしていた木剣は残っていた。どうやら、足の痛みは治ったらしい。 五郎右衛門はその木剣を手に取って構えようとしたが、途中でやめて木剣を置いた。ローソクの火をすべて消すと岩屋から外に出た。 日差しを浴びて、雪が輝いていた。 五郎右衛門は体を伸ばすと冷たい空気を思い切り吸った。焚き火に火を点け、入口の所に座り込んだ。 お鶴は帰って来なかった。風呂から出て、和尚と一緒に朝飯でも食っているのだろう。 不思議な女じゃ‥‥‥ あの女、変な事を言ってたな‥‥‥わしがもし、お鶴に夢中になっていたら、刃物など向けなかったじゃろうと‥‥‥ 昔、馬術をやっていた時、『 くだらん。わしは何を考えてるんじゃ。 剣とは? 五郎右衛門は座り続けた。 昼頃、和尚がやって来た。 「おっ、やってるな。どうじゃ、何かわかったか」 「わからん」 「そうじゃろ、わかるわけない。目を開けて回りをよく見てみろ。暗い、暗い、おぬしだけが暗いわ」 「なんじゃと!」 五郎右衛門は目を開け、和尚を睨んだ。 「喝!」と和尚は叫んだ。 物凄い気合だった。五郎右衛門の体が一瞬、飛び上がったように感じられた。 「そんな抜けがら座禅などやってどうする、やめろ、やめろ」 「和尚が座れと言ったんじゃろう」 「ハッハッハッ、暗い、暗い」と笑いながら和尚は帰って行った。 「くそ坊主め、目を開けて回りを見ろじゃと‥‥‥回りを見たって何も変わっちゃいねえじゃねえか。回りを見ただけで悟れりゃ、こんな苦労するか」 五郎右衛門は座り続けた。しかし、今度は目を大きく開けて風景を睨んでいる。 和尚が帰ってから、しばらくすると、お鶴がやって来た。お鶴はさっぱりとした顔をして着物も着替え、女の姿に戻っていた。それでも腰にはちゃんと短刀が差してあった。 「あら、今度は目を開けて座ってんの。その方がいいわ。でも、焚き火くらい、ちゃんと点けなさいよ。まったく、あたしがいないと何もできないんだから」 お鶴はブツブツ言いながら、消えてしまった焚き火の火を点け、枯れ枝をくべた。 「ねえ、さっき和尚さんが来たでしょ。何か言ってた」 「ああ、今度は座禅なんかやめろじゃと」 「ふうん‥‥‥」 「昨日は何もしないで座ってろと言ったくせに、今日は抜けがら座禅なんかやめろと言いやがった」 お鶴は腹を抱えて大笑いした。 「あなた、和尚さんに遊ばれてんのよ」 「なんじゃと」 「怒っちゃ駄目よ。怒ったら、和尚さんの思う 「わからん」 お鶴は笑い続けたまま、汚れた鍋や器を抱えて小川の方に行った。 五郎右衛門はお鶴を眺めながら座っていた。 お鶴は洗い物をしながらも、時々、手を振って、意味もなく、『五右衛門さ〜ん』と声を掛けていた。 五郎右衛門は返事もせずに、しかめっ面をしたまま座り続けていた。 「終わったわ。ああ、冷たかった」とお鶴は帰って来た。 焚き火にあたりながら、「ねえ、それで、今日もずっと座ってるつもりなの」と聞いた。 五郎右衛門はうなづいた。 「つまんない。せっかく遊びに来たのに」 お鶴は子供のように駄々をこねた。 「わしがどうして、お前と遊ばなけりゃならんのじゃ。ガキじゃあるまいし」 「五右衛門ちゃん、遊ぼ」 「うるさい」 「あたし、泣いちゃうから」 「勝手に泣け」 「そうだ、睨めっこしましょ」 お鶴は五郎右衛門の前にしゃがみ込んで、色々な顔をしてみせて、五郎右衛門を笑わせようとした。五郎右衛門は無視しようと頑張ったが思わず笑ってしまった。 「やったあ、笑った、笑った」とお鶴は両手をたたいて大喜びした。 「まったく、お前は幸せじゃのう」と五郎右衛門はお鶴の無邪気さに呆れた。 「そうよ。今のあたし、一番幸せ」 お鶴は嬉しそうに五郎右衛門を見つめていた。 「わしらは仇同士じゃなかったのか」 五郎右衛門は体をひねった。背骨がポキポキと鳴った。 「そうよ。死んだ夫のお陰で、あたしたち会う事ができたのよ。もし、あなたが夫を斬ってくれなかったら、あたしたち、きっと会えなかったと思うわ。だから、あたし、毎日、夫の 「そんな事してたら、今にお前の亭主が化けて出るぞ」 「大丈夫よ。死んだら、みんな仏様になるのよ。仏様っていうのは広い大きな心を持ってるの。女の可愛い我がままなんて笑って許しちゃうわ」 「お前は、ほんとに幸せもんじゃよ」 「女っていうのはね、幸せにならなきゃ駄目なのよ。どんなに苦しい目に会っても、辛い目に会っても、悲しい目に会っても、あたしは幸せなんだ、幸せなんだ、幸せなんだ、幸せなんだって思うの‥‥‥そしたら、きっと、いい事があるわ‥‥‥」 お鶴はじっと焚き火の火を見つめていた。その目がだんだんと潤んで来ていた。 「お前もわりと苦労したみたいじゃな」と五郎右衛門は言った。 お鶴の陽気さの裏に隠された、悲しみを垣間見たような気がした。 「ううん、あたし、苦労は嫌いよ」とお鶴は笑ったが、目から涙が一滴、こぼれ落ちた。「馬鹿ね、あたし」 お鶴は立ち上がると後ろを向いて涙を拭いた。五郎右衛門にわざと笑って見せると、「さっきの和尚さんの話だけどね」と話題を変えた。 「あたしの場合とあなたの場合は違うかもしれないけど、あたしもあの和尚さんに座禅を教えてって言った事があるの。そしたら、和尚さん、教えてくれないのよ。女がそんなもの、する必要ない。女には女の仕事があるじゃろう。飯を炊いたり、掃除をしたり、洗濯をしたり、針仕事をしたり、これ、すべて禅じゃ。それらの仕事をすべて真剣にやってれば座禅と同じ境地になる。日常生活すべて、その気持ちで過ごせば、それでいいんじゃ。馬鹿どもは座禅をする事が禅だと思ってるが、座ってる時、いくら静かな境地にいたとしても、座禅をやめたら、すぐ、そんな境地はどっかに飛んで行ってしまう。そういうのを抜けがら座禅て言うんだって」 「抜けがら座禅か‥‥‥あの、くそ坊主め」 「ねえ、見て」とお鶴は突然、木の上を指さした。 「ほら、変わった鳥が飛んで来たわ。綺麗ね」 お鶴は真剣な顔をして、鮮やかな色をした小鳥を見つめていた。この辺りでは見かけない珍しい小鳥だったが、五郎右衛門には興味なかった。 「お鶴さん、酒はあるか」と五郎右衛門はお鶴の長い黒髪を見ながら言った。 「えっ、お酒飲むの」とお鶴はニコニコしながら振り向いた。 「今晩、一緒に飲もう」と五郎右衛門も笑った。 「ほんと? もう座るのやめたの?」 「ああ、抜けがら座禅はもう終わりじゃ」 五郎右衛門は立ち上がると体を伸ばした。 「やった!」とお鶴は両手を上げて飛び上がった。 「そうじゃなきゃ、あたしの五右衛門さんじゃないわ。お寺から、いっぱい持って来るわ」 お鶴は跳ねるように帰って行った。まだ、足が痛むのか、時折、立ち止まっては五郎右衛門を振り返っていた。 五郎右衛門はまた木剣を振り始めた。よくわからないが何か一つ、ふっ切れたような気がした。木剣が今まで以上にうまく使えるようになったような気がした。 新陰流の形はやらなかった。何となく、木剣を手にしただけでも嬉しくなり、ただ、上から下に振り下ろすだけの素振りを何回もやり、一汗かいた後、今までの心と体の汚れをすべて洗い落とすかのように、冷たい滝に打たれた。
|