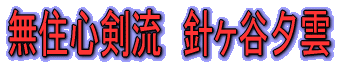
![]()
十三
お鶴は元気になった。 五郎右衛門はお鶴が寝ている間は木剣を手にする事なく、彼女の看病と座禅だけに熱中していた。 座禅の中で、ひたすら自分を殺していた。 「御免なさいね。あなたの修行を台なしにしちゃったわね。すみませんでした」 お鶴は両手をついて頭を下げた。顔色もすっかり、よくなっていた。 「他人行儀な事を言うな」と五郎右衛門は照れ臭そうに、ボソッと言った。 「そうか‥‥‥そうね。ありがとさん」 お鶴は笑って五郎右衛門の膝をたたいた。 「わしもお前のお陰で、少しわかりかけて来たんじゃ」 五郎右衛門は焚き火の上の鍋の中を覗いた。鍋の中ではお粥が煮えていた。 「そう、あたしのお陰?」 お鶴は首をかしげながら五郎右衛門の横顔を見つめた。 「ああ、ありがとう」と五郎右衛門はお粥を掻き混ぜながら言った。 「何だか、二人とも変ね」 「死にぞこなったからのう」と五郎右衛門はお鶴の方を向くと笑った。 お鶴も笑った。 「生まれ変わったのね、きっと」 「そうじゃな」 お鶴は手をたたくと、「今日は祝い酒よ」と言った。 「久し振りに思いきり飲みましょ。ね、やりましょ」 五郎右衛門は久し振りにはしゃいでいるお鶴を見て、うなづいた。 「その前に食った方がいい」 「うん」 お鶴はおなかが減ったと言いながら、お粥をお代わりして食べた。もう大丈夫のようだと五郎右衛門は安心した。 「あたし、お寺からお酒をいただいて来るわ」 そう言うとお鶴は嬉しそうに撥ねるように出掛けて行った。お鶴の後ろ姿を見送りながら、五郎右衛門は心の底から元気になってよかったと思っていた。 五郎右衛門は木剣を持つと外に出た。 外は眩しかった。すでに四月となり、山はあっと言う間に新緑の季節となっていた。陽気もかなり暖かくなっている。新鮮な空気を吸い込むと、久し振りに木剣を振ってみた。 今までとは違った。剣がすんなりと自然に振れる。心の中も静かに落ち着いていて澄み切っているようだ。 五郎右衛門は回りの景色を眺めた。 今まで目に付かなかった小さな花や草、そして、樹木の緑が鮮やかに目に入った。 『回りをよく見ろ』と言った和尚の言葉が思い出された。あの時は意味がわからなかったが、今、ようやく、その意味がわかったような気がした。今までは見ていたつもりだったのに、何も見ていなかった。ただ目を開けていただけで、何も目に入らなかった。 今は違う。まるで、世界が変わったかのようだった。 鳥のさえずり、虫の鳴き声、小川のせせらぎ、風の音、若葉の匂い‥‥‥ すべて、自然のものが自然のままに感じられた。自然の偉大さというものが素直に感じられた。 そして、剣‥‥‥ 構えあって構えなし‥‥‥ 自然に‥‥‥分別なく‥‥‥ 心の念ずるままに‥‥‥ ただ、振り下ろすのみ‥‥‥
久し振りに和尚がやって来た。 分厚い綿入れは着ていなかった。のんきそうに景色を眺めながら、とっくりをぶら下げて、やって来た。 お鶴に頼まれて酒を持って来たのか、と五郎右衛門は思った。 「どうじゃな。ほう‥‥‥何か、つかんだようじゃのう」 和尚は五郎右衛門を見ながら笑った。 「わかりますか」 「うむ。顔を見りゃわかる」 「和尚、お願いします。もう一度、立ち合って下さい」 和尚はうなづいた。 五郎右衛門は木剣を清眼に構えて、和尚に向かい合った。 和尚は相変わらず、杖を突いたまま五郎右衛門を見ている。 二人とも、そのまま動かず、時は流れた。 ひばりが鳴いていた。二人の間を蝶々が舞っていた。そよ風が若葉を揺らせた。 五郎右衛門は木剣を下ろし、「いかがですか」と聞いた。 「相打ちじゃな」と和尚は言った。 「はい」と五郎右衛門はうなづいた。 「どうやら、わかったようじゃな。 「和尚さんのお陰です」 五郎右衛門は素直に頭を下げた。 「なに、わしは剣の事など知らん。もし、最初の立ち合いの時、おぬしが打ち込んでいたら、わしは死んでいたじゃろう」 「しかし、どうしても打ち込めなかった‥‥‥」 「それは、おぬしが強すぎるからじゃ」 「強すぎるから?」 和尚はうなづいた。 「おぬしは鏡に向かって自分を相手に戦っていたようなもんじゃ。一度めの時、おぬしは相手を殺そうとしていた。相手を殺すという事は、自分は殺されたくはないという事じゃ。殺そうとする自分と殺されたくないという自分が、おぬしの中で戦っていて、どうする事もできなかったんじゃ。今度は、おぬしはまず、自分を殺した。そして、相手も殺す‥‥‥相打ちじゃ」 「はい、その通りです」 「まあ、理屈では何とでも言える。今日はな、おぬしと酒を飲もうと思ってやって来たんじゃ。まあ、やろうじゃないか」 和尚は立ち木の側に置いたとっくりを持ち上げた。 「はい。今、お鶴がお寺に行きませんでしたか」 「来た。随分と世話になったようじゃのう。今、犬と遊んでおるわ」 「犬と?」 「ああ、野良犬じゃ。二、三日前にフラッとやって来てのう。居心地がいいとみえて、あのお寺に居着いてしまったわ。お鶴はその犬と本気になって遊んどるよ」 五郎右衛門は犬と遊んでいるお鶴を想像して笑った。 「あれは面白い 五郎右衛門も、確かにその通りだと思った。コロコロと気分を変えるが、こだわりというものはまったく感じられなかった。 和尚は鼻唄を歌いながら岩屋の方に向かった。見るからにのんきな和尚だった。
「本物の剣術は一生のうちに一度だけ使うものです」と五郎右衛門は和尚に言った。 二人は岩屋の入口の側で、焚き火を囲んで酒を飲んでいた。 「その使い道も三通りしかありません。一つは戦場での太刀打ち。二つめは泰平の時、主君の命によって罪人を斬る時。三つめはどうしても避けられない喧嘩の時です。この他に剣術を使う時はありません。そして、三つとも、その場での相打ちの死は、武士として恥ずべき事ではありません。戦場においては、一人でも多くの敵を滅ぼす事が主君に対しての忠ですから、臆病になって命を惜しんだり、敵に討たれて、その敵に逃げられたり、流れ矢に当たって敵を斬る事なく死ねば、それは恥となります。しかし、敵と相打ちになって死ぬ事は恥ではありません。主君の命によって罪人を討つ時も、もし、自分が罪人に斬られ、その場で死に、罪人を取り逃がす事になれば恥となりますが、自分の命を捨てて罪人を討ち捨てるならば恥にはなりません。喧嘩でも相打ちは見よき、聞きよきものです。敵を殺して勝ったとしても、敵の兄弟、子供らが憎しみを持って仇を討ちに来ます。相打ちで両方が死んでしまえば仇討ちなどなくなります」 五郎右衛門は話し終わると和尚の言葉を待った。 「うむ」と和尚はうなづき、酒を飲んだ。そして、五郎右衛門を静かな目で見ると言った。 「おぬしが剣を抜いた時、それは、おぬしの死というわけじゃな」 「そうです」と五郎右衛門は力強く答え、とっくりをつかんだ。 「それもいいじゃろう」 五郎右衛門は和尚が差し出したお椀に酒を注いだ。 「じゃがな、ちょっと、おぬしに面白い話をしてやろう」と和尚は言って、酒を一口飲むと目を細めた。 「何年か前、わしが京都のお寺にいた頃の事じゃ。わしがいたお寺に大ネズミが住み着いたんじゃ。その大ネズミは昼間っから人前に出て来て暴れ回った。仏像は倒す、お経は食い散らかす、お供え物はみんな食ってしまう。坊主たちが座禅していれば調子に乗って頭の上に乗って来る始末じゃ。坊主が総出で捕まえようとしても、とても手に負えん。仕方なく、近所から猫を何匹か借りて来て離してみたんじゃが、どの猫も、その大ネズミには歯が立たんのじゃ。困り果てていると 『わたしは代々、ネズミを捕る家に生まれ、幼少の頃から、その道を修行し、早業、軽業、すべてを身に付け、 老いぼれ猫はそれを聞いて、黒猫に対して、こう答えたんじゃ。 『お前が修行したというのは手先の技だけである。だから、隙に乗じて技を掛けてやろうとして、いつも狙っている心がある。古人が技を教えるのは 次には、いかにもたくましくて強そうな虎毛の大猫が出て来て言った。 『わしが思うには武術というものは要するに気力です。わしはその気力を練る事を心掛けて参りました。今では気が 老いぼれ猫はそれに対して、こう答えた。 『お前が修練したのは、気の勢いによっての働きで、自分に頼む所がある。だから、相手の気合が弱い時はいいが、こちらよりも気勢の強い相手では手に負えんのじゃ。あのネズミのように生死を度外視して、捨て身になって掛かって来る者には、お前の気勢だけでは、とても歯が立たん』 次には、少し年を取った灰色の猫が出て来て言った。 『まったく、その通りだと思います。わしもその事に気づいて、兼ねてから心を練る事に骨折って参りました。いたずらに気色ばらず、物と争わず、常に心の和を保ち、いわば、 老いぼれ猫は答えた。 『お前の言う和は自然の和ではない。 五郎右衛門はじっと考えていた。 「どうじゃな。今のおぬしは老いぼれ猫じゃな。どうする。まだ、上があるぞ」 和尚はうまそうに酒を飲むと、静かな目で五郎右衛門を見つめた。 「どういう事じゃ。剣を構えただけで敵が逃げ去るというのか」 「いや。剣など構えとらんぞ。ただ、居眠りしているだけじゃ」 「そんな事、信じられん」 「信じようと信じまいと、それはおぬしの勝手じゃ。黒猫の業。虎猫の気、いわゆる体の事じゃ。そして、灰色猫の心。今のおぬしは、この『心』『体』『業』を兼ね備えて一つになった。しかし、まだまだじゃ。おぬしの言う『相打ち』、自分を殺し、相手を殺すというのは、まだ、 「活人剣? それはどんなものです」 「字の通り、人を活かす剣じゃ。最後に出て来た眠り猫の境地じゃ。言葉で言えるようなものではない。後は自分で考えるんじゃな」 「活人剣‥‥‥」 「さてと、わしは帰るかのう」 和尚は立ち上がった。 帰りがけに、和尚は五郎右衛門の背中に鋭い声を掛けて来た。 「五郎右衛門!」 「はい」と五郎右衛門は振り返った。 「それじゃよ。それが極意じゃ」と和尚は笑いながら、フラフラと帰って行った。 五郎右衛門は和尚が置いて行った、とっくりをじっと見つめていた。
|