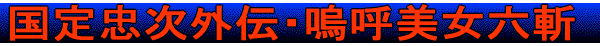

5.貞利の艶本
久次郎はお政と一緒に 久次郎の顔を見ると貞利は筆を止めて、浮かない顔をして縁側まで出て来た。 「やあ、お政さんも一緒か」と貞利はお政を見て笑い、久次郎を見て、「お常ちゃんの事、何か見当は付きましたか」と聞いた。 貞利も久次郎の動きを気にしていたようだ。久次郎は首を振った。 「境の男たちは白です。中瀬で、お常と密かに会ったような奴は見当たりません」 「そうか。中瀬の方も例のしんさんてえのは見つからなかった。昨日も一日中、中瀬一帯を 「えっ、何か見つかったんですか」 久次郎とお政は顔を見合わせてから、貞利の言葉を待った。 「まあ、とにかく、上がってください。お茶でも入れますから」 貞利は二人を仕事場の隣の部屋に案内した。客間らしく、床の間に肉筆の美人絵が飾ってあった。 「こんなとこに先生んちがあったなんて知らなかったわ」とお政が小声で言った。「利根川の側の眺めのいいとこだと思ってた」 久次郎はうなづいた。「俺もそう思って、最初来た時、 「そうなんだ。ここなら絶対、安全だわね。でも、先生、 「何でも、時間が中途半端だから女中なんか置くとわずらわしいんだそうだよ。絵に熱中すると飯を食うのも寝るのも忘れちまうらしい。朝方になって寝付いて、夕方になって目覚めるってえ事もあるんで、一人の方が気が楽なんだそうだ。ただ、近所の婆さんが毎朝、飯だけは炊きに来てくれるらしい」 「ふーん。絵画きさんも大変なのね」 「何でも、ひらめいた時に描いとかねえといい絵ってえのは描けねえんだそうだ」 「へえ‥‥‥」 貞利がお茶と 「一体、何が見つかったんです」久次郎とお政は身を乗り出した。 「まさか、あんな所から出て来ようとは‥‥‥」貞利は首を振ってから、「お常の着物が見つかったんだよ。あの日、着てた着物が出て来たんだ」と低い声で言った。 「えっ、着物が‥‥‥」お政の顔が真っ青になった。口を震わせながら貞利の顔を見つめている。久次郎も貞利の顔を見つめた。 「昨日の夕方、お常が川岸の土手を歩いてるのを見たという者が現れた。その土手を俺たちも歩いてみたんだ。まっすぐ行きゃア 「河原の掘っ建て小屋ですか‥‥‥」久次郎は 「どうして、お常ちゃん、そんなとこに行ったの」とお政が言った。「どうして、そんなとこに着物があるの」 「着物ってえのは上着だけですか」久次郎は貞利に聞いた。 貞利は首を振りながら、「全部だよ」と言った。「上に着ていた 「えっ、お常ちゃん、そこで裸にされちゃったの」 「そのようだな。新八がすぐに島村の親分に知らせに行って、今頃、大勢の子分たちが河原中を捜し回ってるはずだ」 「くそっ、着物が出て来やがったか。その掘っ建て小屋ってえのは人目のつかねえとこにあるんですか」 「ああ、土手からは見えねえ。河原に降りねえとわからねえ。河岸からは離れてるし、渡し場からも離れてる。お常は何者かに、その小屋に連れ込まれて裸にされたに違えねえ」 「河原にいた誰かが土手を歩いてるお常を見つけて、捕めえて小屋に引っ張り込んで、着物を脱がせて‥‥‥」 「やめて!」とお政が叫んだ。 「もう、俺の出る幕じゃアねえんで、島村の親分に任せて帰って来たんだ。仕事をしてたが、やっぱり気になってな、さっぱり手につかねえ」 「こうなって来ると、お常が誰に会いに行ったんかはわからねえが、そいつがお常をどうこうしたんじゃなさそうだな。何者かが、土手を歩いてたお常をさらって、その小屋に連れてったと考えるんが 「多分な」と貞利はうなづいた。 「そうなると、相手はお常じゃなくてもよかったってえ事にはなりませんか。たまたま、土手を一人で歩いてたいい女がいたんで、取っ捕めえたってえ事になりませんかね」 「かもしれねえな」 「そうなって来るとお常をさらった奴を捜すんは益々、難しくなる」 「最悪の事態にならなけりゃいいが‥‥‥」貞利は苦しそうな顔をしてお茶をすすった。 久次郎もお茶をいただいた。お政は放心状態のまま、うつむいていた。 「その小屋ん中に血の跡とかはありませんでしたか」と久次郎は聞いた。 「そんな物はなかった。回りも一応、調べて見たが怪しい物は何もなかった」 「新八はやはり、白でしたか」 「一応、聞いてはみたがな。新八はお常がいなくなった日、確かに中瀬に来ていた。丁度、その日は河岸問屋『 「朝から晩まで、ずっとですか」 「いや、昼頃から晩まで賭場にいて、夜は 武蔵屋の 「先生、いる?」と女の声がした。 久次郎が振り向くと馬を引いた娘が笑っていた。 「やあ、お万か」と貞利は娘に声を掛け、「仕事をさぼって、また、遊んでんのか」と笑った。 「違うよ、もう一稼ぎしたんだよ。いいお客がいてね、 「まだ、日は高えぞ」 「いいのよ。ねえ、あたしの絵はできたの」 「もう少しだ」 貞利は久次郎とお政にお万を紹介した。 お万は貞利が今描いている美人絵『利根川八景』の中の一人だった。毎日、馬を引いているので色は黒いが可愛い顔をしていて、体つきも無駄な お万が来た事によって、お常の話は打ち切りとなり、話題は貞利の美人絵の事になって行った。 江戸から帰って来た貞利は去年の正月、『当世木崎美人』と題して、木崎宿の飯盛女たちを描いて売り出した。今年の正月は『美人例幣使道』と題して、各宿場の素人娘たちを描いた。そして、来年の正月に売り出す予定なのが今描いている『利根川八景』だった。それに、もう一つ、玉村の飯盛女たちも描かなければならないという。 『当世木崎美人』の評判を聞いて、玉村一番の 当時の出版物は正月に刊行されるのが普通だった。八月頃までに 貞利の仕事は美人絵だけではない。わ印(笑い本)と呼ばれる 去年、売り出した『 今年、売り出した『 上巻は四年前の境宿の居酒屋の お仙というのは百々一家の代貸だった新五郎の妻で、お仙がひどい目に会ったのは百々一家を潰すために伊三郎が仕組んだ 中巻は去年の春、太田宿の 輪姦、強姦、殺人、心中と男女の 九年前の文政八年(一八二五年)の夏、歌舞伎作者、 久次郎も当然、貞利の艶本は見ている。お政やお万がいるため、艶本の事は話題に上らなかったが、貞利が来年の正月にどんな艶本を出すつもりなのか気になっていた。 お政とお万がお昼の用意をすると言って、お勝手に行った隙に、こっそりと聞いてみた。 「まだ、はっきりとは決まってねえんだ。実を言うと去年描いたのは島村の親分の好みだったんだよ」と貞利は照れ臭そうに笑った。 「島村の親分の好み?」 「ああ。これは内緒なんだが、親分は残酷な事が好きでな、俺の師匠である国貞や師匠の師匠である 「そうだったんですか」 「ああいうのをまた描けと言われてもなア、あの話は一応、実際にあった事で、みんなも噂に聞いてた話だ。それをああいう風に絵にしたから受けたんであって、作り話じゃア、ああまで売れなかっただろう」 「確かに、お仙さんの話なんか、うちの者たちは腹を立てたけど、町の旦那衆は興味深そうに見てたからな」 「お仙さんが百々一家と関係あったなんて知らなかった。すまねえ事をしてしまった」 「いえ。その事はもういいんだけど、そうなると来年の作品も今年のような残酷なのになるんですか」 「そうしなければ版元も買ってくれる人たちも納得しねえだろう。去年の秋頃から、実際に起こった様々な事件を調べちゃアいるんだが、なかなか、いい題材が見つからねえんだ。島村の親分は 「拷問ですか」 「ああ、 「へえ。女牢の様子なんて面白そうじゃねえですか。俺なんか興味ありますけどね」 「しかし、架空の話じゃどうもな。実際にこの辺りの娘が江戸送りにされたってえ事実がありゃア興味を引くだろうが、牢屋ん中の女たちを描いたからって難しいだろう。一応、その線で描き始めちゃアいるが、どうも、去年のようにスラスラと筆が運ばねえ」 「そうですか。楽しみにしてますよ」 久次郎とお政は昼飯を御馳走になると貞利の家を後にした。 「これから、どうするんですか」と歩きながらお政が聞いた。 「どうしようか」と久次郎は言ったが、何かを考えているようだった。 「お常ちゃん、無事なのかしら」 「そう願いてえが、裸でウロウロしてるたア考えられねえからな」 「何で、お常ちゃん、中瀬になんか行ったんだろう。中瀬なんかに行かなければ、こんな事にはならなかったのに‥‥‥」 「中瀬のしんさんか‥‥‥そいつがお常を中瀬に呼び出したに違えねえ。そいつはお常がいなくなったんを知っていながら、すっとぼけていやがる。許せねえな」 「許せないわね。でも、その人、お常ちゃんと会ってないかもしれないわよ。待ち合わせの場所に行ったら、もう、お常ちゃんはいなかった。来なかったのかと諦めたのかもしれないわ」 「そうか、その線も考えられるな。しまった。お常が土手の上を歩いてたんがいつ頃だったのか聞くのを忘れたな」 「その時刻によって、しんさんと会う前か後かがわかるのね」 「そうだ。 「もう一度、行ってみる?」とお政は立ち止まった。 久次郎も足を止めて、貞利の家を振り返ったが、「いや、大丈夫だ」とお政を促して歩きだした。「うちの 「へえ、そんな事もしてたの」 「一応、新八と信三と万吉の三人を調べさせてるんだ。三人の動きを見張りゃア何かが出て来るかもしれねえからな」 「三人とも島村の親分さんの身内でしょ。お常ちゃんと関係あれば、親分さんが放ってはおかないでしょ」 「そうとも限らねえ。伊三郎の奴は自分の都合の 「親分さんがそんな事をするかしら」 「評判のいい親分に限って、裏で何をしてるかわからねえもんだ」 「そうなの‥‥‥」 境宿に着いた頃、雨がポツポツ降り出して来た。大黒屋の前を通るとおとしに呼ばれて、二人は店に入った。中途半端な時刻なので客はいない。おとしに誘われるまま座敷に上がって、お茶を飲みながらお常の事を話した。 着物が見つかった事を話すと、おとしはすでに知っていた。二人が平塚に行っている時、伊三郎の子分がお常の家にやって来て、その事を知らせて行ったという。父親と兄貴が慌てて中瀬に向かい、お常の家の様子を見ていたお菊が、お常の妹、おさよから話を聞いたので、あっという間に噂になったらしい。 「あたし、ずっと考えてたんだけど」とおとしが小声で言った。「中瀬のしんさんて、いつも、市に来る魚屋さんじゃないかしら」 「そういえば、いたわね」とお政も小声で言った。「すっかり忘れてたわ。でも、その魚屋さん、しんさんていう名前だっけ」 「時々、うちにも売りに来るのよ。それで、前にあたし、名前を聞いた事あるの。確か、伸吉って言ったわ」 「そいつは中瀬から来るのか」久次郎は目を光らせて二人に聞いた。 「そう。中瀬に住んでるみたい」 「そいつは七日の市にも来たのか」 「どうだったろう。あの日は 「あたしも知らないわ。お美奈ちゃんに聞けばわかるかもね」 さっそく、三人は上町にある 銭屋は 「あら、お政ちゃんにおとしちゃん、ねえ、聞いた。お常ちゃんの着物が見つかったんですって」お美奈は眠りから覚めたかのように目を見開いて、興味深そうにしゃべった。 「そうなのよ。その事でね、ちょっと、聞きたい事があるのよ」とお政が言った。 「なあに、何か他にもわかったの」 「そうじゃないのよ。この前の市の時なんだけどね、ほら、あの魚屋さん、見た?」 「魚屋さんて何の話よ」 「ほら、この前、お常ちゃんにどっさりとお魚を持って来た、あの人よ」 「ああ、あの人、確か、来てたわよ。隅の方でお魚を売ってたんじゃない」 「それで、いつ頃、帰ってったの」とおとしが聞いた。 「さあ、ずっと見てたわけじゃないけど、早めに引き上げてったみたいよ。お魚がみんな売れちゃったんじゃない」 「早めって、お昼より前?」 「ええ。お昼頃にはもういなかったわ」 「お常ちゃんが出掛けたのが丁度、お昼頃でしょ。先に帰って待ってたのかしら」 「えっ、ねえ、お常ちゃん、あの魚屋さんと一緒にいるの」 「かもしれないって事よ」 「その魚屋のうちはどこだか知ってるか」と久次郎は聞いて、三人の娘の顔を見比べた。 皆、首を振った。 「でも、明日、来るんじゃない」とおとしが言った。「明日は中市だから、おちまちゃんちで見てれば、すぐに見つけられるわよ」 「でも、本当にあの魚屋さんが中瀬のしんさんなのかしら」お政が首をかしげた。 「あたしたちにはわかんないわよ。やっぱり、お海ちゃんかお菊ちゃんに聞いた方がいいわ」 久次郎はお政と一緒にお菊に会いに行った。おとしはお美奈に話があると言って残った。 村田屋の前を通ると、おたかが意味ありげに笑いながら手を振った。お政も傘を差しながら手を振り返した。井筒屋の前を通ると、おゆみが雨を眺めていた。久次郎に気づくとニコッと笑って手を上げた。お政が早く行きましょうと久次郎の手を引っ張った。 お菊も店先に立って、暇そうに雨を眺めていた。娘たちは皆、お常の事を心配しながらも、何か面白い事でも起きないかと期待しながら宿場の様子を見守っているようだ。 お菊に魚屋の伸吉の話をすると、「そうか、あの人もしんさんだったわね。すっかり忘れてたわ。そうよ、あの人もおかみさんがいるわ。もしかしたら、お常ちゃんと内緒で付き合ってるのかも」と新しい情報をつかんで喜んだ。さっそく、尾張屋のお海に知らせてやろうという顔付きだった。 「でも、どうして、お常ちゃんの着物が河原なんかにあったの」 「わからねえ」 「お常ちゃん、大丈夫なのかしら‥‥‥」お菊とお政は心配顔して顔を見合わせた。 「その魚屋だが、お常がそいつと二人だけでいるとこを見た事あるのか」 「あるって言えばあるけど、ただの世間話をしてただけよ。二人の間に何かがあったようには見えなかったけど、でも、わかんないわね。音吉つぁんとの事があってから、お常ちゃん、やけに慎重になっちゃったから、親の目の光ってる所では、そんな素振りを見せないようにしてたのかもしれないわ」 「明日、そいつが来たら、よく聞いてみるか」 雨降る中、久次郎はお政を家まで送り、百々村に帰った。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧