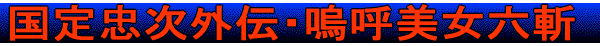

2.橘屋のお関
お関が帰っている事を願って、久次郎とお紺は翌朝、商人宿『 お関はまだ帰っていなかった。両親は心配で一睡もできなかったという。話を聞いてみたが、番頭の梅吉から聞いた以上の事は何も知らなかった。心当たりもないという。両親から、絶対にお関を捜してくれと頼まれた久次郎とお紺は引き受けて、謎の女を見たという 四十年配のおなんも眠れなかったとみえて、腫れぼったい目をして、お関を呼び出した女の事を詳しく話してくれた。 お昼頃、入り口で声がしたので、早いうちからお客が来たなとおなんは応対に出た。客は若い女で顔を隠すように頭巾をかぶり、小さな声で「お関さんはいますか」と言って、おなんが「いますが」と答えると、「すみませんが呼んでください」と言った。 「どちら様ですか」と聞くと、「お関さんに是非とも伝えたい事がありますのでお願いします」と言って頭を下げた。 おなんは一体誰だろうと思いながらも、お関を呼びに行った。 お関は女を見たが、誰だかわからないような顔をした。女はお関を呼ぶと耳元で何事か 「ちょっと待っててください」とお関は言って女を待たせ、部屋に戻って髪を整え、薄化粧をして出て来た。 「どこに行くの」とおなんが聞くと、「ちょっと」と言って女と一緒に出掛けて行った。その素振りから、すぐに帰って来るだろうと一々、 その日は客も少なく、大して忙しくなかったが、お関の事は忘れてしまった。夕方になって、女将さんから、お関はどこに行ったと聞かれ、あれからまだ帰って来ない事を知って、女将さんに女の事を話した。心配になって捜しに行こうとしたら、大騒ぎになるからやめろと言われた。ずっと帰りを待っていたが、お関は帰って来なかった。 「あたしがもっと気を付けてればよかったんです」とおなんは目を潤ませていた。 お勝の方はお関が女と出て行く所をチラッと見ただけで何も知らなかった。 その時のお関の格好を聞くと黒襟に岩井茶の 「最近の泊まり客で、そんな女はいなかったの」とお紺が聞いた。 「いえ、見た事もない人です」おなんが言うとお勝もうなづいた。 「今、 「その女もお師匠さんみてえだったのか」 「はい。年の頃は二十の半ば位で、普通のおかみさんには見えませんでした。何かのお師匠さんか、お茶屋の女か、江戸から来た芸者さんのような感じでした」 「ほう、江戸の芸者か‥‥‥」 「はい。この辺りではあまり見かけないような女でした」 「そんな女が何の用でお関さんを連れ去ったんだんべえ」久次郎は首をかしげながら、お紺を見た。 「そういえば、姉さんのような雰囲気の女でした」とおなんはお紺を見ながら言った。 「まあ、そうだんべ。お紺も深川の芸者衆を手本にしてるからな」 「あのう」とお勝が何かを思い出したように口を挟んだ。「あたしは後ろ姿しか見てなかったんで、よくわからないんですけど、あの着物、どこかで見た事があるような気がしてたんです。誰だったろうって考えてたんですけど、今、ようやく思い出しました」 「なに、あの女が誰なのかわかったのか」 「いえ、顔を見なかったんで、はっきりとはわかりませんけど、あんな着物を着てた人は思い出しました」 「一体、誰なんでえ」 「お北さんですよ。もう四、五年も前ですけど、大黒屋さんで壷を振ってたお北さんです」 「なに、お北だと?」久次郎は驚いて、お勝の顔を見つめた。「おい、そいつは本当なのか」 「はい」とお勝はうなづいた。「あの頃、あたし、大黒屋さんで働いてたんで、よく知ってるんです。お北さん、よくあんな格好してました。島村の親分さんが亡くなってからは全然、見かけませんけど、後ろ姿はお北さんのような気がします」 「おめえは顔を見たんだんべえ。お北に間違えねえのか」と久次郎はおなんに詰め寄ったが、「そう言われても、あたしはそのお北さんてえのをよく知りませんので」と困ったような顔をした。 「くそっ、もし、その女がお北だとしたら、とんでもねえ事んなる」 「とんでもない事って?」とお紺が聞いたが、久次郎は聞いてはいなかった。 「こいつアのんびりしてられねえぞ。早えとこ見つけねえととんだ事んなる」 久次郎は二人に礼を言うと橘屋を後にした。 「おい、松、おめえはお関とお北がどっちに行ったか聞いて回れ。二人の格好はわかってるな」 「へい。兄貴は?」 「俺アお北んちに行ってみる。今、そのうちにゃア弟の孝吉が住んでるはずだ。おめえは一旦、うちに帰って、暇な奴らを使って二人がいつ頃、どこに行ったんかを調べ上げろ」 「へい、わかりやした」 桶松が百々村に帰ると久次郎はお紺の手を引っ張るようにして、さっさと江戸道の方へと向かった。 「ねえ、どこ行くの。お北って誰なの」 「あっ、そうか、おめえはお北を知らなかったんだっけ」 「知らないわよ。大黒屋で壷を振ってたって言ってたけど、女壷振りなの」 「そうか、おめえが百々村に来たんは伊三郎が殺されてからだったな。お北ってえのは伊三郎の妾でな、四年前に一年くれえ大黒屋で壷を振ってたんだ。伊三郎が殺された後、島村一家で跡目争いが起こって、お北は平塚の先生んとこに逃げ込んだ。そん時、伊三郎の 「どうして、今頃、伊三郎の仇を討つの。もう二年近くも前の事じゃない」 「そんな事ア知るか」 「それに、お関をさらうのと伊三郎の仇討ちと、どう関係あるのよ」 「お北はな、お関がうちの角次と仲がいいのを知って、さらってったに違えねえ。姐さんをさらう事ができなかったんで、身代わりにお関をさらったんだんべ。早く、見つけねえとお関は本当に殺されちまうぜ」 二人は横町を平塚方面に向かっていた。 「それで、そのお北って人のうちに行くの」 「とりあえずは先生んちだ。先生に聞きゃア、お北の居場所がわかるかもしれねえ」 浮世絵師、貞利は留守だった。留守を守っている三人の弟子が、二人の娘を手本にして絵を描いていた。 相変わらず、この家は娘たちの出入りが激しいようだ、と久次郎とお紺は顔を見合わせた。弟子たちに聞くと、貞利は玉村宿に出掛けて行ったという。 「玉村? 先生はまた、玉村の女郎を描きに行ったんか」 「いえ、そうじゃなくって、玉村の親分さんとこに行ったんです」と弟子の中で一番年長の平作が答えた。 「例の事件の事でか」 「はい。親分さんとこの子分が呼びに来て、力を貸してほしいって」 「成程な。玉村の親分さんが先生の知恵を借りに来たってえわけか」 「そうみたいです」 「先生も忙しいこったな。今、先生はどんな絵を描いてんだ」 「木崎のお女郎さんです」 「木崎の親分の仕事か」 「はい」 「玉村に行ったんじゃア 「いえ、今日中に帰って来るって言ってましたけど」 娘たちがお茶を入れて持って来た。 「すまねえな。おめえさんたちも先生の美人絵に描かれたのか」と久次郎が聞くと、娘たちは照れながら、「やだア」と手を振った。二人とも美人絵になる程の器量よしではないが、愛嬌のある顔をしていた。 「俺の幼なじみなんです」と二番弟子の政吉が言った。「時々、遊びに来て、絵の手本になってくれるんです。先生は俺の真似ばかりしてないで、実際の女を手本にして描けって、いつも言ってますんで」 「成程な。ここんちには何人も娘たちが遊びに来るだんべえから、手本には事欠かねえってわけだ」 「はい。お陰様で」 「いい絵は描けそうかい」 「難しいです」 「そうだんべ。簡単にゃア先生のようにはなれねえ。まあ、頑張れ。先生がいねえんじゃしょうがねえな。そうだ。おめえら、孝吉んちを知らねえか」 「知ってますけど」と答えたのはやはり、地元の政吉だった。 「おう、おめえ、知ってるか。すまねえがちょっと案内してくんねえか」 「でも‥‥‥」 「人の命にかかわる事だ。後で先生にちゃんと言ってやるから頼むぜ」 行ってこいと平作が言ったので、政吉はうなづいて案内に立った。 お北の弟、孝吉は伊三郎の子分だった。伊三郎死後の跡目争いの時、兄貴分の尾島の貞次と共に世良田の弥七を殺して国越えした。一年余りの旅を続けて、帰って来たのは去年の八月。帰って来ると島村一家を継いでいるはずの小島の彦六はいなかった。平塚を追い出され、中瀬の藤十のもとに逃げた彦六は自分の子分に殺されてしまった。伊三郎の威を笠に着て、威張り散らしていた者の哀れな末路だった。 兄貴分の貞次は前島の秀次の子分になったが、孝吉は従わず、姉のお北が伊三郎からもらった平塚の家に住んで、時々、百々一家の賭場に顔を出しては小銭を稼ぎ、毎日、ブラブラしている。兄貴分だった新八がやっている絵草紙屋に顔を出したり、姉が出入りしていた貞利の家に遊びに行ったり、伊三郎の子分だった事も忘れて、百々一家の子分たちと一緒に飲み歩いたりしていた。渡世人の世界では親分子分の関係を持たない博奕打ちの事を 孝吉の住む家は伊三郎が 「ほう、さすがだな。桃中の旦那が見たら大喜びするだんべえ」 こじまんりとした家だったが風流な造りで、噂に聞く、向島の寮(別荘)という感じだった。 「何か、うめえ物でも買ってって、みんなで食いな」久次郎は政吉に うまい具合に孝吉はいた。のんきに寝ていたらしく、寝ぼけた顔をして二階から下りて来た。昨夜、誰かと酒を飲んだのか、茶の間にとっくりやお 「何でえ、久次の兄貴ですかい。よく、ここがわかりやしたね」孝吉は目をこすりながら、久次郎とお紺を見た。 「起こして、すまなかったな」と久次郎は上がり 「何か、あっしに用ですかい」首の後ろを掻きながら孝吉は座り込んだ。 「ああ、ちょっと聞きてえ事があってな」 「わざわざ、兄貴がこんなとこまで来るってえのは余程の事で」 「まあ、そういう事だ。おめえ、最近、姉御に会ったか」 「えっ、姉御?」孝吉は目を見開いて、久次郎を見つめた。 「会ったんだな」と久次郎は問い詰めた。 「まさか」と孝吉は首を振った。「旅から帰って来てから、あっちこっち捜してるが、どこにもいねえ。 「ここに帰って来たんじゃねえのか」 「帰って来るわけねえ。兄貴、姉ちゃんに会ったんかい」 「俺は会っちゃアいねえが、見た者はいる」 「どこで見たんです」孝吉は身を乗り出して聞いて来た。 「境だ。昨日の昼過ぎから橘屋のお関が消えちまった。お関を連れ出したのが、どうも、おめえの姉ちゃんらしいぜ」 「姉ちゃんがお関を? どうして、お関を連れ出したんだ」 「そいつを聞きにやって来たんだ」 訳がわからないという顔をして孝吉は首の後ろをたたき、久次郎を見て、お紺を見た。 「姉ちゃんがお関を連れ出すなんて信じられねえ。人違えじゃねえのかい」 「まだ、はっきりとおめえの姉ちゃんと決まったわけじゃアねえんだが‥‥‥おめえの姉ちゃんは実家に帰ったって聞いてたが、実家にはいねえのか」 「いねえ。旅から帰って来て、俺も実家には顔を出したが、島村の親分が死んでからア一度も帰ってねえらしい。まったく、どこに行っちまったんか、このうちだって、ずっと、空き家になってたんだ」 「おかしいな。平塚の先生は実家に帰ったって言ってたぜ」 「その事ア俺も聞いた。島村一家が跡目争いをおっ始めた時、姉ちゃんは先生んちに逃げたんだ。先生んちに一ケ月くれえ世話んなって、その後、実家に帰るって言って、どっかに行っちまったらしい。結局、実家にも帰らず、先生んとこにも現れねえ。先生は島村の親分の仇を討つために百々村の親分を捜しに行ったんじゃねえかと言ったが、親分が帰って来ても姉ちゃんは帰って来ねえ。姉ちゃんは壷振りの腕を持ってるから、どっかの親分さんに見込まれて、どっかに落ち着いたんかもしれねえって俺は思ってたんでさア」 「てえ事は、旅から帰って来て、ここにも姿を現さねえで、どっかに隠れてるってえ事か」 「もし、姉ちゃんが本当に帰って来たんなら、そうなるだんべえな。しかし、どうして、姉ちゃんはお関を連れ出したんだ」 「俺が思うにゃア、お北はまだ、仇討ちを諦めちゃアいねえって事だな。お関はうちの角次といい仲だ。お関を手初めとして、百々一家に関係のある女を一人づつ殺そうと考えてんかもしれねえ」 「まさか、そんな事を‥‥‥」 「うちの親分を追って長旅を続けてるうちに復讐の鬼になっちまったんかもしれねえ」 「お関ちゃんがいなくなったって本当なんですか」と二階から顔を出したのは煙草屋『越後屋』の娘、お奈々だった。 「何でえ、おめえ、ここに泊まったんか」久次郎は驚いて、お紺と顔を見合わせた。 お奈々は境宿の七小町の一人で、色白の美人だった。 「隠れてようと思ったんだけど、お関ちゃんの事が心配になって」 お奈々は恥ずかしそうに孝吉の隣に座ると、「うちには内緒にしてください」と言って両手を会わせた。「お 「わかった。見なかった事にしておくよ」 お奈々はホッとして頭を下げた。 「すみません。それで、お関ちゃん、孝吉さんのお姉さんと一緒にいなくなっちゃったんですか」 「そうらしいな。おめえはいつから、ここにいるんだ」 「昨日の夕方です」とお奈々は顔を赤らめた。 「ここに来る途中、お関が姉ちゃんと一緒のとこを見なかったか」 お奈々は孝吉を見ながら首を振った。 久次郎はお奈々から孝吉に目を移すと、「おめえの実家なんだが両親は健在なのか」と聞いた。 「いや。二親とももういねえ。兄貴夫婦が細々と百姓をやってる。あんなとこに姉ちゃんが帰るたア思えねえ」 「貧しいのか」 「貧しいさ。姉ちゃんが島村の親分のお妾になったお陰で、何とか人並みな暮らしができるようになったんだ。それなのに、兄貴は姉ちゃんを白え目で見やがる。俺もあんなうちを飛び出して、姉ちゃんに頼んで親分の子分になったんだ。親分が亡くなる前に二親とも死んじまったから、もう、あんなうちは関係ねえや」 「お北が実家に帰る事はねえと言うんだな」 「ああ、ねえだんべ。あんなうちに帰るくれえなら、こっちに帰って来るはずだ。ここには姉ちゃんの着物も結構残ってんだ。旅から帰って来たら、着替えるためにもここに帰るはずだ」 「そうか‥‥‥」と久次郎は腕組みをした。どうも、当てが外れたような感じだった。お紺を見ると小さく首を振った。 「姉ちゃんは旅支度だったんですかい」と孝吉が聞いて来た。 「いや、そんな風じゃなかったらしい」 「姉ちゃんじゃアねえんじゃねえですか。旅から帰って来てすぐに、お関と角次の関係なんかわかるはずがねえ」 「そう言われりゃアそうだが、復讐が目的で帰って来たとすりゃア、どこかに隠れながら様子を探ってたのかもしれねえ」 「帰って来たんなら、ここに来ると思うがなア。それに、先生んとこにも顔を出すはずだ。先生は何て言ってた」 「 「らしいな」と孝吉はうなづき、お奈々をちらっと見てから話を続けた。「島村の親分は妾を何人も持ってたんだ。親分が若え妾に夢中になった腹いせに先生とできちまったらしい。でも、親分にばれちまってな、辛え目に会わされたようだ」 「伊三郎に懲らしめられたんか」 「懲らしめられたにゃア違えねえが、普通のやり方じゃなかった。姉ちゃんに恥ずかしい格好させて、それを先生に描かせたんだ。親分は若え妾とニヤニヤしながら、それを見てたらしい」 「伊三郎がそんな事をしたのか」 「裸にされて縄で縛られたりもしたらしい。兄貴も先生の『美女六斬』は見たんべえ。あん中の残酷な絵は実際に姉ちゃんを責めて、それを手本したらしいぜ」 「そうだったのか‥‥‥」 「あの本に出てる以外にも、先生は姉ちゃんを手本に何枚も残酷な絵を描いたらしい。親分はそれを見ながら不気味に笑ってたそうだ」 「伊三郎ってえのは、そんな変態野郎だったのか」 久次郎は驚いたが、それ以上にお奈々は驚いていた。ポカンとした顔して孝吉の話を聞いていた。 「俺も姉ちゃんから聞いた時、信じられなかったが、 久次郎は貞利の家の蔵の中を見せてもらった事があった。まだ、お政と付き合っていた頃で、お政が蔵の事を聞いたら、あの蔵は伊三郎が若い娘と密会するために作った蔵で、伊三郎が亡くなった今は米や味噌を置いているだけだと言って、気楽に見せてくれた。蔵の中は二つに分かれていて、手前の土間には米や味噌、炭や 「あそこで、おめえの姉ちゃんの他にも 「いるさ。親分が平塚に先生を呼んだんは、それが目的だったらしい。『 『遊女魔庫』には四人の流れ者に犯されている居酒屋の女将や、まだ十五歳の呉服屋の娘が強姦されている場面が描かれていた。あの場面が実際に行なわれ、それを貞利が写していたなんて信じられなかった。 「何て野郎だ。そんなきったねえ事をしてたのか」 「ほんとの事を言やア、姉ちゃんは親分が殺されてホッとしたんじゃねえのかなア。もし、生きてたら 「そうか。お北が伊三郎からそんな目に会ってたとなると、仇討ちをするってえのはどうも嘘臭えな」 「そうさ。親分から解放されて、姉ちゃんはどっかで幸せにやってんじゃねえかと思うぜ。江戸の 「お北は金は持ってたのかい」 「小金は貯め込んでたらしい。俺がここに来た時、ここにはなかったから、そいつを持って旅に出たんだんべえ」 久次郎は一応、孝吉から尾島村にある実家の場所を聞いた。 「もし、姉ちゃんが帰って来たら絶対に知らせるんだぜ」 孝吉はうなづいた。お奈々は心配そうな顔をして孝吉の横顔を見つめていた。二人と別れて、久次郎とお紺は外へ出た。 「ねえ、尾島に行くの」とお紺が土手の上から利根川を眺めながら聞いた。 「おめえはどう思う」 「尾島にはいないと思うわ。それに、あの人の話だと、お北が伊三郎の仇討ちをするとは思えない。まして、あれから二年も経ってるのに、今更、仇討ちでもないでしょ」 「かもしれねえな。やはり、人違えだったのか‥‥‥とりあえず、どっかで昼飯でも食ってから帰るか。松の野郎が何かをつかんだかもしれねえ」 お北の家から、突然、木崎節が聞こえて来た。孝吉が唄っているらしい。お奈々の合いの手も聞こえて来る。 「まったく、のんきな野郎だぜ」久次郎は二階を見ながら苦笑した。 「結構、いい声してるじゃない」 〽雨が三年ひでりが四年 久次郎とお紺は孝吉の唄を聞きながら土手から下りると、賑やかな大通りの方へと足を向けた。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧