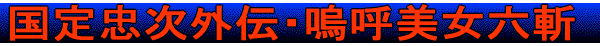

7.謎の女
朝から風の強い日だった。 用があって、朝早く、 風が強いので、通りには人影が少なかった。 村田屋を覗くと客の姿はなく、奉公人に成りすました 「おい、なかなか似合ってるじゃアねえか」と久次郎が声を掛けると、庄太は驚いて顔を上げ、「あっ、兄貴、脅かさねえでくだせえ」と照れ臭そうに笑った。 「今からでも遅かアねえ、おめえ、堅気に戻ったらどうだ」 「兄貴、よしてくだせえよ。こんな堅っ苦しい格好して、一日中、店番なんかしてたら腐っちめえますよ」 「案外、楽しそうにやってるじゃねえか」 「いえ、まあ、今はちっと番頭さんが席を外してるんで、おしんちゃんと話ができるんですけどね、番頭さんが 「まあ、油断しねえでしっかりやれ」 「へい」 「へいじゃねえ。はいだ」 「はい、かしこまりました」庄太はかしこまって頭を下げた。 おしんが隣でクスクス笑っていた。 久次郎はうなづくと村田屋を出て、六軒先にある太物屋の井筒屋を覗いた。思った通り、おゆみの姿はなかった。久次郎も考えて、ここには見張りを入れなかった。鹿安に毎日、違う格好をさせて、おゆみを守らせる事にした。鹿安もそれは面白いと今日は貞利の真似をして、絵師に扮しているはずだったが、その姿も見当たらない。番頭の常五郎に聞くと、裏庭にいるだろうと愛想笑いを浮かべながら言った。 店の脇を抜けて裏庭に行ってみると、鹿安が池の中に入って 「おい、おめえら、何やってんだ」 久次郎は 「あっ、兄貴」と鹿安が言うと、「ちょっと、動かないでよ」とおゆみが怒った。 おゆみの絵を覗いてみると、 「ほう、おめえ、なかなか、筋がいいじゃねえか。それだけの絵が描けりゃア、平塚の先生の弟子になれるぜ」 「ほんと? あたし、女絵師になろうかな」おゆみは嬉しそうに笑った。 「そいつもいいかもしれねえぞ」 「先生に紹介してもらって、江戸の偉い先生のお弟子になろうかしら」 「何も、江戸まで行く事アねえや。平塚の先生の弟子になりゃアいいじゃねえか」 「あたし、江戸に行ってみたいのよ。誰か一緒に行ってくれないかしら」 「こんな田舎じゃ、つまらねえか」 「うん。もう、飽きちゃった。毎日、同じ顔ばかり見てんだもん」 「江戸に行きゃアいい男がいるってか」 「そうよ。いい男が一杯いるのよ」 「音吉みてえのがか」 おゆみは顔を上げて久次郎を見ると、寂しそうに笑った。「そうね。音吉つぁんみたいなのがね」 「まあ、おめえなら江戸に行ったって立派にやってげるだんべえ」 「そうかしら‥‥‥ねえ、これ見て」とおゆみは縁側に伏せてあった絵を見せた。「これがあたしだって言うのよ、 その絵は、おゆみの顔を描いたようだったが、あまりにも下手くそで、吹き出さずにはいられなかった。 「まったく、あたしを馬鹿にしてるよ」 「おい、安。いくらなんでも、こんな絵を描いて絵師たア笑わせるぜ。明日から 「えっ、蛙ですか?」 鹿安は訳がわからないという顔をした。それを見ながら、おゆみはゲラゲラ笑っている。 「遊んでるのもいいが気を緩めるなよ」 二人と別れると久次郎は干菓子屋の 「ひどい風ですねえ」 「まったくだ。 「あのう、お嬢さんが江戸に連れてかれたってえのは本当なんでしょうか」 「おめえんとこの梅吉がうちの角次と一緒に江戸に行ったが、確かな証拠があったわけじゃアねえんだ。角次にしても、親御さんにしても、何もしねえじゃいられねえんで江戸に捜しに行ったんだ。見つかってくれりゃアいいが難しいだんべなア」 「そうですか‥‥‥一体、どこに行っちゃったんでしょう。お嬢さんがいなくなってから、もう、うちん中はお 「わかってる。できるだけの事はしてるんだ。お嬢さんは必ず、連れ戻す。もう少し、時間をくれ」 「お願いします」と言って忠太はしょんぼりしながら帰って行った。 お関を連れ戻すには、人さらいの一味がもう一度、現れるのを待つしかなかった。久次郎は気を引き締めて、怪しい者がいないか、目を光らせながら大通りを翁屋に向かった。 砂埃の舞う中、桐屋の前にいる 「あら、久次さんじゃない」と手を振った。 貞利の家に出入りしているお万だった。 「そんなとこで何してんだ」と久次郎は大声で聞いた。 「仕事に決まってんじゃない」とお万も大声で答えて、陽気に笑った。 「 「大した荷物じゃないけど稼ぎになるのよ」 「ほう、そいつはよかったな」 「ねえ、その辺に『翁屋』ってない」 「翁屋はそこだ」と久次郎は二軒程先を指差した。「翁屋の荷物を運んで来たのか」 「翁屋だけじゃないわ。あっちこっちよ」 久次郎とお万は翁屋の前で行き会った。 「あとは橘屋と井筒屋と‥‥‥」お万は馬に積んだ荷物の宛て先を読んでいた。 「橘屋に井筒屋?」 「それと、村田屋よ」 久次郎は首をかしげた。お万が言った所は皆、七小町の家だった。 「そういえば、おめえ、今、桐屋の 「うん。桐屋にも届けたの」 その時、「 五月屋にいた浅次郎だった。さらに、越後屋にいた幸次、桐屋にいた秀吉もわめきながらやって来た。三人が大声で騒いでいるので、近所の者たちが何事かと通りに顔を出した。 「てめえら、静かにしろい」久次郎は怒鳴った。「 「兄貴、大変なんだ」 三人は同時に手に持った荷物を目を背けるようにして、久次郎に見せた。それを見て、久次郎は声が出なかった。代わりに、お万が大声で悲鳴を上げた。 荷物の中にはバラバラになった人間の死体が入っていた。浅次郎の持っているのは左もも、幸次のは折れ曲がった左腕、秀吉のは折れ曲がった右腕だった。 お万の悲鳴を聞いて、町の者たちがどおっと集まって来た。死体の一部を見て、女たちがまた、悲鳴を上げた。 久次郎は浅次郎たちを番屋に行かせ、翁屋から出て来た桶松に早く、親分を呼んで来いと命じた。呆然と立ち尽くしているお万を連れ、荷物を積んだままの馬を引っ張りながら、久次郎も丁切の脇にある番屋に向かった。見物人がゾロゾロと後について来た。 木戸番の親爺に見物人たちを押さえさせ、番屋でお万が持って来た荷物を調べてみると、宛て名はやはり、七小町の家で、荷物は全部で七つあった。すべてを開けてみると、右腕、左腕、右もも、左もも、右すね、左すね、そして、生首があり、胴体だけがなかった。生首は苦痛に歪んでいたが、お関に間違いない。残酷にも生首の宛て名は橘屋だった。 二年前のお常と同じように、手や足は傷だらけで、手首、足首には縛られた跡が残っている。それと、不思議な事に左手の小指が切られてあった。 放心状態のお万に聞くと、平塚の 「その女はどんな女だ。お北じゃなかったのか」と久次郎はお万に聞いた。 「お北?」とお万は久次郎を見たが、何の事かわからないといった顔付きだった。 「伊三郎の妾だ。平塚の先生んちに出入りしてたから、おめえも見た事あるだんべ」 「ああ、あの人。違うわ。あの人じゃなかったわ」 「なに、お北じゃねえ」 「違うよ。頭巾で顔を隠してたけど、あの人じゃなかったわ」 「それじゃア、お夢だな。三味線の師匠のお夢だな」 「違うよ。お師匠じゃないよ」 「おめえ、お夢を知ってんのか」 「あたしも時々、三味線を習いに行ってんだよ」 「おめえが三味線を?」 「あたしだって三味線くらい弾くさ」 「畜生め。お北じゃねえ、お夢でもなけりゃア、一体、誰なんでえ」 忠次と円蔵が見物人をかき分けて、番屋に入って来た。 「おい、こいつは一体、どういう事なんでえ」 忠次が顔をしかめながら、バラバラ死体を眺めた。 「親分、見た通りです。俺アこれからすぐに、下手人を追いかけます。詳しい事ア、こいつに聞いてくだせえ」 久次郎はお万をその場に残すと、浅次郎、秀吉、幸次を連れて平塚へと走った。 平塚の立場で休んでいる その後、女は急ぐように渡し場の方に行ったと言うので、久次郎たちも後を追った。 渡し場の舟頭もしっかりとその女を覚えていた。女は急いでいるらしく、銭は弾むから、すぐに渡してくれと言った。舟頭も喜んで引き受けて、女を中瀬に渡したという。 久次郎たちも中瀬に渡り、立場にいた駕籠かきに聞くと、 女を乗せた駕籠かきはすぐに見つかった。深谷のどこで降ろしたかを聞くと、すぐに、その場所を目指して、一里半ばかりの道を走った。道の両側には新芽が顔を出した 汗と砂埃にまみれて深谷宿に着き、女が駕籠から降りたという仲町の旅籠屋、吉野屋を捜した。吉野屋はすぐに見つかった。しかし、旅籠屋の小僧に聞いても、女中に聞いても、駕籠から降りた女の事は知らなかった。せっかく、ここまで追い詰めたのに見失ったかと途方にくれたが、吉野屋の真向かいにある茶屋で聞くと、そこの娘が女を見ていた。女は駕籠から降りると吉野屋の横の細い路地に入って行ったという。 さては、ここに住んでいるのかと久次郎たちは女を追った。路地の両側には家々が立ち並び、そこを抜けると桑畑に出てしまった。この近所に住んでいるに違いないと、一軒一軒、聞いて回ったが、ついに見つけ出す事はできなかった。 久次郎たちが深谷に向かっている頃、境宿では、忠次と町役人たちが相談して、伊勢崎の酒井様の御領内取締役を務め、関東取締出役の道案内でもある木島村の助次郎に知らせた方がいいという事になった。人が殺されたとなると伊勢崎の陣屋に届け、役人の検視を受けなくてはならない。十手を持っていない忠次だけの力で解決する訳にはいかなかった。 木島村の助次郎は百々一家から寝返って伊三郎の代貸となった裏切り者だった。伊三郎が生きていた頃は桐屋の賭場を任されて、境宿に住んでいたが、伊三郎がいなくなり、島村一家が分裂すると木島村に帰った。その数ケ月後に伊勢崎藩の御領内取締役を務めていた父親が亡くなったため、助次郎は父親の跡を継いで御領内取締役となり、関東取締出役の道案内にもなった。木島村と 忠次としても助次郎がでしゃばるのを見たくはなかったが、どうしようもなかった。 「なあに 「あまり、でけえ面をすんなよ」と忠次もニヤリと笑った。「うちの御隠居は未だに、おめえさんの事を許しちゃアいねえ。おめえさんを早く叩っ斬ってくれと年中、言ってんだ。下手な真似をしたら、その首が飛ぶと思って慎重に事を運ぶこったな」 「脅すつもりか」 「脅しなんかじゃねえ。うちの若え者の中にゃア、急ぎ旅ってえのをやってみてえっていう無鉄砲なのが何人もいるって事よ」 「ふん。今はおめえとやり合ってる暇はねえ。手柄を上げさせてもらうぜ」 助次郎はお万を連れて、平塚へと向かった。 助次郎と入れ違いのように貞利を呼びに行った桶松が帰って来た。関東取締出役の役人がやって来ると手配中の忠次と文蔵はしばらく隠れなければならないので、この事件を解決させるために忠次が呼んだのだった。しかし、貞利は玉村に行っていて留守だった。 忠次は後の事を円蔵に頼み、文蔵を連れて赤城山中に身を隠した。 その後、伊勢崎の陣屋から役人たちがやって来て、バラバラになった死体を検視し、本陣において関係者から事情を聞いた。お関が行方不明になった事は一応、知らせてあったので役人も知っていたが、まさか、こんな事になるとはと顔を曇らせた。助次郎が下手人を捕まえて戻る事を願いながら、役人たちは本陣に腰を落ち着けた。 深谷に行った久次郎たちが手ぶらで帰って来たのは日暮れ近くだった。目の色を変えて、久次郎の後を追って行った孝吉も疲れたような顔をして一緒に帰って来た。 それからしばらくして、助次郎も手ぶらで帰って来た。久次郎は百々村に帰り、助次郎は本陣に行き、探索の結果を報告した。 「どうした、下手人は捕まったか」 久次郎の声を聞いて円蔵が飛び出して来た。 久次郎は首を振った。 「下手人は女だったらしいが、そいつはお北でもお夢でもなかったってえじゃねえか」 「へい、驚きました。お万も違うって言うし、平塚の駕籠かきたちも、まったくの別人だとはっきり言ってました」 「お関を殺しちまったんじゃア江戸から来た人さらいでもねえ。そうなりゃア、一体、何者なんでえ」 「まったく、わからなくなりました」 久次郎が円蔵に連れられて、客間の方に行くと貞利が来ていた。 「どうだった、下手人は捕まったのか」貞利は青ざめた顔をして久次郎を見上げた。 「残念ながら逃げられました」 久次郎は謎の女を追って深谷まで行った事を二人に話した。 「その女は深谷に住んでんのか」と貞利が聞いた。 「そのようです。しかし、見つけ出す事はできなかった」 「助次の奴も深谷に行ったのか」と円蔵が聞いた。 「へい、やって来ました。道案内をやってる深谷の親分に頼んで、深谷中を捜し回ってました。今日は捜し出せなかったようだけど、あれだけの人数で捜しゃア、明日にでも捕まるだんべえ」 「そうか‥‥‥下手人が深谷にいるんじゃ、助次に任せるしかねえな。こんな時は十手を持ってた方が何かと便利だ」 「親分は隠れたんですか」と久次郎は円蔵に聞いた。 「ああ。文蔵を連れて 「へい」 「ところで、先生、今度の事件をどう見なさる」と円蔵が貞利に聞いた。 「まったく、予想外な結果になっちまって‥‥‥玉村であんな事件が起きたと思ったら、今度は境で起こるたア。多分、下手人はわたしが描いた本の真似をしたに違えねえ。まったく、いやになりますよ」 「玉村の方はどうなんです。下手人の目星はつきそうなんですか」 「はい。お関がいなくなったと聞いて、何となく、いやな予感がしてたんだ。お関がこんな事になる前に、玉村の下手人を挙げたかったんだが遅かった。玉村の方はもう少しなんです。下手人らしい者を何人かに絞り込んで、今、玉村の親分の子分たちが見張りを続けてます。そのうちに尻尾を出すに違えねえんだが、敵も警戒してるのか、なかなか、尻尾をつかませねえようです」 「そうですか。もしかしたら、玉村の下手人がお関をやったんじゃアありませんかねえ」 貞利はうなづいた。「そいつもねえとは言えません。お関をさらったんは女だが、その後ろに男がいるに違えねえ。その男が玉村の下手人なのかもしれません。ただ、同じバラバラ殺人だからといって、すぐに結び付けるのも危険ですな」 「先生、もし、お関を殺したのが深谷に逃げた女だとして、女の力で死体をバラバラにする事ができるんだんべえか」と久次郎は首をかしげた。 「それは何とも言えねえ。必死になりゃア、たとえ、女とはいえ馬鹿力を出すからな」 「それとわからねえのは、下手人はお関をずっと深谷に隠してたんだんべえか。下手人がお関と平塚まで行ったんはわかってるけど、渡し舟にゃア乗ってねえ。それに、下手人はバラバラにした死体を平塚の立場から、お万に頼んでる。深谷からわざわざ平塚まで死体を運んで、そこから馬子に頼むってえのは、ちょっとおかしいんじゃねえだんべえか」 「確かにそうだな」と円蔵が言った。「深谷で殺して、バラバラにしたんなら、わざわざ平塚まで行かなくても深谷で頼みゃアいい。一両も出しゃア、そのくれえの事はやってくれるだんべ」 「そうですな。わからねえ事が多すぎる。 「殺しの予告?」と円蔵と久次郎は同時に言って、貞利を見た。 「うむ。下手人は七小町全員を殺すつもりなのかもしれねえ」 「下手人は七人の小町全員に恨みを持ってるのか」円蔵は 「かもしれません。七小町に選ばれなかった恨みとか‥‥‥しかし、そうなると、深谷の女が、どうして、七小町に恨みを持つのかわからねえな」 「本当に深谷の女かどうか確かめる必要がありそうだな。今まで、ずっと、姿を隠していた女が突然、平塚に現れて、その後、深谷まで行ったってえのがおかしい。中島に行ったり、木崎に行ったりしたようにごまかしかもしれねえ」 「そいつも充分に考えられる。深谷とはまったくの逆方向に隠れてたってえ事も考えられますな」 「深谷の方は助次の奴に任せて、もう一度、洗い直した方がよさそうだな」 「洗い直すって、どこを洗い直すんですか」と久次郎は円蔵に聞いた。「お関を恨んでたんは徳次郎ぐれえです。しかし、あの女はお夢じゃなかった。七小町を恨んでる奴を捜すったって」 「もう一度、聞き込みをやり直すんだ。あん時と違って、お関が殺された今、何か新しい事実が出て来るかもしれねえ」 「へい、わかりました。七小町の見張りはどうします」 「それは続けた方がいいだろう」と貞利が言った。「下手人が捕まるまでは安心できねえ。わたしが描いた女が次々に殺されるなんて、まったく、たまりませんよ。どうせ、仕事なんか手につかねえだろうから、わたしにも下手人捜しを手伝わせてくだせえ」 「先生が一緒なら心強えや。よろしくお願えします」 貞利はその夜、平塚には帰らず、円蔵と久次郎と一緒に事件の再検討をした。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧