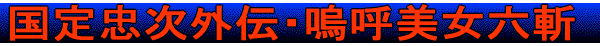

3.江戸に行ったおゆみ
貞利は『国定一家女列伝』を描いていた。 忠次が一家の名を百々一家から国定一家に変えた宣伝に、来年の正月、馴染みの旦那衆に配るために頼んだのだった。 忠次の妾のお町。円蔵の妻のおりん。三人の女壷振り、お辰、お紺、お藤。代貸の清五郎の妻お加代。代貸の富五郎の妻おすみ。代貸の千代松の妻お沢。代貸の友五郎の妻お美奈。文蔵の妹で清蔵の妻お安。代貸の助八の妾おすえ。代貸の茂吉の妾お若と十二人の女たちを描いていた。 久次郎が顔を見せると、ちょっと一服するかと筆を置いて、客間の方に案内した。 「仕事の方は順調ですか」と久次郎は聞いた。 「まあ、何とかな」と貞利は答えて、ニヤッと笑った。「国定一家の方は順調だ。艶本の方は今、思案中と言った所だな」 「思案中って、仙太郎の事を描くんじゃねえんですか」 「版元もみんなも期待してるから、一旦は描こうと思ったんだがな、やめる事にしたよ」 「えっ」と久次郎は驚いて、貞利の顔を見つめた。 「仙太郎の事を描くと、どうしても『美女六斬』と同じような絵になっちまうんだ。それじゃア、版元もお客さんも満足しねえだろう」 「そうか。先生の本を真似した仙太郎をまた、先生が描くってえのもおかしなもんですね」 「そうさ。真似の真似を描いたんじゃ、どうしたって『美女六斬』よりいい物ができっこねえ。もう血まみれの残酷物を描くのも飽きてきたしな、来年は気分を変えて、楽しく見られる艶本にしようと決めたんだよ」 「そうですか。その方がいいかもしれませんね。そろそろ、伊三郎の亡霊から離れた方がいいですよ」 「伊三郎の亡霊か。まさしく、久次さんの言う通りだ。仙太郎のような奴が出て来たのも、島村の親分の 「へえ、『天女乃舞』ですか。題を聞いただけでも見たくなりますねえ」 久次郎は薄い 「みんなの期待に答えられるように、面白え 「さすが、先生、勘が鋭えですね」 「いや。この土砂降りん中、わざわざ、やって来るんだから、どうしてもそう思うさ」 「実は、今度アおゆみがいなくなっちまったんです」 「ちょっと待ってくれ。おゆみなら江戸に行ったぜ」 「えっ」と久次郎はまた驚いて、貞利の顔を見つめた。 「うちの者は知らねえのか」 「へい、何も知りません。おゆみがいなくなったんは三日前で、ようやく、今日になって心配しだしたってえわけです」 「まったく、あの 「江戸に行く前にここに寄ったんですか」 貞利はうなづいた。「暗くなってから、雨ん中を旅支度で現れたぜ。明日、早く、旅立つから朝まで置いてくれってな」 「泊めたんですか」 「なアに、泊めたといっても寝やしねえ。江戸に行ったら、当分、帰って来ねえから、あたしの絵を描いて、うちに届けてくれって言うんでな、絵を描いてやったよ。その後、酒を飲みながら江戸の話など聞かせて、おゆみは夜が明けると旅立って行った」 「それはいつです」 「 「たった一人で江戸まで行ったんですか」 「いや、深谷に柳屋の徳次郎が待ってるって言ってたぜ」 「徳次郎が?」 「ああ、俺もおゆみが徳次郎と関係あったなんて知らなかったんだが、何回か会ってたらしい。江戸に行った徳次郎から手紙が来たらしくてな、おゆみも江戸に行く決心をしたようだ」 「へえ、徳次郎の奴はおゆみを江戸に呼ぶ程、惚れてたんですかね」 「おゆみが江戸に行きてえって言ってたのを聞いていて、もしかしたらと手紙を出したんだろう。それがうまく行ったんで、深谷まで来て、おゆみを呼び出したようだ。おゆみは手紙をもらって、すぐに旅支度をして家を飛び出して来たんだろうな」 「徳次郎の奴は深谷まで来て、どうして、うちに帰らねえんです」 「一年は帰って来るなってきつく言われたようだ。遊びが過ぎて、江戸に行っても金が自由にならねえんだろう。金がありゃア遊ぶとこはいくらでもあるが、金がなけりゃア女遊びもできねえ。そこで、おゆみを呼んでみようと考えたに違えねえ」 「そうだったんですか。おゆみもとうとう江戸に行っちまったか‥‥‥境も寂しくなるな」 「そうだな。おゆみは人気者だったからな。そのうち、手紙が届くだろう。向こうに着いたら、必ず、手紙を出すように言っておいたからな」 「そうですか‥‥‥」 「ああ、そうだ。おゆみの絵なんだが届けてくれねえか。雨がやんだら届けようと思ってたんだが、いつになってもやまねえんでな」 貞利は絵を見せてくれた。 おゆみが手紙を読みながら、嬉しそうに笑っている姿だった。 「兄貴」と呼ぶおゆみの声が聞こえたような気がした。 「おゆみを『天女乃舞』に描こうと思ってるんだ」と貞利は言った。「面白え娘だからな。それに絵になるよ、あの娘は」 「そいつはいい。おゆみが出てくりゃア、みんな買いますよ」 「それと、お万も描こうと思ってる。三巻物にするには、もう一人いるんだが、それを誰にするか今、悩んでるんだよ」 「お万もいい女だからな、男どもが見たがるだんべ。面白え本ができそうですね」久次郎は貞利の新しい艶本を想像しながらニヤニヤしていたが、急に真顔になって、「ところで、先生、話は変わりますが、お関の小指はどこに行ったんだんべえ」と聞いた。 貞利は驚いたように顔を上げた。 「その事か‥‥‥俺も気になってな、玉村の親分に聞いてみた」 「わかりましたか」 貞利は首を振った。 「仙太郎のうちを床下から天井裏まで捜したが見つからなかったそうだ。ただ、お八重の小指は出て来たらしい」 「お八重も小指を切られてたんですか」 「ああ。お関の小指はどこにやったって仙太郎に聞いたら、奴は気味の悪い笑みを浮かべて、食っちまったと言ったそうだ」 「小指を食った? 気違えだ。お八重のは取っておいて、お関のを食うってえのはどういうこってす」 「お八重の時は初めての人殺しだったんで、逃げるんが精一杯で、そんな余裕はなかったんだろう。塩漬けにして天井裏に隠してあったそうだ」 「何で、小箱なんか切ったんです」 「そいつは、ただ、俺の本の真似しただけさ」 「えっ、お常の小指もなかったんですか」久次郎は当時の事を思い出してみたが、そんな記憶はなかった。 「お常の左手は見つからなかったんだよ」と貞利は言った。 「そうだ、左手は見つからなかったんだ」 「馬吉の奴に左手をどうしたって聞いたら、お諏訪様に捨てたって言いやがった。あそこは隅から隅まで捜したが見つからなかった。多分、野良犬がくわえてどこかに持って行っちまったんだろう。そん時、馬吉が小指の話をしてな、小指は肌身離さず持ってたが捕まった時、やべえと思って、こっそり利根川に捨てたって言ったんだ。その話を聞いたんで、俺も艶本の中のお常の小指を切ったってえわけだ」 「へえ、そうだったんですか。しかし、あの本は何度も見たけど、小指には気づかなかった」 「そこまで気づくんは余程の変態だ。普通の者はそんな細けえ所まで見ねえ」 貞利は仕事場から『美女六斬』を持って来て久次郎に見せた。 下巻の第三図、お常の死体の両足を切り落とし、切った足を手に持ちながら、死体を犯している馬吉が描いてある場面、ぐったりとした左手の小指が確かになかった。 続いて第四図、お常の死体をバラバラにし、生首を抱いて笑っている馬吉、馬吉の足元に転がっている左手に小指がなかった。どちらの図も、描かれている左手は小さく、言われて見なければわからなかった。 「驚きました。確かに小指がねえ」 「誰も小指の事なんか気づかねえと思ってたよ。小指がねえのに気づいた仙太郎のような奴がいたってえのは嬉しいが、実行に移すたア困った事だ」 「馬吉はどうして、小指を切ったんですか」 「女郎の指切りと同じさ。自分だけの女だってえ 「成程。仙太郎の方は女郎屋通いもした事がねえんで、馬吉の気持ちはわからなかったんだな。ただ、先生の本の真似して小指を切ったが、どうしたらいいのかわからず、食っちまったんですかね」 「かもしれねえな」 「これで謎が解けて、すっきりしました。おゆみがいなくなったと聞いた時ゃア、もしかしたら、お関を殺した奴は仙太郎じゃなくて、他にいるんじゃねえかって思ったんですが、これで安心しました。おゆみは江戸に行ったようだし、もう二度と、あんな悲惨な事件は起きねえだんべえ」 「馬吉や仙太郎のような気違えが、そう何人もいたらたまらねえぜ」 「先生、忙しいとこをすいませんでした」 「いや。久次さんも保泉村の方が忙しいたア思うが、お紺さんを連れて遊びに来てくれ」 「ええ、この長雨がやんだら、小町たちも連れてやって来ますよ」 久次郎は貞利と別れ、弟子の庄次と一緒に境に帰った。 雨は少し、小降りになったようだった。 「おめえ、おゆみが江戸に行ったの知ってたか」 「はい」と庄次はうなづいてから、「残念です」と小声で言った。 「何が残念なんだ」 「おゆみは絵の手本になってくれるんです」 「絵の手本なら、いくらでもいるだんべえ」 「ええ、でも、裸になってくれるのはおゆみとお万さんだけですよ」 「何だと。おゆみはおめえたちの 「ええ」と庄次は当然の事のようにうなづいた。 「裸になって、どんな格好するんだ」 「どんなって色々ですよ」 「股をおっ広げたりもすんのか」 顔を赤くしながら庄次はうなづくと、「艶本を描くための稽古ですから」と言った。 「畜生め。おめえら、いい思いしてやがんな。それで、おゆみのべべっちょ(女陰)はどんな 「綺麗です。あそこだけじゃなくって、おゆみは真っ白な身体をしていて、ほんとに綺麗なんです」 「まあな」と久次郎はおゆみの裸を思い出しながら言った。「確かに、おゆみは真っ白ないい身体をしてやがる。あれだけ男出入りが激しいのに相変わらず綺麗だったか‥‥‥」 「もしかして、久次さんもおゆみと?」 「昔の事さ。おめえはおゆみと寝たのか」 庄次は首を振った。 「そういやア、おめえ、おゆみなんか嫌えだって前に言ってなかったか」 「言ったけど、綺麗なもんは綺麗です」 「おめえは確か、おしんが好きだって言ってたな。おしんはうちの庄太とできちまったぜ」 「おしんちゃんの事は言わないでください。あんな風に変わっちゃうなんて」 「もう嫌えか」 「嫌いじゃないけど、もう、いいんです」 「庄次が振られて、庄太といい仲になるたア面白えもんだな」 「もうやめてください」と庄次は突然、叫んだ。 「わかった、わかった。おゆみとお万か‥‥‥おめえ、先生が来年に売り出す艶本の事、何か知ってるか」 「もう残酷なのはやめるって言ってましたけど、何を描くのかは聞いてません」 「そうか‥‥‥ところで、姉ちゃんは元気かい」 「はい。浅次さんと一緒になるみたいです」 「そんなとこまで話が進んでんのか」 「姉ちゃんも二十歳ですから、そろそろ、嫁に行かないと」 「そうだな。浅の奴となら、うまく行くかもしれねえ。おめえも賛成なのか」 「はい、浅次さんはいい人です」 「まあな」 「久次さんの方はどうなんです。お紺さんとうまく行ってるんですか」 「まあな。おめえもいい女を見つけろ。そうすりゃア、好きなだけ女の裸が描けるぜ」 「裸を描くために絵をやってんじゃありません」 「そう力むな。女を描くにゃア、もっと、女を知らなくちゃなんねえ。真面目に先生んとこに通うんもいいが、もっと、女遊びをしなくちゃア駄目だ」 「わかってるんだけど、そんな銭はねえし」 「そうか、よし、今度、俺が木崎に連れてってやる」 「ほんとですか」と庄次は目を輝かせた。 久次郎は木崎行きを約束して庄次と別れ、貞利の描いた絵を届けるために、おゆみの家『井筒屋』に向かった。 それから六日後、江戸からおゆみの手紙が届けられた。相変わらず元気でやっているというので、皆、安心した。 おゆみがいなくなってから、おりんの店にはおゆみと関係のあった男たちが集まって、毎晩、おゆみの噂を 集まった男たちの中で、おゆみの悪口を言う奴は一人もいないという。まったく、不思議な娘だった。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧