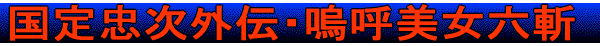

5.越後屋のお奈々
孝吉を殺した三郎太は木崎宿に連れて行かれ、現場にいた不流一家の藤次たちも取り調べのために連れて行かれた。久次郎と貞利も左三郎と一緒に木崎に行った。 すでに、下手人が捕まっているお関殺しがからんでいるため、取り調べはなかなか、はかどらなかった。前回の事件を調べた玉村の佐重郎親分と木島の助次郎も呼ばれて事情を聞かれた。 結局、お関殺しの件は落着し、下手人の仙太郎が 久次郎が境宿に帰ったのは、お通が殺されてから五日後の夕方だった。さすがに疲れ切っていた。早く保泉村の家に帰って熱い風呂に入って眠ってしまいたかった。 「久次さん、違うんです。孝吉さんじゃありません。お通ちゃんを殺したのは孝吉さんじゃないんです」お奈々は雨に濡れるのも構わず、久次郎を見つめて、まくし立てた。 「何を言ってんだ。おめえの気持ちはわかるがな、孝吉のやった事なんだよ」 「違います。違います。絶対に違うんです」 泣き続けていたのか、お奈々の目は腫れていて、そして、また、泣き出しそうだった。 久次郎はお奈々を大黒屋に連れて行って話を聞いた。 「孝吉さんがあんな事をするはずありません」とお奈々はやつれた顔で、久次郎を必死に見つめながら言った。 「おめえの気持ちはわかる」と久次郎はうなづいた。「俺だって お奈々はホッとしたように胸を押さえ、「そうでしょ。孝吉さんじゃないんです」と微かに笑った。 「しかしなア、蔵ん中にバラバラ 「そんな、違います。孝吉さんがお関ちゃんを殺したなんて‥‥‥」お奈々の目から涙が溢れ出た。 お奈々は涙を拭くと、「絶対に孝吉さんじゃありません」と言った。 「違う、違うったってしょうがねえ」 「お願いします。もっと、よく調べてください」 「調べてくれったってなア」そんな事は無理だというように久次郎は首を振った。 「あたし、色々と考えたんです。きっと、孝吉さんは本物の下手人の 「いや、孝吉はバラバラにした死体を利根川に捨てるつもりだったんだ。川の水は増水して勢いよく流れてる。死体を投げ込みゃア、あっと言う間に下流まで流されちまうだんべ。ところが、孝吉が捨てる前に不流一家の奴らが来ちまったってえわけだ」 「そんなの違います。孝吉さんは罠にはまったんです。本当の下手人は孝吉さんに罪をかぶせて、笑ってるに違いないんです」 「気味の 「だって、孝吉さんがあんな事をするはずありません。馬吉や仙太郎と比べてみてください。性格が全然、違います」 「確かにな‥‥‥おめえ、孝吉に痛え目に会わされた事アねえか」 「そんな事ありません。あの人はそんな変態なんかじゃありません。あの『美女六斬』の本だって、新八さんとこでチラッと見ただけで、気持ち悪いって言ってたんです」 「なに、孝吉は『美女六斬』を持ってねえのか」 「そんなの持ってませんよ。先生の美人絵は何枚か持ってますけど、残酷な本なんて持ってません。新八さんから買って、 「奴は『美女六斬』を持ってねえのか‥‥‥」久次郎は煙管を取り出すと、煙草に火を点けて考えた。 「お願いします。もう一度、よく調べてください。孝吉さんじゃないんです」 お奈々は涙を流しながら両手を合わせて、久次郎をじっと見つめていた。 「おめえの言う事アわかった。無駄だとは思うが、もう一度、当たってみるぜ」 「お願いします」 うなだれているお奈々を残して大黒屋を出た久次郎は新八の絵草紙屋に顔を出した。 暇そうに 「ああ、まったくだ」とうなづきながら、久次郎は飾ってある『境七小町』の美人絵に目をやった。これが売り出されてから、まだ半年も経っていないというのに、お関が殺され、お通までも殺されるなんて、とても信じられない事だった。美人絵から新八に目を移すと、新八も暗い表情で、お通の絵を見ていた。 「孝吉はおめえさんの弟分だったはずだな。奴があんな事をすると思うか」と久次郎は新八に聞いた。 「なに、奴じゃねえのか」と新八は目を見開いて久次郎を見た。 「そうじゃねえが、今、お奈々に泣きつかれてな。もう一度、よく調べてくれって言われたんだ。俺としてもちょっと納得できねえ事があるんでな」 「そうかい。奴が無実なら証明してやってくれ。俺もおかしいって思ってたんだ。奴があんな事をするはずねえってな。俺は奴が三下の頃から知ってるが、あんな事をする奴じゃねえ」 「ちょっと聞きてえんだが、孝吉は『美女六斬』は持ってなかったのか」 「持ってねえだんべえ。奴はああいうのは好かねえようだ。どっちかって言やア、仲良く抱き合ってる奴の方が好きだったな」 「英泉のわ印を持ってるって聞いたが、どんな奴だ」 「孝吉は英泉が描く 孝吉が持っている『色自慢江戸紫』という艶本を見せてもらったが、残酷な場面など一つもない普通の艶本だった。 「おめえさん、お関の小指がなかったのを知ってるか」久次郎は艶本を眺めながら、何げなく聞いた。 「ああ、そんな噂は聞いたぜ。その小指が孝吉んちにあったのかい」 「いや、見つからなかった。孝吉がどうして、小指を切ったのかわかるか」 「そんなの俺が知るわけねえや」 「お常の小指もなかったそうだ」 「へえ、そうかい‥‥‥ちょっと待て、お常ん時は俺も調べたから知ってるが、そんな覚えはねえぜ。嘘言うない」 「本当だ。お常の左手は見つからなかった。しかし、平塚の先生が馬吉に聞くと左手の小指を切ったって言ったそうだ」 「へえ、初耳だな」 「『美女六斬』を見りゃアわかる」 「描いてあんのか」 新八は住まいの方に行って、『美女六斬』を持って来ると上巻から絵を眺め始めた。 「どこだい」 「下巻だ」と久次郎は教えた。 新八は下巻を手に取るとバラバラにされた左手の小指がないのを見つけた。 「へえ、ほんとだ。気がつかなかったぜ。あいつも細けえとこまで描くなア」 「下手人はそれを真似して、小指を切ったそうだ。玉村の女郎の小指もなかったらしい」 「そうだったのかい‥‥‥しかし、よくまあ、こんなとこまで見るなア」 「普通の者はそんなとこまで気づかねえ。実際に自分もやってみてえと思う者だけが、小指がねえ事に気づくんだんべえ」 「となると、下手人は孝吉じゃねえぜ。孝吉がそんな事を知ってるわけがねえ」 「それがわかりゃア白だが、伊三郎か先生から聞いたのかもしれねえ。先生がその本を描いてた頃、奴は先生んちに出入りしてたからな」 「そうか‥‥‥しかし、奴がわざわざ、そんな細けえ事までするたア思えねえ」 「確かにな。しかし、奴が下手人じゃねえとなると、本物の下手人がまだ、どこかにいるってえ事になる」 「畜生め。一体、誰なんでえ」 「わからねえ。もう一度、はなっからやり直さなくちゃならねえ」 久次郎は百々村に顔を出して、文蔵の兄貴と円蔵に本物の下手人がいるかもしれない事を話し、もう一度、小町たちを見守るように頼むと保泉村に帰った。 一風呂浴びて、さっぱりした久次郎はお紺を相手に、お通殺しをもう一度、検討してみた。 「確かに、おかしいわねえ」とお紺が お紺は久次郎がもう一度、じっくり読み直そうと持って来ていた『美女六斬』を示した。 久次郎はうなづくと、酒を一口飲んだ。「もし、本物の下手人がいたとして、どうして、お通の死体を孝吉の蔵ん中に隠したんだんべ」 「それは孝吉に罪を着せるためでしょ」 「何のために」 「さあ。もしかしたら、孝吉が本物の下手人の事を知ってしまって口封じのためかしら」 「口封じったって、孝吉を殺したんは不流一家の奴らだ。奴らが孝吉を殺したから口封じになったが、殺さなかったら孝吉の口から何もかもばれるって事になるぜ」 「そうよね。下手人はお通の死体を蔵に隠して、孝吉も殺すつもりだったのかしら。もしかしたら、自害に見せかけるつもりだったんじゃない。でも、下手人が来た時、孝吉はいなかった。下手人はどっかに隠れて孝吉が帰るのを待ってたのよ。殺そうと思ったら、不流一家の人たちが来て孝吉を殺しちゃった。下手人は安心して帰ってったんじゃない」 「うむ、かもしれねえな‥‥‥となると、下手人は孝吉んちの蔵の鍵のありかを知ってる奴だな」 「蔵には鍵がかかってたの」 「かかってた。不流一家の連中が鍵を開けて、お通を見つけたんだ」 「ねえ、その鍵、どこにあったの」 「台所の 「それじゃア、すぐに見つかるじゃない」 「しかしなア、死体を運んで行くんだ。まごまごしてたら自分が危なくなる。あらかじめ、知ってたと考えた方がいいんじゃねえのか」 「そうか。お通の死体を持って、ウロウロできないわね。まして、雨は降ってるし。となると、鍵の事を知ってるのは誰?」 「孝吉んちに出入りしてた奴だな。まず、徳次郎たちだ」 「徳次郎は今、江戸にいるんでしょ」 「いや、わからねえ。この前もおゆみを迎えに深谷まで来てるんだ。こっそり帰って来たかもしれねえ」 「徳次郎が孝吉に弱みを握られたのかしら」お紺は首をかしげた。 「待てよ」と久次郎は酒を飲んだ後、宙を睨んだ。「徳次郎の奴がおゆみと組んでやったのかもしれねえぞ」 「まさか、おゆみちゃんはそんな事しないわよ。徳次郎と一緒に江戸に行ったからって、おゆみちゃん、徳次郎に惚れてたわけじゃないんでしょ。頼まれたからって、そんな事をする娘じゃないわ」 「そうだよな」 「おゆみちゃんは関係ないわ」 「おめえ、やけにおゆみの肩を持つじゃねえか」 「あの娘、妹みたいで可愛いんだもん」 「結構、素直なとこがあるからな。徳次郎と一緒に江戸に行ったとしても奴と一緒にいるたア限らねえ。江戸に着いた途端に、徳次郎なんか捨てて、どっかに行っちまったかもしれねえな」 「そうよ。いい男を見つけてうまくやってるかもね。他に鍵の事を知ってるのは?」 「新八も知ってるかもしれねえな。奴は江戸から本を取り寄せてるんで、平塚にはよく行く。そん時、孝吉んちに寄っている」 「新八さんか‥‥‥もうすぐ、子供が生まれるっていうのに、そんな馬鹿な事しないわよ。他には?」 「孝吉は博奕で飯を食ってたから、平塚の助八の子分の中にも付き合ってた奴がいるとは思うがわからねえ」 「徳次郎たちが一番、怪しいわね。お関の時も疑われたんだから」 「そうなるな。奴らをもう一度、調べ直すか」 「新八さんの方はどうなの」 「お関殺しの時は調べなかった。お関を口説いてたような様子はなかったからな。さっき、会って話を聞いてみたが、お常の小指の事は知らなかった。嘘をついてるたア思えねえ。一応、お通がいなくなった日の行動を洗ってみるが白だんべえ」 「お常の小指か」とつぶやくと、お紺は『美女六斬』の下巻を手に取って眺めた。「この小指がないのを気づくのは確かに、変態かもしれないわね。下手人は間違いなく、この本を持ってる人よ」 「徳次郎は先生の本はすべて持ってる。徳次郎とつるんでる鶴屋の耕作もな。それに、船頭の為吉も持ってたな」 「為吉は孝吉のうちに出入りしてないの」 「わからねえ。奴も博奕好きだから出入りしてた可能性はある」 「調べた方がいいわね」 「ああ」 「あたしはこの事件の事、知らないんだけど、結局、お常のいい人って誰だったの」 「しんさんか。結局、わからなかったんだ」 「しんさんて?」 「中瀬のしんさんだよ。その本に書いてあるだんべ」 久次郎はお紺に上巻を渡した。お紺は上巻の 「そんなはずはねえ。ちょっと見せてみろ」 中瀬のいい人に会いに行くと書いてあり、しんさんの事は書いてなかった。 「しんさんが誰だかわからなかったから書かなかったんかな」 「本当はしんさんだったの」 「そうさ。その言葉を頼りにしんさんを捜し回ったんだ」 「そうだったの。でも、結局、しんさんは見つからなかったんだ。そのしんさんていうのが本当の下手人じゃないの」 「なに言ってんだよ。下手人は馬吉だ。お常がしんさんに会いに行ったにしろ、お常がしんさんと会う前に馬吉に捕まっちまったんだ」 「でも、しんさんはいるはずでしょ」 「そりゃアいるだんべなア」 「しんさんはお常が殺されたのに、どうして名乗って出て来ないの。自分が関係なかったら名乗り出るはずよ。お関ちゃんが殺された時、角次さんは気違いみたいに捜し回ってたじゃない。あげくには確かな証拠もないのに江戸まで行ったわ」 「そうだな、そう言われてみりゃアおかしいな。あん時、お常を捜し回ってたのは先生と新八だ。やはり、しんさんてえのは新八だったんだんべえか」 「新八さんは白だったの」 「一応、色々と調べてみたが、どうも違うようだった」 「洗い直した方がいいんじゃないの」 「うん‥‥‥」 「それとね、あたし、気になってたんだけど、これ、誰のなの」 お紺は上巻の大つび絵(女性器を拡大した図)を久次郎に見せた。「先生、お常のを見て描いたの」 「こいつは多分、お万のだんべ。先生がこれを描いた時、お常は死んでいた。先生はお常のべべっちょなんか見やしねえだんべえ」 「お万て、あの馬子の娘?」 「そうだ。お万は裸になって先生の手本になってんだ」 「へえ、凄いのね」 「お常が逆さ吊りになってる絵があるだんべ。その絵は実際にお万が逆さ吊りにされて、それを先生が描いたんだよ。だから、あんなに迫力があるんだ」 お紺は中巻にある逆さ吊りの絵を眺めた。「へえ、これがお万だったの。ほんとに裸になって吊るされたの」 「そうさ」 「大したもんね。他の絵もみんな、お万なの」 「お北も手本になったらしい」 「ああ、そう言ってたわね。みんな、凄いのね。あたしなんか恥ずかしくって、人様の前で裸になんてなれないわ」 「みんな、変わった女たちさ。おゆみも裸になったらしい」 「へえ、おゆみちゃんも。あの娘なら平気でやりそうだわね」 「その本を描いた時は、おゆみはまだ先生んちに出入りしてなかったけどな、七小町に選ばれてからはちょくちょく遊びに行って、絵の手本になってたようだ。今年の正月に出した『 「へえ、そうなの」と言いながら、お紺は中巻の絵を初めから眺め始めた。 「この縛られてるのはお北なのかしら」と言いながら見ていたが、最後の大つび絵をじっと見つめ、「これはお万のだったのね」と言った。「ホクロまでちゃんと描いてあるから、てっきり、お常のだと思ってたわ」 「ホクロ?」 「ほら、ここに」とお紺は指で示した。 割れ目の右脇、陰毛の中に確かに小さいホクロのようなものが描いてあった。 「こっちのがよくわかるわ」とお紺は上巻の大つび絵を見せた。 「へえ、ほんとだ。おめえよく、こんなホクロなんかに気づいたな」 「あたしじゃないわよ。この間、丹次と亀がこっそり見ててね。ここにホクロがあるのは締まりがいいとか何とか生意気な事を言ってたわ。お常さんは締まりがよかったんですねえって感心してたから、そうねえって言ってやったけど、後で考えたら、その絵を描いたのはお常が死んだ後でしょ。先生が想像して描いたにしてはホクロまであるから、誰かのを見たんだろうって思ったんだけど、そんなの一々、見せる人がいるのかしらって思ってたのよ」 「多分、お万だんべ。いや、お北かもしれねえ。あの頃、伊三郎が死んで、お北も一時、先生んちに 「それにしたって、お万やお北が股を広げて、それを見ながら先生が描いてるなんて、何か、 「先生は真剣そのものだよ。俺たちが博奕に熱中してる時の気持ちで絵を描いてんだそうだ。変な気なんか少しも起きねえとさ」 「そうよね。変な気を起こしたら、こんな絵は描けないでしょうね。でも、もし、これがお万やお北のじゃなくて、お常のだったらどうなるの」 「そうだとしたら、先生がお常のを見たって事になるだんべえ」 「そうなるとどうなるの。先生がお常のいい人だったって事?」 「まさか」 「しんさんていうのが先生なんじゃないの」 「先生の本名は利助だ。どう考えても、しんさんにはならねえ。考え過ぎだよ」 「そうとも言えないわ。お常にしろ、お関にしろ、お通にしろ、みんな、先生に関係あるもの。先生に声を掛けられれば、疑いもなく付いてくでしょ。そして、殺すって事もないとは言えないわ」 「確かにそうだが、先生がどうして、そんな真似をするんだ。先生は何もしねえけど、先生が一声掛けりゃア、娘たちは文句なく先生に抱かれるぜ。そんな先生がわざわざ、娘をかどわかして変態じみた真似をするわけがねえ」 「変態かもしれないわよ。だって、いつも、美女に囲まれていて、誰にも手を付けないなんて正常とは言えないわ。先生だってもう三十に近いんでしょ。おかみさんがいたっておかしくない年よ。それなのに独り者を通してる。女に相手にされない 「お万もおゆみも先生を誘ってるのに抱いてくれねえって言ってたな」 「おかしいわ。馬吉みたいに女を痛めつけないと興奮しないんじゃないの」 「そんな事アねえだんべえ。木崎や玉村の女郎を抱いてんだからな」 「女郎は抱くけど、素人女には手を出さないってわけ。渡世人じゃあるまいし。今時、渡世人だって、そんなの建前だけじゃない」 「もうやめろよ。あれだけの絵を描く先生だ。じっと相手の顔を見ただけで、その女の性格とか、すべてを見抜いちまうのかもしれねえぜ。確かに、先生の回りには器量よしの娘たちが集まって来る。だが、そういう娘たちはみんな目立ちたがり屋の我がままな娘ばかりなんだ。先生はそういう娘は好きじゃアねえ。たとえば、おしんみてえに先生の事をずっと好きだったが、先生の側にも行けねえ娘がいる。世間知らずの何もできねえお嬢さんだと思ってたら、とんでもねえ。こっちが驚く程、芯の強え働き者だ。先生もああいう娘なら一緒になりてえと思うかもしれねえが、ああいう娘は先生の側には行かねえんだ」 「そうか。おしんちゃんには驚いたわね。ほんと、あの娘はいい娘よ。庄太には勿体ないわ。先生の回りには綺麗な娘は一杯集まるけど、おかみさんにしたいっていうのはいないのか」 「そうさ」 久次郎とお紺はお常の大つび絵を眺めながら、酒を酌み交わした。 外では激しく雨が降っていた。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧