
![]()
7
早朝。 ふんどし一丁で滝に打たれている五郎右衛門。両足を踏ん張り、両手を合わせ、仁王のような顔付きをして、ときたま、気合を入れている。 木剣で形の稽古。
新陰流、三学円之太刀
朝の稽古が終わると、五郎右衛門は朝食の支度をした。朝食といっても、わずかばかりの米に野草を混ぜた 五郎右衛門の一日は判で押したように決まっていた。 朝、夜明けと共に目を覚まし、滝を浴び、木剣で形の稽古を何度もやる。それから、朝飯、食後はしばらく、座禅。そして、また木剣を振り、立ち木を打ち、抜刀(居合)をやり、座禅をして、日が暮れる頃、小川で汗を流し、夕飯を食べる。夜は岩屋の中で、彫り物を彫るか座禅をしてから眠る。 今日でもう八日めになるわけだが、五郎右衛門の悩みは解決の糸口さえ、わからなかった。 五郎右衛門は気合を掛けながら木剣を振っていた。 汗を拭こうと小川に近づいた時、ふと、小川の向こう側に女が立っているのに気づいた。 女は五郎右衛門を見ると丁寧に頭を下げた。 五郎右衛門も頭を下げる。なぜ、こんな山奥にあんな女がいるんだろうと不思議に思ったが、あえて無視して、顔の汗を拭いていた。そのうち、どこかに行くだろうと思っていたが、意外にも女は裾をまくって、川の中をこちらに向かって歩いて来た。 年の頃は二十四、五か。見るからに山の女ではない。武家の女であろう。 女は五郎右衛門の側まで来ると笑いながら、「こんにちわ」と言った。 「はあ」 「随分、お強そうですね」 「弱いから、毎日、稽古をしておる」 「そんな事ありませんわ。わたしにはわかります」 「そなたはこんな山奥で何をしてるんじゃ?」 「わたしは、このすぐ上にあるお寺にいます」 「お寺?」 「はい」 「こんな山の中に寺があるのか?」 「はい。ちょっと変わった和尚さんがおります」 「そうか、知らなかった。その寺で何をしてるんじゃ?」 「夫の 「亡くなられたのか?」 「はい。誰かに斬られて殺されました」 「斬られた?」 「夫は剣術使いでした。試合をして負けてしまったのです」 「試合に負けて死んだのか‥‥‥」 「旅の途中で負けてしまったんです」 「そうか‥‥‥」 「あの、お侍さんわたしを助けて下さいませんか?」 「助けるとは?」 「夫の 「相手がわかんのじゃろう」 「縁があれば、きっと会えると思います」 「成程」 「その時は、わたしを助けて下さい。お願いします」 「よかろう。縁があったら、お助けしよう」 「助かりました。お侍さんが付いていて下さったら、もう百人力です」 「それでは失礼」と五郎右衛門は言って、去ろうとした。 「ちょっと、待って下さい。わたしは鶴といいます。お侍さんのお名前は?」 「針ケ谷五郎右衛門と申す」 「ハリガヤゴロウエモン‥‥‥珍しいお名前ですね‥‥‥また、ここに来てもよろしいでしょうか?」 「ご勝手に」 五郎右衛門はまた木剣を振り始めた。 お鶴という女はしばらく、五郎右衛門を見ていたが帰って行った。
|
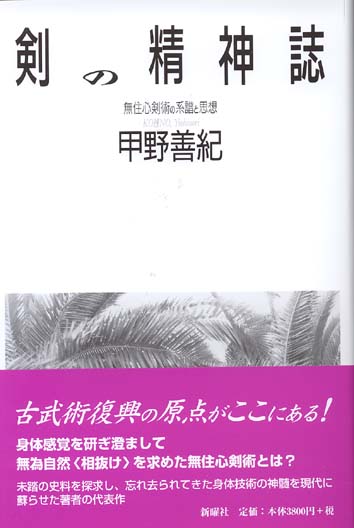 |
| 目次に戻る 次の章に進む |