馬天浜
サハチルー(佐八郎)は六歳になっていた。
みんなから『サハチ』と呼ばれて可愛がられ、健やかに育っていた。
今日、サハチは、去年生まれた弟のマサンルー(真三郎)をおぶった母親に連れられて、馬天浜にある祖父のサミガー大主の屋敷に来ていた。四歳になる妹のマシュー(真塩)と一緒だった。
父のサグルー(佐五郎)はサハチが生まれた小屋の隣りに屋敷を建てて、サハチはそこで成長した。大きなガジュマルの木の下にあった光る不思議な石は、志喜屋の大主に言われた通り、サハチの産土神として、小屋の中に大切に祀られた。『ツキシル(月代)の石』と名付けられ、あれ以来、光った事はないが、サグルーも母のミチ(満)も毎日、その石にサハチの無事を祈っていた。勿論、サハチとマシューも両親の真似をして祈った。
久高島で剣術の修行を積んだサグルーは、ミチの父の美里之子に認められた。わずか半年で、信じられないくらい強くなったサグルーに目を見張って、ミチの事を頼んだぞと許してくれた。サグルーはお礼を言って、さらに強くなるために修行に励んだ。今では、美里之子の武術道場で師範代を務めるほどの腕になり、みんなからは『苗代大親』と呼ばれていた。
苗代大親は今、美里之子と一緒に大グスクに詰めていた。敵である八重瀬按司が、ヤマトゥ(日本)からの船が出入りする馬天泊を狙って、攻めて来るかもしれないというので守りを固めていた。
サハチが生まれた年(一三七二年)の夏、明の国(中国)から使者がやって来た。浦添按司は明の国と朝貢貿易を始め、明の洪武帝から『察度』という名前で、琉球中山王に任命された。以後、毎年のように明の国から大きな船がやって来て、大量の鉄や陶磁器、織物など、貴重な品々が浦添按司のもとへともたらされた。その貴重な品々を求めて、ヤマトゥからの船も以前より増してやって来ていた。
その頃の琉球は、大まかに言えば四つに分かれていた。北部は今帰仁按司に従って、中部は浦添按司に従って、南部は二つに分かれて、西部は島尻大里按司が勢力を持ち、東部は玉グスク按司が勢力を持っていた。
島尻大里按司は中部の浦添按司と手を結んで、勢力を広げようとしている。対する玉グスク按司は島添大里按司、大グスク按司、糸数按司、垣花按司、知念按司と手を結んで対抗している。島尻大里按司の叔父、八重瀬按司は東部を我が物にしようと、八重瀬と糸数の中程に新グスクを築いて隙を窺っている。今回も、八重瀬按司の兵が新グスクに集結しているとの知らせを、糸数按司から受けた大グスク按司は、守りを固めるために武将たちを招集したのだった。
八重瀬按司が八重瀬グスクを攻め落として、自ら八重瀬按司を名乗ったのは八年前だった。滅ぼされた八重瀬按司は玉グスク按司と同盟を結んで、島尻大里按司に対する最前線を守っていた。八重瀬グスクは八重瀬岳という険しい山の中腹にある難攻不落のグスクだった。島尻大里按司の東への進出を押さえていたのだったが、八重瀬按司の奸計によって落城してしまった。八重瀬按司はさらに東へと侵攻するために新グスクを築いた。
当初、八重瀬按司の目的は宿敵である玉グスク按司を倒す事だったが、時代が変わった。浦添按司が明国との交易を始めて、浮島(那覇)にはヤマトゥや南蛮(東南アジア)から船が集まって来ている。これからの世は、良い港を持って海外との交易をしなければ世の中から遅れてしまう。八重瀬グスクには港がない。何としても港が欲しかった。近くで良港と言えば、与那原泊と馬天泊だった。どちらかを必ず奪い取ってやろうと八重瀬按司はたくらみ、島添大里グスク、あるいは大グスクを狙っていた。
六歳のサハチはそんな難しい事は知らない。戦支度をして父親が馬に乗って出掛けると母親の袖を引っ張って、「お爺のおうちに行こう」と言って、連れて来てもらったのだった。
お爺の屋敷はいつも賑やかで面白かった。カマンタ(エイ)を解体しているので、ちょっと臭いけど、そんなのは我慢できた。今日はいい天気なので、ウミンチュ(漁師)たちは皆、海に出て行って、いなかった。それでも離れの屋敷には、遠くからやって来たお客さんがいつもいて、面白い話を聞かせてくれた。
クマヌ(熊野)と呼ばれているヤマトゥの山伏は、三年前の暮れにヤマトゥからやって来て、島の北から南まで歩き回っていた。ジャランジャランと鳴る錫杖と呼ばれる杖を持って、腰に頑丈な刀を差し、柿色の衣を着て、頭には兜巾と呼ばれる角のような物をかぶっている。見るからに異様で、山の中で山伏と初めて出会った、この島の人は山の神様ではないかと勘違いするという。この前来た時はいなかったけど、旅から戻って来ていて、サハチの顔を見ると笑いながら、「おう、サハチか。大きくなったのう」と手招きした。
「クマヌさん、今度はどこに行って来たの?」とサハチはクマヌのそばまで駆け寄ると興味深そうに聞いた。
「浮島に行っていたんじゃよ」とクマヌは目を細めながら言った。
「浮島ってどこ?」とサハチは聞いた。
「西の方じゃ。あちこちから来た船がいっぱい泊まっていてな、面白い所じゃよ。ヤマトゥンチュ(日本人)が住んでいる村や唐人(中国人)が住んでいる村があって、市場では珍しい物が色々と売られている。賑やかな所じゃ。南蛮から来たという者たちもおった。波之上の権現様でばったり知り合いと出会ってのう。こんな所で会うなんて奇遇じゃと話が弾んでな、奴の所にしばらく厄介になっていたんじゃ。そろそろ帰ろうかと思った時、明国からの船が入って来たんじゃ。まるでお祭りのような騒ぎじゃった。偉そうな唐人がぞろぞろと小船から降りて来て、お輿に乗って『天使館』という立派な屋敷に入って行ったわ」
「ねえ、明国のお船って大きいの?」
「大きいぞ。わしらが乗って来たヤマトゥの船よりもずっと大きい。わしには船の事はよくわからんが、どうも、ヤマトゥの船とは造りが違うようじゃ」
「見てみたい」とサハチは目を輝かせて言った。
「もう少し大きくなったらな、連れて行ってやるよ」とクマヌはサハチの肩をたたいた。
二人の会話はヤマトゥ言葉と島言葉が混じっている。祖父も父も、若い頃にヤマトゥの国に行った事があるので、ヤマトゥ言葉を話す事ができ、ヤマトゥ言葉の字も読む事ができた。サハチはまだ読む事はできないが、自然と話す事はできるようになっていた。
クマヌの他にはビング(備後)と呼ばれる無口なヤマトゥのサムレー(武士)、ソウゲン(宗玄)と呼ばれる物知りのヤマトゥの禅僧、ヤンシー(楊渓)と呼ばれる浮島から来た唐人もいた。
クマヌの話だとビングは槍の名人で、ヤマトゥにいた頃は戦に出て活躍していたらしい。しかし、負け戦になって家族を失い、琉球に流れて来たという。ビングはここでウミンチュたちに槍を教えていた。槍術はカマンタを採るのにも役立つし、今は戦乱の世で何が起こるかわからない。サミガー大主がヤマトゥとの取り引きで手に入れた財産を狙う悪党がいるかもしれない。身を守る武術はウミンチュにも必要だった。
ソウゲンは元の国(明の前の王朝)で修行を積んだ偉い禅僧だとクマヌは教えてくれた。元から明に変わる内乱が続いて、ソウゲンは日本に帰れなくなってしまった。何とか、琉球に行く船に乗り込む事ができて、琉球にやって来た。琉球に来てみると日本から来た船がいくつもあり、いつでも日本に帰れる事がわかって安心した。せっかく来たのだから、琉球の事を知ろうと旅に出て、ここまで来たら、居心地がいいので腰を落ち着けてしまったのだった。
ヤンシーは島言葉がしゃべれる唐人だった。浮島に長い間、住んでいたのでしゃべれるようになったと本人は言うが、クマヌが思うには、どうも明国から琉球を調べるように遣わされた地位の高い役人ではないかという。ヤンシーは三日前に、ふらりとここにやって来た。半年程前、クマヌは今帰仁の城下でヤンシーを見ている。別に怪しいそぶりがあるわけではない。それでも、旅をしている唐人は珍しいらしい。
今はこの離れも閑散としているが、ヤマトゥからの船が馬天泊に着くと、乗っていたサムレーや船乗りたちが半年近くも滞在しているので賑やかだった。サハチが生まれた時も、彼らはここに滞在していて、みんなから誕生を祝福された。勿論、赤ん坊だったサハチは覚えていない。四歳だった時も、彼らは滞在していて、その時の事はよく覚えている。毎日のように遊びに来ていて、みんなが帰ってしまうと寂しくて泣き続けていた。
仕事場の方にもヤマトゥから来た人たちが何人か働いていて、高麗(朝鮮半島)という国から来たという言葉の通じない人も働いていた。サハチが仕事場の方に行こうとしたら、妹のマシューが呼びに来た。サハチはマシューと一緒に浜辺に向かった。
白い砂浜がずっと続いている馬天浜は、いつ来ても綺麗だった。
強い日差しを浴びて、青い海はキラキラと輝いている。その海に浮かんだ小舟に乗って、祖父が笑いながら手を振っていた。
祖父のサミガー大主はカマンタ捕りの名人で、人喰いフカ(鮫)を倒したとの伝説もあった。ウミンチュたちから尊敬されて、恐れられてもいたが、サハチやマシューにとっては優しいお爺だった。
「わーい」と叫びながら、サハチはマシューの手を引いて小舟の方に走った。
三人を乗せた小舟は、静かな海を気持ちよさそうに沖の方へと進んで行った。
|

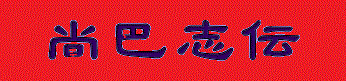
![]()