
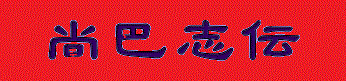
![]()
新宮の十郎
熊野の 淀川のような大きな船ではなく、四、五人乗りの小さな舟で、曲がりくねった川を下った。流れは穏やかだったが、突然、急流になったりして、舟が揺れるのでお酒なんか飲めなかった。それでも天気に恵まれて、あちこちにある滝を見たりして、楽しい舟旅だった。 新宮に着くと新宮孫十が待っていた。鈴木庄司から知らせがあって、 速玉大社の近くにある大きな宿坊に入ると、ササは孫十から新宮の十郎の事を聞いた。孫十の話は、鈴木庄司から聞いた話とほとんど同じだった。十郎が琉球に行ったかどうかはわからないが、当時、熊野水軍が 平泉の藤原氏が滅んだあとは、琉球に行く事もなくなって、鎌倉幕府のために働き、南北朝の争いの時は南朝のために働いた。今は京都の将軍様(足利義持)のために働いているという。そして、十郎の姉の『 かつて熊野を支配していた 長女が湛増に嫁ぐ二年前、父の 晩年になって別当に就任した夫の行範は、別当になってから一年後に亡くなった。夫が亡くなると、丹鶴姫は出家して『 作戦が平家に漏れて、以仁王と頼政は戦死してしまうが、十郎の活躍で各地の源氏が立ち上がった。伊豆に流されていた義朝の嫡男の 壇ノ浦の合戦の時の熊野別当は、鳥居禅尼の娘婿の湛増で、初めは平家の味方をしていたが、鳥居禅尼に説得されて源氏方となり、熊野水軍を率いて壇ノ浦に行き、平家を滅ぼしている。 「丹鶴姫様と十郎様は、新宮が誇れる英雄でございます」と孫十は力を込めて言った。 「丹鶴姫様が住んでおられたお屋敷はなくなってしまいましたが、東仙寺がある山は『丹鶴山』と名付けられて、新宮の者たちは決して、お二人の事を忘れてはおりません」 翌日は新宮に滞在して、熊野別当の屋敷跡地や丹鶴山に登って、十郎と丹鶴姫を忍んだ。 十郎が琉球に行った事は確認できなかったが、十郎の活躍で平家を倒した事はわかった。 妙心寺に寄って、おいしいお茶とお菓子を御馳走になり、神倉山に登った。急な石段を登って行くと、山の中腹に巨大な石があった。まるで、琉球のウタキ(御嶽)のようだった。 「昔は立派な神社がここにもあったんだけど、 ササたちは巨大な石の下にひざまずいてお祈りをした。 「遅いぞ」と神様が言った。 スサノオの声だった。ササは驚いて、体を震わせた。スサノオを祀っている山なので、スサノオがいるのは当然と言えるが、ここに来るまでスサノオの声を聞いていなかったので、スサノオは京都にいると思っていた。まさか、ここにいたなんて思いもしない事だった。 「あたしが連れて来たのよ」とユンヌ姫も一緒にいた。 「色々とお世話になったから恩返しよ。新宮の十郎も一緒よ」 「えっ!」とササはまた驚いた。十郎と会えるなんて考えてもいなかった。 「ユンヌ姫から聞いたぞ」とスサノオが言った。 「琉球に行った男を捜しているそうじゃのう。この地から琉球に行った男は何人もおる。また、琉球からこの地に来た者も何人もおる。お前が探している新宮の十郎とやらを探すのは容易な事ではないと思ったが、丹鶴姫の弟じゃという事で、何とか見つける事ができたんじゃよ」 「丹鶴姫様を知っていたのですか」 「丹鶴姫はよくこの山に来て、源氏再興をお祈りしていたんじゃ。それに琉球に行った弟の事も心配しておったのう。けなげで可愛い 「美人だったのですね?」とササが聞くと、 「勿論、美人じゃが、それだけでなく、賢くて、強い女子じゃったのう。あの頃、熊野別当家を支えていたのは丹鶴姫じゃった。何となく、リュウに似ているな」とスサノオは言った。 「リュウ?」 「お前が高橋殿と呼んでいる女子じゃよ」 「えっ、高橋殿も知っていたのですか」 「あれほどの舞を舞える女子は滅多におらんからのう」 「クミなのか」と誰かが言った。 「違います」とサスカサが答えた。 「その 「新宮の十郎様なのですね」とサスカサが聞いた。 「そうだ。クミと子供たちがどうなったのか教えてくれ」 ササは口を出さず、サスカサに任せる事にした。 サスカサは息子の 「そうか、シンテンが按司になったのか」と十郎は嬉しそうに言った。 「舜天という変わった名前は、十郎様が付けたのですか」 「そうだよ。ここは 「新天だったのですか。今はなまってしまって、シュンティンと呼ばれています」 「そうか、新天の事はちゃんと語り継がれているんだな?」 「はい。初代の浦添按司だと伝わっております。新天のお母さんが、あなたが琉球を去ったあと、何をしていたのか知りたがっています」 「そうか。そうだろうな。戻ると言って琉球を去ったきり戻らなかったからな」 「どうして、戻らなかったのですか」 「今思えば欲が出たんだろうな。憎き平家を倒すのが目的だった。平家を倒したら、あとの事は甥たちに任せて琉球に帰ればよかったんだ」 十郎は久し振りに話を聞いてくれる者を見つけたとみえて、子供の頃からの事を延々と話し始めた。 十郎が生まれた時、父親の 母親の父親は速玉大社の 弁慶は別当家の一族だが庶流なので、別当になる事はできず、先達山伏になって別当家のために働く事になっていた。十郎と同い年だったので、幼い頃から一緒に育っていた。 十六歳の時に、京都で『保元の乱』が起こって父が戦死した。父の戦死を聞いても、十郎には実感がわかなかった。十郎が生まれた翌年、父は京都に行ってしまい、父との思い出はまったくなかった。亡くなる三年前、父は 十郎にとって、実の父よりも、姉の夫である行範が父のような存在だった。行範は厳しい修行を何度もしていて、山伏たちから尊敬されていた。山の中に籠もって修行ばかりしていたので、姉を妻に迎えた時は二十七歳になっていて、姉より十一歳も年上だった。十郎も行範を尊敬して、父親のように慕っていた。 父が亡くなったあと、十郎は行範から父親の事や会った事もない兄たちの事を聞いて、武士として生きようと決心した。 翌年、十郎は弁慶と一緒に熊野水軍の船に乗って、奥州の平泉に行った。武士として生きるのなら、将来のために、平泉の藤原氏とつながりを付けておいた方がいいと行範に言われたのだった。 当時、平泉では豪勢な寺院をいくつも造っていて、 山国育ちの十郎と弁慶にとって、平泉は驚くべき都だった。立派な屋敷が建ち並ぶ大通りを、華やかに着飾った人々が大勢行き交い、まるで、異国に来たようだと思った。平泉を見た十郎は、京都に行こうと決心した。 平泉から帰った十郎は、藤代の鈴木氏の娘を妻に迎えた。その翌年、長兄の義朝に呼ばれて、弁慶と一緒に京都に上った。姉が家臣として二十人の兵を付けてくれた。平泉を見た十郎は京都も似たような所だろうと思っていたが、やはり、新しい都の平泉とは違って、重々しさが感じられた。そして、 義朝は後白河上皇に仕えている武士で、 京都に来て一年余りが建った頃、二条天皇と後白河上皇が争い、そこに 「あいつは武士のくせに、公家になろうとしているんじゃよ」と兄は苦虫を噛み潰したような顔をして言った。 六波羅殿が熊野参詣に出掛けると、義朝の長男、鎌倉源太が東国の兵を率いて京都に入って来た。熊野からも妻の父親が兵を率いてやって来た。そして、戦が始まった。十郎にとって 「どうなったんだ?」と十郎が聞くと、 「負け戦だ」と弁慶は言った。 「再起を図るため、左馬頭殿(義朝)は東国に向かった。お前らは熊野に帰って待機していろ。熊野水軍に動いてもらう事になるかもしれんと言っていた」 十郎と弁慶は八人に減ってしまった家臣たちを連れて新宮に帰った。山伏たちによって、義朝の死が知らされ、妻の父親の戦死も知らされた。義朝の長男の源太も討ち取られたという。源太は十郎と同い年だった。同い年なのに、東国の兵を引き連れて、まるで大将のようだった。羨ましいと思う反面、源太には負けられないと思ったのに死んでしまった。 六波羅殿は残党狩りをしていたが、熊野まで来る事はなかった。姉から、兄たちの 京都の戦の噂も治まって、ほっと安心していた頃、後白河上皇が熊野にやって来た。一緒に六波羅殿もいた。十郎と弁慶は山の中に隠れた。後白河上皇たちが帰ったあと新宮に戻ると、六波羅殿は十郎の事を知っていたと姉に言われた。 身の危険を感じた十郎はその年の冬、熊野水軍の船に乗って琉球に行った。弁慶も誘ったが、山伏の修行をすると言って、一緒には来なかった。 琉球への船旅は楽しかった。海を見ていると嫌な事がすべて忘れられるような気がした。いくつもの島を経由して、着いた琉球は美しい島だった。 熊野水軍は一年おきくらいに琉球に来て、熊野や京都の様子を知らせてくれた。後白河上皇は毎年のように熊野御幸をして、一緒に来る六波羅殿の家来たちは十郎の事を探しているという。六波羅殿は出家して、京都を離れて 琉球に来てから十三年の月日が流れた。琉球に来た熊野水軍から、義兄の行範の死を知らされた。姉の事が思い出され、新宮にいる妻や子の事も思い出された。ちょっと様子を見に行こうと十郎は思った。次に熊野水軍が琉球に来る時には必ず帰るとクミと子供たちに約束して、十郎は新宮に向かった。 弁慶が義朝の息子の義経と一緒に奥州平泉にいると聞いて、十郎は会いに行った。弁慶は義経の 琉球に帰ろうと思っていた矢先に母が亡くなった。その翌年に、福原殿(平清盛)と後白河法皇の対立が深まって、平家の時代に陰りが見え始めた。姉の鳥居禅尼は各地にいる源氏と連絡を取り合っていた。そんな姉を助けようと十郎は山伏姿になって、姉の手紙を各地の源氏のもとへと届けて回った。 「京都に行くにあたって俺は名前を変えたんだ」と十郎はサスカサに言った。 「義盛という名前のままだと危険なので、 その年の十一月、高倉天皇に嫁いだ福原殿の娘(徳子)が男の子を産んで、都はお祭り騒ぎになった。翌年の七月、福原殿の嫡男の小松殿(平重盛)が亡くなった。そして、十一月、福原殿は大軍を率いて京都を攻め、後白河法皇を鳥羽に幽閉してしまう。翌年の四月、福原殿に所領を没収された後白河法皇の皇子、以仁王が『平家討伐』の令旨を発した。 以仁王は八条院の 信濃木曽にいる甥の義仲、 熊野に帰ると熊野でも戦があって、平家方の田辺別当家の湛増が新宮に攻めて来たという。追い払う事はできたが、娘婿の湛増は何としてでも寝返らせなければならないと姉は言った。 新宮で待機していた十郎は、八月に伊豆の頼朝が挙兵したとの知らせを受けると、倅の太郎と次郎を連れて、新宮の兵を率いて出陣した。水軍の船に乗って尾張の津島に上陸した十郎は、スサノオを祀る津島神社に戦勝祈願をして兵を募った。源氏の白旗のもとに兵たちが続々と集まって来た。 五千余騎となった兵を率いた十郎は、頼朝を倒すために東国に向かう平家軍を 「あの時は最高の気分だった。俺も源氏の 戦に負けた十郎は三河まで逃げて態勢を建て直し、鎌倉にいる頼朝のもとへ行った。 「三郎(頼朝)の所は居心地がよくなかった。俺としても甥の家来になるつもりはまったくなかったので、三郎と別れて、木曽の次郎(義仲)と合流したんだ。そして、各地の平家を破って、大軍を率いて京都に入った。平家の奴らはみんな西に逃げてしまった。こんな事が起こるなんて信じられなかった。京都のあちこちに源氏の白旗がなびいていた。世の中が変わった事を実感して、なぜか、涙が溢れて来たんだ。戦死した親父や兄貴に、この眺めを見せてやりたいと思ったよ。俺は 「かしこまりました。お伝えいたします」とサスカサが言った。 「ありがとう。俺もクミの事はずっと気になっていたんだ。そなたはどことなく、クミに似ている。会えてよかったよ」 「一つ、聞いてもよろしいでしょうか」 「ああ。構わんよ」 「あなたが琉球に行った時、大里グスクはどこにありましたか」 「 「その大里グスクの中にウタキはありましたか」 「ウタキ? ああ、クミがお祈りをしていたウタキがあったな。『月の神様』を祀っていると言っていた」 「ありがとうございます。わたしは今、そのグスクで暮らしております。今は 「懐かしいな。グスクへと続く山道を子供たちと一緒に登ったのを思い出したよ」 サスカサがササを見た。 ササはうなづいて、「壇ノ浦で平家が滅ぼされたと聞きましたが、あなたはその戦に参加したのですか」と十郎に聞いた。 「そなたは誰じゃ」と十郎は言った。 「馬天浜のヌルです」とササは答えた。 「おお、そうか」と十郎は納得した。 「俺は参加しなかった。鎌倉の三郎の軍に入りたくなかったんだ。戦で活躍しても、手柄は三郎のものだからな。俺は河内で、拠点となる城を築いていたよ。壇ノ浦の大将は六郎(範頼)と九郎の二人だ。熊野水軍が加わって源氏が勝って、平家は滅んだんだ」 「 「朝盛法師?」 「 「そう言えば、一度会った事がある。 「 「会った事はないが、福原殿(平清盛)が 「二人とも琉球に来ています」 「何だって!」 「最初に理有法師がやって来て、ヌルたちを殺しましたが、朝盛法師がやって来て、舜天と協力して、理有法師を滅ぼしました」 「そうだったのか。源三位入道殿が戦死したあと、朝盛法師の姿を見かけなくなったので、戦死してしまったのだろうと思っていたが、理有法師を追って行ったのか。理有法師は不思議な術を使うと聞いていた。その術を封じていたのが朝盛法師だと源三位入道殿から聞いた事があった。そうか。理有法師が琉球に逃げて、それを追って行ったのか」 「色々と教えていただきありがとうございました」とササはお礼を言った。 「こちらこそ、わざわざ会いに来てくれてありがとう」 ササはスサノオにお礼を言おうとしたが、スサノオもユンヌ姫もどこかに行って、いないようだった。 その後、ササたちは『那智の滝』をお参りして、大雲取りを越え、 |
熊野速玉大社
丹鶴山
神倉山