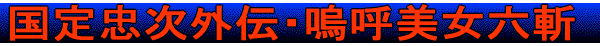

3.浮世絵師、歌川貞利
川べりの眺めのいい所にあると思っていたのに、貞利の家は川から大分離れた 門は開いていた。声を掛けたが返事はない。まだ新しい家は戸締まりがしてあり、貞利は留守だった。伊三郎と一緒に中瀬に行っているに違いない。 久次郎も中瀬に向かった。 渡し場に行く前に、 「若旦那が何か」と小声で聞いて、久次郎を店の隅に誘った。 「なに、ちょっと聞きてえ事があるだけだ」 「そうですか。さっきも島村の親分さんが見えましたが‥‥‥」 「それなら知ってると思うが、境の娘が行方知れずになった。その事で話を聞きてえんだ。俺は島村一家とは別口でな、 「そうですか。それで、どちらさんで」 久次郎が 「何だと」と久次郎はカッとなって怒鳴ったが、人足たちに睨まれ、悔しいながらも引き下がった。こんな所で騒ぎを起こしたら、伊三郎に何をされるかわからない。 柳屋から通りに出ると、さっき、貞利の家の場所を教えてくれた茶屋の娘がこっちを見ていた。久次郎は娘に近づいて、伊三郎がどこに行ったかを聞いた。娘はニコッと笑って、小料理屋『鶴屋』に入って行ったと教えてくれた。ついでに徳次郎の事を聞くと、「今頃は剣術道場じゃないかしら」と言う。 「道場てえなア 「ええ。でも、もしかしたら、鶴屋さんにいるかもしれない。あそこの息子さんと仲がいいから。徳次さんがどうかしたんですか」 「なに、ちょっと話があるだけだ」 「境の小町がいなくなったんですって」 「ほう、もう知ってんのか」 「さっき、島村の親分さんに見なかったかって聞かれたんです」 「それで、見たのか」 「よく覚えてないんです。中瀬に行ったんなら通ったと思うんだけど、一々、女の人なんて見てないもの」 「男なら見てんのか」 「いい男ならね。あんたが『柳屋』さんに入ってったのも見てたわ」 「そいつアありがてえ」と久次郎は笑った。 改めて、娘を見ると年の頃は十七、八、色は少々黒いが目鼻立ちのはっきりした可愛い娘だった。 「あたし、糸って言うの。去年、徳次さんといい仲だったんだけど、もう、別れたわ」 「どうして、別れたんだ」 「その小町のせいよ。お常の錦絵をいつも持ち歩いてニヤニヤしてんの。馬鹿みたい。何でも中途半端でいい加減で、くだらない男よ」 お糸は徳次郎の悪口をまくし立てた。 「徳次とお常はいい仲だったのか」 「振られたんじゃないの。いい気味よ。振られた後、あたしとよりを戻そうとやって来たけど追い返してやったわ。もしかしたら、あいつがお常をさらったんじゃないの。自分の思い通りにならなかったんで、中瀬に行く途中をさらったに違いないわ。島村の親分さんに言って捕まえた方がいいわ」 「そんな事をしそうな奴なのか」 「一人じゃ何もできないけどね。仲間とつるんだら、その位の事はやりそうね。でも、島村の親分さんが出て来たから、今頃、真っ青になって震えてんじゃない」 「ヤットウ(剣術)の腕はどうなんだ」 「大した事ないわよ。お金持ちだから道場の方でも通わせてるんじゃないの」 「そうか。色々とすまなかったな。それとなく、奴の事を見ていてくれ」 久次郎はお糸に 「ついでに言っとくが、俺ア島村一家じゃねえ。百々一家の お糸の態度が変わるかと思ったが変わらなかった。ニコニコしながら、「また、来てくださいね」と頭を下げた。 鶴屋を覗くと伊三郎たちの姿は見当たらなかった。二階にいるのかと聞いてみたが、やはりいない。しかし、徳次郎の方はいた。通りに面した座敷で仲間とつるんで、つまらなそうに酒を飲んでいた。 久次郎が顔を出すと、ニヤニヤしながら、「兄貴までお出ましですか」と慣れ慣れしく言った。 「島村の親分にしぼられたと見えるな」と久次郎は笑って、徳次郎たちの顔を見回した。 「そうでもねえけど、俺たちアお常の事には関係ねえですよ」と徳次郎らしい男が首の後ろを掻きながら言った。「お常がいなくなった日、俺たちア伊勢屋の賭場にいたんです。ちっとばかし勝たしてもらったんで、そのまま、木崎に繰り出したってえわけです。 「そういやア、おめえらの 「これを機に覚えておいてくだせえ」 徳次郎は仲間たちを紹介した。皆、剣術道場に通っている仲間で、酒屋の次男の竹次郎、船大工の三男の鉄五郎、この小料理屋の次男の耕作と、どら息子ばかりだった。年は皆、十九だという。 「兄貴、お常はどこ行っちまったんです」 「そいつがわかりゃア苦労はねえ。おめえたちゃア本当に知らねえんだな」 「そんなの知らねえや。知ってりゃアこんなとこにくすぶってなんかいねえ。あのアマ、錦絵になったからって、いい気になりやがって、俺が何を言ったって見向きもしねえ。まったく、腹の立つ女だ」 「てめえらは親の金ばっか当てにするから、相手にされねんだ。汗水垂らして働いてから、そういう事を言え、馬鹿野郎」 「そんな事言ったってよお、俺たちゃ次男坊、三男坊は跡を継げねえんだ。今のうちに遊ばなくっちゃア兄貴にみんないいとこを取られちまうぜ」 「そんな事を考えてるから女に相手にされねんだ。自分の足で立つ事をまず覚えろ」 どら息子たちの相手をしている場合ではないので、久次郎は徳次郎たちと別れて、渡し場に向かった。 山の雪解け水で増水した利根川は悠々と流れていた。三月から四月にかけては水量も豊富で気候も安定しているので、江戸と上州を結ぶ船の出入りは多かった。 渡し舟の 「お常を知ってたのか」 「知らねえけどよ、あんな 「お常は 「かぶってたけど別嬪だってこたアわからア。顔を背けるようにしてたが、いい女だった」 「お常は間違えなく、向こうに行ったんだな」 「そいつア確かだ。向こうに渡ったんが昼頃だ。夕方までには戻るだんべえと、わしゃアあっちでずっと待ってたんだが戻っちゃア来なかった。次の日も今日も、まだ戻って来ねえ。もっとも、島村にも渡しがあるから、そっちから 「そん時、舟に乗せたんは、お常一人だけだったのか」 「そうさ。普通は四、五人集まってから渡すんだが、急いでるからお願いって言うんでな。別嬪からそう頼まれちゃア、いやとは言えねえわ」 久次郎はとにかく利根川を渡って中瀬に上がった。逢い引きに使いそうな茶屋や小料理屋、 「おい、てめえは百々一家の野郎だな。こんなとこで何してやがんでえ。お常捜しなら、てめえらの出る幕じゃねえ。さっさと帰りやがれ。てめえ、信三の兄貴を疑ってるならお 久次郎は口答えをせずに、その場を離れた。 お常が中瀬に来たのはしんさんと会うためだったとはいえ、今もしんさんと一緒だとは限らない。しんさんと別れた後、何者かにさらわれたとも考えられる。この辺りでも、お常が錦絵に描かれた境小町だというのは有名だ。お常に言い寄ったが相手にされなかった男が、一人きりでいるお常を見つけて、さらったとも考えられた。 久次郎は荷揚げ人足や船引き人足たちの溜まり場にも行き、お常の錦絵を見せながら聞いてみたが、お常を見た者はいなかった。 日の暮れる頃、平塚に戻り、もう一度、貞利の家に行くと貞利は帰っていた。 「おめえさんはさっき、中瀬で会った‥‥‥」 「ええ、百々一家の久次郎です」 「そうだったな。それで、お常は見つかりましたか」 久次郎は首を振った。 「どこに行っちまったんだろうな。あん時、俺が一緒に行きゃア、こんな事にはならなかったのに‥‥‥まあ、どうぞ、お上がりください」 「いえ、ここで。すぐ、帰りますので」 貞利は筆を置くと縁側の方にやって来て、「大分、陽気がよくなりましたな」と桑畑を眺めた。間近に見る貞利は目鼻立ちのはっきりした役者のような顔をしていて、娘たちが騒ぐのもわかるような気がした。貞利が縁側に座り込んだので、久次郎も腰を下ろした。 「ところで、中瀬で一緒にいた人はどなたなんですか」と久次郎は貞利に聞いた。 「あいつは幼なじみの新八ですよ。島村の親分の子分だ」 「あいつが新八でしたか。新八と一緒に捜してたってえ事は、新八もお常の居場所は知らねえってえ事ですね」 「はあ」と言って貞利は久次郎の顔を見た。「奴が知ってるわけねえだろう。おめえさんは新八を疑ってるのか」 「いえ、中瀬のしんさんてえのは新八じゃねえかって聞いたもんですから」 「何だって。誰だ、そんな事を言ったのは」 「お菊とお海です」 「ああ、あの二人か」貞利は小さくうなづき、桑畑の方に目を移した。「ここで何度か、新八に会ったから勝手に想像したんだろう。確かに、新八はしんさんには違えねえけど、お常といい仲になってたなんて考えられねえな」 「二人が言うには、新八にはかみさんがいるから、世間に内緒で中瀬で密会してたとか」 「中瀬で密会してたから中瀬のしんさんか。うめえ話だが、お常と新八がねえ」 貞利はまさかと言うように首をひねった。 「お常は中瀬に行く 「いや、ただ、中瀬に用があると言っただけだ。何となく浮き浮きはしていたが」 「そん時、先生も中瀬に行く用があったんですよね」 「ああ、今、島村の親分に頼まれて、この辺りの美人を描いてんだ。それで、中瀬の 「へえ、今度はこの辺りの美人を 「『利根川八景』と名付けてな、八人を描こうと思ってる」 「利根川八景ですか。差し支えなければ、その八人の美人を教えてくれませんか」 「ああ、構わねえよ」 貞利が下絵を見せてくれると言うので、久次郎は仕事場に上がらせてもらった。描き損じの絵が散らかっていたが、思っていたよりも部屋の中は片付いていた。 「まず、島村の親分の娘のおいっちゃん、島村の林蔵さんのお妾、お清さん、島村の舟頭の娘、お波、平塚の留五郎さんのお妾、お筆さん、中島の長平さんの娘、お伊代ちゃん、中島の船問屋の娘、おみの、藤十さんのお妾、お茂さん、それに、こいつはまだ途中だが、平塚の 貞利は次々に下絵を見せてくれた。 「へえ、島村の親分にこんな可愛い娘がいたんですか」 振り袖を着て、花見をしている娘が嬉しそうに笑っている。遠くに 「まだ十四だけどな、あと一、二年もしたら、男どもが放ってはおかねえだろう。ただし、おっかねえ親父の目が光ってるから、近づく事さえ難しいだろうがね」 「そうだんべなア」と久次郎は苦笑しながらうなづいた。「しかし、うめえもんですねえ。娘たちがキャーキャー騒ぐんも無理アねえや。みんな、こういう風に先生に描いてもらいてえんでしょうねえ」 「描いてくれと言やア、すぐに描いてやるよ」と貞利は何でもない事のように言ってから、「錦絵にするのはちょっと難しいけどな」と付け足した。 「島村の親分に関係のある女が五人もいるんですか」久次郎は八枚の絵を眺めながら聞いた。 「しょうがねえんだ。江戸と違って、この辺りの 「成程、そうだったんですか」 「俺が最初に出した『当世木崎美人』は木崎の親分が助けてくれた。『美人 「へえ、境宿もそうだったんですか」 「いや、境は違った。島村の親分はあまり口出ししねえで、宿場の者たちに任せたようだ。 貞利は八枚の下絵を片付けた。 「お常、お政、おたかの三人が選ばれる前、大黒屋の娘も候補に上がってたんだ。俺は親分が大黒屋のおとしを選ぶに違えねえと思ってたんだがね」 「境の有力者たちの機嫌をとるため、余計な口出しはしなかったんでしょう」 「そうかもしれねえな」 「境宿はずっと、百々一家が仕切ってました。それを島村の親分が強引に奪ってしまったんです。島村の親分のやり方に反発を持ってる者も結構いるんですよ。特に桃中の旦那は百々一家の先代の親分と親しいんです。それで、機嫌を取るつもりで何も言わなかったんだんべえ」 「俺も江戸に出る前の島村の親分を知ってるが、確かに、利根川筋は仕切ってたが、境は百々一家だった。帰って来て、境もほとんどが島村の親分の縄張りになったと聞いて、ほんとに驚いたよ」 「島村の親分はみんなからいい親分さんだと言われていい気になってるけど、裏じゃア汚え事をやってんですよ」 描きかけの下絵を眺めていた貞利は顔を上げて、久次郎を見たが何も言わなかった。 「まあ、先生にこんな 「ああ、俺が荷物をまとめてるうちに、さっさと行っちまったんだ。渡し場に行った時はもう、お常の姿は見当たらなかった」 「お常は確かに利根川を渡った。舟頭に見られてます。そこまではわかるが、そこから先はまったくわからねえ」 「俺たちも昼からずっと捜し回ったが、お常を見たという者は見つからなかった。今まで、新八の事を疑ってもみなかったが、お菊たちが言うように、お常が新八と密かに会ってたってえのも考えられん事もねえな」 「さっき、新八が先生と一緒にいたのは、島村の親分に命じられたんですか」 「親分が用があるからと言って、新八を呼び出して命じたんだが」 「そうですか‥‥‥さっきの新八の態度から、お常の事を知っていながら、知らん顔して捜し回ってるとは思えませんでしたか」 「そう言われてもわからねえな」 「お常がここに来た時、新八とお常が親しそうにしてる所を見た事はありませんか」 貞利は部屋の中を見回しながら、しばらく考えていたが、久次郎を見ると、「そんな事はなかったと思うが、よくわからんな」と言った。「お常はいつも、お菊、お海の三人でここに来た。その時、たまたま、新八がいる時もあるし、いねえ時もある。二人が出会ったのはここに違えねえだろうが、ここでは何も起こらなかった。新八を疑いたくはねえが、明日も奴と一緒に捜す事になってるんで、それとなく聞いてみよう」 「お願えします。しかし、新八がお常と中瀬で密かに会ってたとしたら、絶対に知らねえと言い張ると思いますよ。今まで、誰にもわからねえように付き合ってたんですから」 「そうだな‥‥‥しかし、今日、新八と一緒に密会に使いそうな場所を回ってみたが、新八が利用してるような所はなかったぜ」 「口止めしてるに違えありません。本人を前にしてしゃべるはずはありませんから」 「それもそうだな」 「それに、茶屋とか旅籠屋は危険なので、どこかに隠れ家を持ってるのかもしれません」 「成程、それもありえる。しかし、新八がお常と密かに隠れ家で会ってたにしろ、うちに帰らねえってえのはおかしいじゃねえか」 「考えられるのは二つです。一つは何かの理由があって、新八がお常をどこかに隠してる。もう一つは新八と別れた後、何者かに襲われ、どこかに閉じ込められてるか、最悪の場合、殺されちまったのかもしれません」 「そんな事は考えたくはねえが‥‥‥」と言って、貞利は首を振った。 その後、久次郎は貞利に誘われて、一杯やりながら世間話をした。会う前は江戸帰りの絵師なんて、生意気で取っ付きにくい変わり者だろうと思っていたが、貞利はそうでもなかった。偉ぶった所は少しもなく、自分の腕に自惚れてもいない。自分の絵はまだまだだ。本物の女を描くのは実に難しいと言っていた。 ほろ酔い気分の久次郎は貞利から
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧