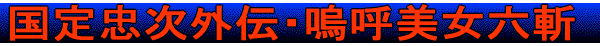

9.嗚呼美女六斬
お常のバラバラ事件の後、久次郎は暇さえあれば、お政と会っていた。そして、時々、お菊やお海たちと一緒に平塚の貞利の家に遊びに出掛けた。 貞利は忙しかった。『利根川八景』の仕事が終わると玉村宿に行って 美人絵を描くのと違って、艶本を作るのはかなり大変なようだった。当時の艶本は 『利根川八景』に描かれた お政は、貞利とお万ができているに違いないと疑った。お万に聞いてみると、「先生の前で何度も裸になってんのにさ、先生は一度も、あたしを抱いてくれないんだよ」と色っぽい仕草でぼやいた。 絵師として女の裸なんか見飽きているのだろうかと久次郎は不思議に思った。お万程の魅力があれば、男なら誰だって抱きたくなるのが普通だ。貞利に聞くと、絵に熱中している時はその気にはならないという。 「博奕打ちが博奕に熱中してる時、女の事なんか 艶本には絵の後に 艶本を売り出す事は幕府に禁止されていて、表立って売り出す事はできなかった。しかし、博奕と同じように、禁止されているからといってやめるわけにはいかない。陰に隠れて販売されていた。 江戸で有名な浮世絵師はすべてと言っていい程、皆、裏に隠れて艶本を描いている。美人絵で有名な喜多川 貞利の師匠、 貞利は寝る間も惜しんで艶本作りに取り組んでいた。久次郎は円蔵から言われたように、 貞利は艶本作りに夢中になり、久次郎はお政に夢中になっていた。民五郎も 梅雨も上がった六月の半ば、お政に会いに行こうとした久次郎は、やっとの思いで歩いている傷だらけの文蔵と民五郎に出会った。驚いて駈け寄ると、お政の事も忘れて、二人を連れて帰った。 その日、文蔵と民五郎は 「彦六の野郎は許せねえ、彦六をたたっ殺して、伊三郎の奴も殺っちまえ」と文蔵は騒いだが、円蔵に止められた。 世良田には各地の親分が賭場の準備のために子分たちを送っていた。百々一家の代貸、文蔵が彦六にやられた事はみんなに見られている。親分の忠次としても、このまま放っておくわけには行かなかった。忠次が伊三郎に対して何もしなかったら笑い物になってしまう。 円蔵が止めても忠次はこの機に、絶対に伊三郎を殺すと言い張った。忠次に説得されて、円蔵もようやく覚悟を決めた。 忠次と円蔵はじっくりと作戦を練り、密かに伊三郎暗殺計画を進めて行った。世良田の祇園祭りに参加しないと伊三郎に怪しまれて警戒されるので、忠次は彦六たちにペコペコ頭を下げながら境内の外れに賭場を開いた。 その後、伊三郎が忠次を警戒していない事を知ると、半月後の七月二日、境宿に市が立つ日、忠次は伊三郎の暗殺を決行した。 久次郎も伊三郎殺しに加わりたかったが選ばれなかった。伊三郎を殺した後、子分たちが百々一家に押しかけて来るに違いないので、円蔵と一緒に留守を守ってくれと言われた。 その日、伊三郎は昼過ぎに境宿にやって来た。供回りはいつもと変わらず、用心棒の永井兵庫、子分の中瀬の信三、荷物持ちの三下奴が二人だけ。伊三郎は その夜、世良田の長楽寺で日待ちの賭場が開かれる事になっていた。世良田の顔役たちが集まる賭場に伊三郎は必ず 伊三郎が島屋に入ったのを見届けると忠次たちは先回りをして、平塚道から世良田へと向かう道の途中にある熊野 伊三郎を殺した忠次たちは百々村に帰る事なく、そのまま、国外へと旅立って行った。 久次郎は円蔵らと共に百々村で島村一家の襲撃に備えて守りを固めていた。ところが、島村一家の子分たちは、いつになっても攻めては来なかった。伊三郎が殺されると跡目争いが始まって、百々一家を攻める所ではなく、島村一家はバラバラになってしまった。 島村一家は本家と 伊三郎が一家を本家と分家に分けたのは、もう十五年も前の事で、伊三郎の知らない所で本家と分家の対立が続いていた。目付となって代貸のもとに入っている者たちは伊三郎の威を笠に着て、言いたい放題の事を言い、代貸の悪口を告げ口する。代貸たちは生意気な目付役を何とかしたいと思うが、伊三郎を恐れて何もできない。しかし、伊三郎は目付役の言う事をすべて信じる事なく、代貸たちの言い分もしっかりと聞いたので、一家が分裂する事はなかった。 本家で伊三郎に次ぐ地位にいたのが小島の彦六だった。林蔵の弟分だったが、林蔵が分家になってからは伊三郎の代理を務める程の権力を手にしていた。二年前、助次郎と共に百々一家を裏切って伊三郎の代貸となった 伊三郎が忠次に殺されたとの知らせが届くと、境宿の横町に住んでいた彦六は直ちに島村の本家に向かった。すぐに跡目を継いで、百々一家を倒すつもりでいた。ところが、彦六の跡目相続はうまく行かなかった。かつての一の子分だった林蔵が跡目を継ぐのは自分だと言い出し、代貸たちの意見を聞こうじゃねえかと言い出した。 代貸たちの意見を聞けば、自分が負けると思った彦六は代貸たちのもとにいる目付役を本家に呼び戻し、林蔵を倒す準備を始めた。その中に彦六の弟分で平塚の代貸になっていた留五郎もいた。留五郎は彦六に跡目を継がせようと子分を引き連れて島村にやって来た。彦六が留五郎らと林蔵を倒す作戦を練っている時、平塚で騒ぎが起こった。留五郎の留守を狙って、中島の長平が平塚を乗っ取ってしまった。今まで、伊三郎に押さえられていた代貸たちから見れば、島村一家の事より、伊三郎がいなくなった今こそ、縄張りを広げる絶好の機会だと行動に移したのだった。 次の日は七日、境宿の上町に市の立つ日だった。百々一家としては伊三郎の子分が攻めて来るに違いないとずっと待ち構えていたのに、一向に来る気配はない。敵の情報を集め、跡目争いを始めたらしい事はわかったが、気を許すわけにはいかなかった。その日、充分に警戒しながら伊勢屋の賭場を開いた。大黒屋の彦六も桐屋の助次郎も何事もなかったように賭場を開き、子分同士の争い事もなく、不気味な静けさの中、その日は終わった。 江戸からの船が出入りして、金持ちの河岸問屋が多く、博奕好きな船頭も多い平塚の縄張りは何としてでも取り戻さなくてはならない。彦六と留五郎は次の日の夜明け前、平塚を攻めて、長平を殺し、中島河岸も手に入れた。うまく行ったと喜んだのもつかの間、二人の留守に林蔵が本家を乗っ取った。この時、怪我をして寝込んでいた用心棒の永井兵庫と中瀬の信三は林蔵の子分に殺された。 利根川を挟んで林蔵と彦六の睨み合いが続いた。十日の夜、長平を殺した留五郎は一人殺しても二人殺しても同じだと、密かに島村に渡って、林蔵を暗殺した。そして、留五郎も林蔵の子分に殺された。林蔵の跡目はすぐに川端の大次郎が継ぎ、彦六との睨み合いは続いた。 そんな時、伊三郎の代貸の一人、世良田の弥七が関東取締出役が来るので、内輪もめはやめろと言って来た。彦六も大次郎も弥七の言う事を聞いて、とりあえずは和解した。 次の日、関東取締出役の吉田左五郎がやって来た。弥七がうまく取り入って、島村一家の内部抗争は表沙汰にされなかった。左五郎は伊三郎殺しを調べ、伊三郎を殺した忠次と文蔵の二人が手配された。しかし、この頃の忠次はまだ無名に等しかった。 左五郎は百々一家にも現れ、事情を聞いた。円蔵の話から百々一家の縄張りが境宿の一部に過ぎない事を知ると、無茶な事をやったもんだなと呆れ、厳しく、忠次の詮索をしようとはしなかった。かえって、上州一の大親分といわれた伊三郎が消え、島村一家が分裂した事は左五郎から見れば喜ばしい事だった。 調査を終えた左五郎が玉村方面に行ってしまうと、彦六と大次郎の抗争は再燃した。まず、手初めに彦六の弟分、尾島の貞次が世良田の弥七を殺して旅に出た。弥七には野心はなかったが、彦六は弥七が跡目を狙っていると考えて殺してしまったのだった。弥七の一の子分だった 助けを求めて来た者を追い返すわけにも行かず、円蔵は子分を引き連れて世良田に向かった。伊三郎を殺した百々一家と手を結んだ茂吉の行動に腹を立てた彦六は、裏切り者を倒せと抗争外にいた中瀬の藤十、前島の秀次に連絡を取った。ところが、伊三郎の威を笠に着て威張っていた彦六を快く思っていない二人は、島村一家から抜けて独立すると言って来た。木島の助次郎と柴の啓蔵も彦六に反感を持っていたので協力を拒んで独立した。 孤立した彦六は境宿から手を引き、独立した助次郎も百々一家に対抗する事はできず、境宿から出て木島村に帰って行った。 七月二十二日、百々一家は境宿を取り戻して、伊勢屋、桐屋、大黒屋の三ケ所で賭場を開いた。久次郎は大黒屋の 伊三郎を殺した事によって島村一家は分裂し、島村は大次郎、平塚河岸と中島河岸は彦六、世良田村は茂吉、中瀬河岸は藤十、前島河岸は秀次、柴宿は啓蔵、木島村は助次郎と小さな一家がいくつもできた。それらの一家に比べれば、境宿を手に入れた百々一家は一番勢力のある一家にのし上がったと言えた。 次の市日、二十七日は境宿の諏訪明神の祭礼、八坂祭りだった。百々一家は町人たちと協力して盛大な祭りを行ない、境宿の人たちと一体化する事に成功した。 境宿がすべて百々一家の縄張りとなり、大手を振って下町に行ける身分となった久次郎だったが、親分たちが留守のため、以前よりずっと忙しくなり、なかなか、お政と会う時間が取れなかった。 七月の末、ようやく、休みを取った久次郎は久し振りにお政を連れて、貞利の家に遊びに行った。貞利の家には女がいた。伊三郎の 久次郎が忠次の子分だと知ると恐ろしい顔をして 久次郎は甲州(山梨県)か総州(千葉県)だと答えた。実際は信州(長野県)に行ったのだが、勿論、その事は隠した。 「ふん、忠次の妾にお町ってえのがいるらしいね。いい女だってえじゃないか。忠次の代わりにそいつを殺してやろうか。お常みたいにバラバラにしてやろうか。忠次が帰って来て、どんな顔をするか見ものだねえ」 「何だと、おめえ、 「 「そんな事アさせねえ」 「あたしゃやるよ。忠次が帰って来たら、絶対に殺してやる。でも、その前に、お町を殺すんだ。せいぜい気を付けんだね」 「そんな事ア絶対にさせねえ。姐さんの側に近づいてみろ。女だって許しゃアしねえ。たたっ斬ってやる」 「ふん、やれるもんならやってみな。まず、手初めに、その女を殺ってやろうか」 お北はニヤニヤしながら、お政を見た。 貞利は仕事に熱中していて仕事場から出て来る気配はない。久次郎はお政を連れて、貞利の家から離れた。 百々村に帰ると久次郎はお北の事を円蔵に知らせて、 八月の半ば、久次郎とお政が貞利を訪ねるとお北の姿はなかった。仇討ちをすると騒いでいたのを貞利が説得して尾島村にある実家に帰らせたという。一応、納得して帰って行ったが、まだ、忠次を恨んでいるので気を付けた方がいいだろうとの事だった。 九月半ば、尾張屋のお海が 伊三郎がいなくなってから百々一家の株は上がり、子分になりたいという若者が何人もやって来た。やって来た者をすべて子分にするわけにもいかず、そいつらの話を聞いて、円蔵に取り次ぐのは久次郎の仕事だった。 以前は伊三郎に遠慮して、 円蔵を別格として、久次郎は代貸の国定村の清五郎と 久次郎とお政が別れた頃、二年半前に旅に出た平塚の助八が帰って来て、百々一家に草鞋を脱いだ。助八は伊三郎の代貸だったが、中島の代貸、 伊三郎がいなくなり、平塚を取り戻したいので助けてくれという。円蔵は引き受けて、彦六を倒す計画を練った。平塚にいる彦六の行動を充分に調べあげ、十一月半ばに助八は平塚を襲撃した。 襲撃は成功し、彦六は利根川を越えて中瀬の藤十を頼って逃げて行った。助八は平塚だけでなく、昔からの念願だった中島までも手に入れ大喜びだった。見返りとして、百々一家は平塚の賭場のカスリを手に入れた。久次郎も平塚の襲撃に加わったが、誰も殺す事なく、急ぎ旅に出なくて済んだ。 年の暮れ、百々一家に女の渡世人がやって来て草鞋を脱いだ。水沢村のお 円蔵の妻であり、一流の壷振りでもある弁天のおりんの目にかなって、お紺は子分になる事を許された。百々一家には以前から伊勢屋の賭場で壷を振っていた 久次郎は円蔵に頼まれ、浮世絵師、貞利を呼んで、三人の絵を描かせた。伊三郎がいなくなったので、貞利も誰にも遠慮せずに百々一家に出入りするようになっていた。また、貞利としても伊三郎に代わる後援者として百々一家を選んでいた。 久次郎は突然やって来たお紺に一目惚れをした。壷を振っている時の張り詰めた緊張感と普段の素顔の差があまりにも大きく、時々見せる笑顔が何とも言えず可愛かった。久次郎はお紺をものにしようと必死になって口説いていた。 年が明け、 境宿の市は七日の上町の市から始まる。その日は その日、貞利が去年描いた美人絵『利根川八景』と『玉村美人八景』も売り出された。 境宿には 『玉村美人八景』の方は玉村に遊びに行こうと思っている男たちが買い、 『嗚呼美女六斬』は売り出される前から境の旦那衆の話題になり、予約が殺到して、その日のうちにほとんどが売れてしまうという 久次郎は新年の挨拶に来た貞利から直々に、その艶本をもらった。半紙本三冊で、上、中、下巻に分かれ、表紙は艶本とは思えない程、上品に仕上がっていた。 上巻の表紙をめくると、貞利自筆の序文があり、次におさね(お常)の大首絵があった。おさねが楽しそうに笑っている。その笑顔を見ているとお常が殺された事が嘘のように思える程、生き生きとしていた。 次の絵はおさねの家が描かれてあった。 次におさねが夕涼みをしている所が描かれてあった。 次の絵は前図の続きで、暑さに耐えられなくなったおさねが庭で 場面は変わって、桑畑の中で若者に抱かれているおさねを馬吉が覗いている。おさねは恥ずかしそうに 祭りの夜、空き地の草むらの中で、蓑吉に後ろから抱かれているおさね。蓑吉は人の目を気にして振り返っている。物陰から二人を覗いている後ろ姿の馬吉。おさねの髪から 次はどこかの 次には中瀬の土手で一人待つ頭巾をかぶったおさねの姿があった。手前の利根川には小舟が浮かび、土手の桜が満開に咲き誇っている。土手下にある例の掘っ建て小屋からおさねを見ている馬吉。ここで初めて馬吉の顔が明かされる。馬吉は気味の悪い薄ら笑いを浮かべながら、おさねをじっと見つめている。 最後におさねの大つび絵(女性器を拡大した図)で一冊目の絵は終わった。久次郎は貞利に裸を描かせていたお万を思い出した。このつびはお万のものかもしれないと思った。 中巻はおさねが苦しんでいる大首絵で始まった。苦しみながらも、その顔は美しい。 次の絵は利根川の河原にポツンと立つ掘っ建て小屋の絵で、人物は描かれていない。利根川に帆掛け船が通り、桜が満開に咲いている。何の変哲もない静かな風景画だった。 次をめくると一転して 次は裸にされたおさねを馬吉が縛っている場面。掘っ建て小屋の中ではなく、平塚の空き家らしい。両手を広げるように柱に縛られたおさねは猿轡をはめられ涙を流しながら、足を縛られまいともがいている。馬吉はニヤニヤしながら、おさねの足を押さえて足首を縛ろうとしている。おさねの髪は乱れ、貞利が見つけたという その後、大の字に縛られたおさねを 逆さ吊りにされたおさねの姿は久次郎とお政が目にしたお万の姿だった。その顔は苦しみながらも、くすぐられて笑いながら涙を流している、何とも表現できない顔だった。よくこんな顔が描けるものだと感心せずにはいられなかった。 下巻の大首絵はお常の死に顔のようだ。髪は乱れて、顔は歪み、目が飛び出し、歯を剥き出し、見るからに気味の悪い絵だった。そして、傷だらけになって死んでいるおさねを嬉しそうに撫でている馬吉の姿があり、おさねの両足を切断し、切った左足を持ちながら死んだおさねを犯している血だらけの馬吉が描かれてある。ここまで来ると、とても見てはいられない程、残酷な絵だ。 次には死体をバラバラにした馬吉が苦痛に歪んでいるおさねの生首を抱いて笑っている絵がある。ようやく、残酷な場面が終わり、早朝、馬吉がバラバラにしたおさねの死体を荷車に乗せて走っている場面となった。 場面は一転し、木崎宿の女郎を抱いている馬吉。下巻の絵で、この場面だけは艶本らし正常な交わりだった。そこに十手を持って踏み込んで来た卯三郎(伊三郎)の顔が 最後の大つび絵は死んだおさねの血だらけのつびだった。 上巻から下巻まで、絵には簡単な会話が書き込まれ、絵の後に事件の経過を詳しく説明した文章が書かれてある。馬吉以外の登場人物の名が仮名になっている他は、ほとんど事実に即して書いてあった。 上巻は何とか楽しく見られるが、中巻、下巻になると気分が悪くなる程、残酷な場面の連続だった。貞利がこれを描いていた時、伊三郎はまだ生きていた。伊三郎の趣味が多分に反映しているように思われる。これでもか、これでもかと残酷な場面を連続させたのは、 貞利としてはもっと明るく楽しい艶本を描きたかったのだろうが、これがまた評判になれば、来年はもっとどぎつい物を要求される。伊三郎はいなくなってしまったが、貞利が残酷な絵から抜け出す事は難しいように思えた。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧