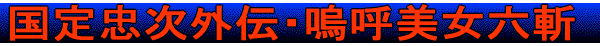

9.翁屋のお通
一雨来そうな空模様だったが、雲の間から晴れ間が顔を出し、日差しを浴びて利根川が輝いていた。 利根川を渡って平塚に着いた久次郎は土手の上を歩きながら孝吉の家を目指した。 謎の女がお北ではなかったとはいえ、孝吉の疑いが晴れた訳ではない。お関に振られて、無理やりものにし、貞利の艶本を真似して死体をバラバラにしたのかもしれない。ただ、姉のお北の他に、殺しの手助けをするような女がいるかどうかだった。お奈々がお関殺しを手伝うはずはないし、昨日はずっと幸次が守っていたのでできる訳がなかった。 土手から孝吉の家を覗くと二階は閉め切ってあるが一階に人影が見えた。土手を降りて、庭を横切ろうとしたら、桶松がどこからか出て来た。 「おめえ、こんなとこで何してんだ」 「お通がいるんですよ」と桶松は孝吉の家を 「お通がいる? おめえが連れて来たんか」 「そうじゃありませんよ。昼過ぎに孝吉が店にやって来て、お通とお関の話を始めたんです。そのうちに、人情本の話になって、孝吉がうちにそんな本ならいくらでもある。読みてえなら、やるぞってな事になって、お通は人情本が好きで、暇さえありゃア、 「人情本だと? あの野郎、今度は、お通をものにするつもりでいやがる。おめえは何で、こんなとこで 「お通にすぐ来るから待っててって言われて」 「馬鹿野郎が。お通がやられちまうぞ」 「俺だって一緒に行きたかったんですけど、孝吉が 「お通が 「まだ、ほんの 久次郎は桶松を連れて縁側から声を掛けた。 茶の間から孝吉が顔を出し、久次郎がいるのを見て、ちょっと変な顔をした。お通は何冊も積み重ねた本を前にして頭を下げた。 「兄貴、お通なら 「いや、お通の事で来たんじゃねえ」と久次郎は縁側に腰を下ろした。「お関の事で深谷に行って来た 「俺はお関の事なんか何も知らねえぜ」 「そいつはわかってるが、何としてでも下手人を捕まえなけりゃアならねえ。下手人はこの近所に出没してるんだ。おめえ、何か心当たりはねえか。ほんの 「心当たりったってな、その女を見たわけでもねえし‥‥‥」 「下手人はおめえの姉ちゃんを下手人に仕立てあげようとしたんかもしれねえんだぜ」 「そんな事言ったってな‥‥‥俺だって、角次と一緒に色々考えてみたんだが、 「ああ、すぐに帰って来るだんべえ。奴がいなくてよかったぜ。バラバラになったお関の姿を見たら、あいつは何をするかわからねえ」 「まったくだ。この間も、えれえ 久次郎は孝吉からお通に視線を移した。お通は七小町の中で一番年下の十六歳だった。京人形のような可愛い顔をして、熱心に人情本を見ていた。 「おめえは何か知らねえか」と聞くと、お通は顔を上げて首を振った。 「読みてえ本があったら、持ってっていいぜ」と孝吉が言った。 お通は嬉しそうに六冊を手に取った。「これ、いいですか」 「それだけでいいのか」 「はい。読んだら、また、お借りします」 「おう。いつでも来な」 桶松にお通を送らせると、久次郎は上がり込んで本の山を眺めた。 「 「ああ。姉ちゃんはこんなのを読んじゃア、江戸に行きてえって言っていた。今頃は深川辺りで芸者にでもなったんかもしれねえ」 「かもしんねえな‥‥‥こいつで釣るたア、おめえもやるじゃねえか。お通はなかなか堅え娘だ。そんな娘にも弱みはあったか」 「なあに、たまたま、お通が『 「何を言ってやがる。下心見え見えだぜ。だが、これを知ったら、お奈々が何と言うか見ものだな」久次郎はニヤニヤしながら孝吉に人情本を返した。 「ただ、本を貸しただけだ」と孝吉は顔色も変えずに本を受け取った。 「まあ、そんな事はどうでもいい。おめえを疑うわけじゃねえが、昨日はどこにいた」 「俺がお関を 「そうじゃねえが、一応、聞いておくんだ。こうなったら、怪しい奴を一人づつでも消して行かなきゃどうにもならねえ」 「俺が怪しいってえのか」 「おめえは七小町をみんな、ものにするって木崎の色地蔵に 「待ってくれ」と孝吉は慌てた。「確かに、そんな事を言ったが、お関は角次の女だ。そんな女に手を出す程、落ちぶれちゃアいねえ」 「ほんとに諦めたのか」 「諦めちゃアいなかったが、角次が留守じゃア勝負にならねえ。奴が帰って来たら張り合うつもりでいたんだ。そしたら、奴が帰って来る前に、お関は消えちまったってえわけだ」 「まあ、おめえの言う事は信じておくよ。それで、昨日は何してたんだ」 「昨日か‥‥‥ 「昼過ぎまで、一人で寝てたのか」 「ああ。お奈々はあれ 「ふん、たまにはいいぜ。ちょっと聞きてえんだが、裏にある蔵には何が 「まだ、疑ってんのか」 「そうじゃねえが、何となく、このうちに、あの蔵は不釣り合えのような気がしてな。ちょっとばかし大き過ぎんじゃねえのか」 孝吉は外を眺めながら、「もう、話しても大丈夫だんべ」と独り言のようにつぶやくと久次郎を見た。「あの蔵は島村の親分が、ちょっとした 「拷問だと?」 「ああ、お 「どうして、あんなとこで取り調べなんかするんでえ」 「番屋で拷問なんかしたら親分の評判が落ちるからさ。俺も一度だけ立ち会った事があるが、用心棒の旦那がニヤニヤしながら残酷な事をしてたぜ。姉ちゃんが言うには、あん中で 「責め殺したのか」 「逆さに吊るしといたら、くたばっちまったんだとさ」 「ひでえ事をしやがる。それで、その 「取り調べ中に病死って事で片付けたんさ。無宿者の一人くれえ死んだって何とでもなるのさ。姉ちゃんはそれ以来、あの蔵には近づかなくなったらしい。俺もここに住んじゃアいるが近づいた事もねえ」 「蔵ん中には何もねえのか」 「そんなの知るけえ。俺が 「鍵はあるのか」 「その辺にぶら下がってると思うが」 孝吉は土間に下りると 「こいつだと思うがな」 「よし、蔵ん中を見せてもらうぜ」 久次郎は鍵を受け取ると裏口の方に向かった。土間の隅に据え風呂が付いていた。 「風呂付きとは豪勢じゃねえか。お奈々もこの風呂に入ったんか」 「ええ、まあ‥‥‥兄貴もお紺さんとここを使ったらどうです。逢い引きには最高のうちですぜ。 「何を言っていやがる‥‥‥おめえ、もしかしたら、このうちを角とお関に貸したんじゃねえのか」 「へい、奴が旅に出る前に貸しましたよ」 「成程な」 裏庭には井戸があって、 久次郎は蜘蛛の巣を払いながら中に入った。奥の方に重そうな四角い石がいくつも積んであった。その上にギザギサになった洗濯板のような物が乗っている。壁には色々な形をした棒が立て掛けられ、太さも様々な縄が輪になってぶら下がっている。敷いてある 中に入る事なく、恐る恐る蔵の中を覗いていた孝吉は安心したように、「何もねえだんべえ」と言った。 「無宿者だけじゃなく、女もここで責めたんじゃねえのか」と久次郎は責め道具を眺めながら聞いた。 「そんな事ア知るけえ」 「これだけの蔵を遊ばせとくたア 「ここで賭場でも開帳するか」 「それもいいだんべえが、助八にちゃんと挨拶しねえと、おめえがその道具で責められる事になるぜ」 「脅かさねえでくれ。何となく気味が 「おめえ、わりと 「そうじゃねえが、俺アここに住んでんだ。化けて出られたらかなわねえ」 「それだけ恐れてるとこをみると、おめえも、その無宿者を 「いや、とんでもねえ」 久次郎は元通りに錠前を下ろすと鍵を孝吉に返した。そのまま、孝吉と別れ、再び、土手に上がると利根川を見回した。 いい天気になると思ったのに、 為吉は貞利の本をすべて持っているので怪しいと三日前、弟分の 大通りに出て、料理屋『鶴屋』に行こうとしたら、ばったり、お夢と出会った。三味線の入った箱を持った 「あら、お前さん、まだ、ウロウロしてんのかい」とお夢は薄笑いを浮かべた。 「お関がとんだ事になっちまったんでな」 「聞いたよ。バラバラにされたんだってねえ。二年前にも同じような事があったってえじゃないか。江戸が恐ろしいと思ったら、こんな田舎でも恐ろしい事が起こるんだねえ。早く、下手人を捕まえてくださいよ」 「ああ、わかってる。おお、そうだ。おめえに頼みてえ事があったんだ」 「何さ。また、 「そうじゃねえ。その事はあやまる。おめえの疑えは晴れた。その事じゃなくて、おめえの腕を見込んで頼むんだ。今度、うちの お夢は目付きを和らげて笑うと、「姐さんてえのは親分のおかみさんかい」と聞いた。 「いや、お 「そう。あたしゃア構わないけどね」 「すまねえな。後で使いの者をよこすから、そん時は頼まア」 「あいよ。立ち話も何だから、ちょっと、うちに寄ってかないかい」 お夢の色っぽい目付きに、ついぐらっと来たが、久次郎はじっと 「そうしてえとこだが、今は無理だ。今日は徳次たちはいねえのか」 「いないよ。どうせ、どっかの賭場だろ」 「昨日はどうだ」 「昨日? 徳さんを疑ってんのかい」 「そういうわけじゃねえが、お関と関係ある奴は一通り、調べなけりゃアならねんだ」 「あたしんとこにいたって言いたいけどね、昨日は来なかったよ。お光んとこにいたんじゃないのかい」 「お光ってのは誰でえ」 「 「上総屋ってえのは京屋の前の茶屋か」 「そうさ、行ってみな。いるかもしれないよ」 お夢と別れ、料理屋『鶴屋』を覗くと耕作はいなかった。徳次郎の所だろうというので、河岸問屋の『柳屋』に行ったが、徳次郎も耕作もいない。二人を見張らせていたのに怪しい所が何もなかったので、見張るのをやめてしまった事が悔やまれた。多分、中島の賭場にいるだろうと番頭は言う。親が甘いから遊んでばかりいて困ると番頭は小声で愚痴った。 『上総屋』のお光は徳次郎が目を付けただけあって可愛い娘だった。徳次郎の事を聞くと、昼前に耕作と二人でやって来て、しばらく話をしてから中島の賭場に行ったという。昨日も昼前に来て、半時ばかりいて、伊勢崎に行くと言って出掛けて行った。愛用の煙管が壊れたので、耕作と酒屋の伜、竹次と一緒に買いに行ったらしい。お光の様子から見て、まだ、徳次郎と深い仲にはなっていないようだった。 広瀬川に沿って中島に行き、忠次の代貸、為次が開いている賭場に顔を出した。しかし、ここにも徳次郎たちはいなかった。 賭場を後にした久次郎は質屋『和泉屋』の 境宿に帰った久次郎は『石屋』の与之助と『桶屋』の長次から話を聞いた。二人とも昨日は町から出てはいなかった。長次は桶松と同じ桶屋の伜だが別の店で、桶松は上町の桶屋、長次は下町の桶屋だった。 長次の家の隣が、お通の店なので、覗いてみるとお通は店番をしながら、孝吉から借りた『 お関に言い寄っていた男たちで、残るは世良田の孫三郎と伊勢崎の仙太郎の二人だった。どうせ、二人とも関係ないとは思うが一応、話を聞かなければならない。まもなく日が暮れ、貞利がやって来るので、明日にする事にして、七小町たちから話を聞く事にした。 まず、料理屋の桐屋に入って、お粂を呼んだ。お粂から、お関の胴体が中瀬の下流で見つかったと聞かされた。 「お昼頃、八州様がやって来て、色々と調べてたの。そしたら、木崎の親分さんとこの子分だと思うんだけど、その知らせを持って来て、八州様は中瀬の方に行ったんです」 「胴体は川に捨てられたのか‥‥‥」 「そうみたい‥‥‥でも、見つかってよかった。胴体がないんじゃお葬式もできないわ」 泣き明かしていたのか、お粂の目は腫れていた。その目がまた潤んで来ている。 「そうだな‥‥‥それで、胴体は境に来たのか」 「ええ」とうなづいて、お粂は涙を拭いた。「 「先生も一緒だったのか」 「ええ。しばらく、番屋で調べてたけど、お関ちゃん、ようやく、うちに帰れたみたい」 「そいつはよかった‥‥‥それで、先生はどこに行ったんだ」 「八州様と一緒に本陣に入ったようです。しばらくして、木島の親分さんはまた出てったけど、先生はまだ、出て来ないみたい」 「本陣で八州の旦那と話し込んでるのか」 「絵の話でもしてるのかしら」 「八州の旦那は江戸っ子だ。江戸の話でもしてるんだんべ」 その後、越後屋のお奈々、五月屋のお政から話を聞いたが、手掛かりになるような事は何も得られなかった。井筒屋のおゆみは相変わらず、家にはいなかった。おりんの店にいるだろうという。 井筒屋から出ると隣の蘭方医、随憲先生の家から塾生が三人出て来た。声を掛けて、仙太郎の事を聞くと、仙太郎は昼前に顔を出したという。お関が殺されたという噂を聞いて驚いてやって来て、しばらく、お関の話をしてから、うどん屋で昼飯を食べると力なく帰って行ったらしい。 「仙太郎ってえなアどんな奴なんだ」と久次郎は塾生に聞いてみた。 「頭はいいらしいが、それだけで、面白くも何ともねえ奴さ」と塾生の一人が笑いながら言った。「うちが金持ちだから、江戸から色んな本を取り寄せちゃア読みあさってるらしい。確かに頭はいいが、付き合いたかアねえ野郎だな」 「奴はお関が好きだったらしいじゃねえか」 「好きだったらしい。でも、お関じゃなくても、七小町なら誰でもよかったんじゃねえのかな。好きだと言っても、声も掛けられねえし、側にも行けねえ。俺たちが面白半分に小町たちを紹介してやったら、あいつ、大喜びしてたぜ」 「そうか、仙太郎ってえなアそんな野郎か。呼び止めて、すまなかったな」 塾生たちは下町の方に帰って行った。 村田屋を覗くと店仕舞いをする所だった。おしんから話を聞いたが、やはり、何も知らなかった。仙太郎の事を聞いてみるとおしんは知っていた。 「随憲先生のとこに時々来る人でしょ。お昼頃来て、煙草入れを買ってくれました」 「奴は何か言ってたか」 「何も。ただ、煙草入れを見せてくれって言っただけです。青白い顔をしていて、何となく、具合が悪そうでしたよ」 久次郎はおしんにうなづくと庄太を見て、「おい、おめえも奴を見たのか」と聞いた。 「へい、なよなよっとした 「あら、そうかしら」とおしんは首をかしげた。 「そうさ。おしんちゃんが俯いて、煙草入れを出してる時、奴はおしんちゃんのうなじをじっと見てたんだ」 「そうだったの。いやねえ、気味が悪いわ」 「よく来るのか」と久次郎はおしんに聞いた。 「いいえ。最初、来た時は塾の人たちと一緒に来て、その後、二回くらい来たかしら」 「二、三度しか来ねえので、よく覚えてるな」 「だって、来る度に、何かを買ってくれるんですもの。それも、結構、高価な煙管とか煙草入れとか買ってくれるんで覚えてたんです。そんな人、滅多にいませんから」 「ほう。そんないい物を買ってくのか」 「最初、来た時、塾の人が、こいつは金持ちの伜だから、一番高い煙管を売ってやれって言ったんです。冗談だろうって思ってたら、本当に一番高いのを買ってくれたんです。その後も、来る度に高いのを買ってくれます」 「成程な」 久次郎は庄太におしんを頼むぞと言うと店を出た。 日がすっかり暮れ、皆、戸締まりをして、町中はシーンと静まっていた。出歩いている者たちも少ない。昨日の夜から町の者たちは正体のわからない下手人に脅えて、皆、日が暮れると同時に店を閉め、出歩かないようになってしまった。 曇っていて月も見えない薄暗い中、おりんの居酒屋だけがポツンと明るかった。久次郎はその明かりに吸い込まれるように縄暖簾をくぐった。
|
1.登場人物一覧 2.境宿の図 3.「佐波伊勢崎史帖」より 4.「境町史」より 5.「境町織間本陣」より 6.岩鼻陣屋と関東取締出役 7.「江戸の犯罪と刑罰」より 8.「境町人物伝」より 9.国定一家 10.国定忠次の年表 11.日光の円蔵の略歴 12.島村の伊三郎の略歴 13.三ツ木の文蔵の略歴 14.保泉の久次郎の略歴 15.歌川貞利の略歴 16.歌川貞利の作品 17.艶本一覧